新しい癌克服戦略への1つの道
UICCシンポ「家族性腫瘍とがん予防」開催 宇都宮譲二(兵庫医科大学教授・外科)
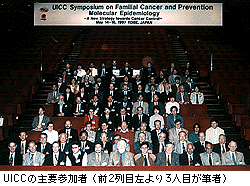
「家族性腫瘍とがん予防会議週間」が,さる5月13-17日にわたり,神戸市の神戸国際会議場において実施され,第3回家族性腫瘍研究会などが開催された。また,その一貫として期間中の5月14-16日の3日間,同研究会などの主催による,UICCシンポジウム「家族性腫瘍とがん予防-分子疫学(Symposium Familial Cancer and Prevention/Molecular Epidemiology-A New Strategy towards Cancer Control)」が開かれたので報告する。
●癌克服をめざすプロジェクト
家族性腫瘍とは,遺伝性または共通の環境要因により発症する腫瘍であり,癌全体の5-10%程度であるが,その研究は発癌理論の解明とその対策の確立の近道であることがわかり注目を浴びている。近時,急速な発展を遂げた分子生物学を用いた家族性腫瘍研究の結果,大腸癌,乳癌,小児癌,その他多くの腫瘍の原因遺伝子が次々に明らかにされた。その結果多段階発癌の分子生物学的シナリオが解明,同時に遺伝子(素因)診断が可能となり,癌予防戦略の研究は大きく展開されつつある。
UICC(国際対癌連盟)ではこのことに注目し,1990年に癌疫学と予防プログラムの1つのプロジェクトとして,「家族性がん予防計画」(Walter Weber委員長兼欧州・アフリカ拠点担当者,John J. Mulvihill米拠点担当者,宇都宮譲二アジア・オセアニア拠点担当者)を発足せしめ,家族性腫瘍の研究と対策を通して癌克服をめざす戦略を展開することになった。
その一環として,今回専門家会議としてUICCシンポジウムを開催。本シンポジウムは,分子生物学的研究成果をいかに効果的に癌死削減に結びつけるかというTranslational Study(展開研究)の推進を目的としたものとしては初めての試みである。またわが国におけるUICC本体の活動としての集会は1966年の第9回国際癌学会以来の貢献である。
●アプローチ別にプログラム編成
プログラム編成も特徴的であった。総計207題に達する演題を,まず研究手法(アプローチ)別に癌の,A.遺伝疫学,B.遺伝子診断,C.倫理問題とカウンセリング,D.対策という4領域に大別し,さらに計13の研究課題に細分(表参照)した。さらにワークショップ(72題)とポスターセッション(107題)に振り分け,それぞれを代表する国際的指導者によるプレナリー講演(18題)が行なわれた。また,国際パネルディスカッションでは各国の現状と将来のあり方も討議された。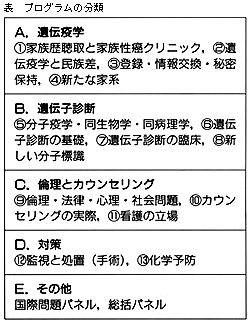
シンポジウムへの参加者は,日本(255名),アメリカ(34),イギリス(10),スイス,オーストラリア,フランス,インド,イタリア,オーストリア,ドイツ,韓国,カナダ,マレーシア,など全19か国から総計343名であった。また分野別では遺伝学(16.3%),分子生物学(13.4%),外科(12.3%)の他,生化学,病理学,疫学,内科,免疫学,小児科,遺伝カウンセラー,泌尿器科,倫理学,看護学,皮膚科,統計学,婦人科,微生物学,放射線学,コメディカル,学生,など医学の内外26分野にまたがった。
また主な発表者として,国外からはM. Gurger(UICCの立場,以下括弧内は発表演題),J. J. Mulvihill(遺伝性癌カタログ),H. T. Lynch〔HNPCC(遺伝性非腺腫症性大腸癌)の臨床〕,D. Easton(乳癌の遺伝疫学),C. Harris(p53遺伝子と分子疫学),R. Montesano(食道癌の分子疫学),G. Stermermann(アメリカ在住日本人近親者の癌リスク),S. Narod(乳癌の民族間の遺伝疫学的差異),R. W. Miller(遺伝性疾患と腫瘍病変),P. Meera Kahn(FAPの遺伝子診断),E. Harlow(RB蛋白質),G. Thomas(NF21癌抑制遺伝子),J. Jass(HNPCCの病理),J. St. Johns(家族歴に基づく大腸癌集団検診),A. de la Chapell(HNPCCの遺伝学),G. Petersen(遺伝子診断の癌予防の意義),S. Wells(MENの分子遺伝学),K. Nugent(FAPとデスモイド),H. Vasen(HNPCCの調査と治療),B. Zbar(遺伝性腎臓癌の遺伝疫学),B. Korf(神経線維腫症の診断と治療),K. H. Keamer(色素性乾皮症の癌予防),D. Kwiatkowski(結節性硬化症遺伝子),D. Porter(家族性多発性軟骨腫),M. Green(異形成母斑),G. Fraser(家族性癌ユニット),P. Lynch(法律問題),R. Porkosky(生命保険問題),H. Mueller(医師カウンセラーの立場),E. Gettig(遺伝カウンセラーの立場),A. Arderen‐Jones(ナースの立場),R. Shatzkin(癌予防の分子生物学的見解),J. Burn(FAPに対するCAPPの効果),G. Wind(FAPに対するサリンダック座薬),A. Howell(家族性乳癌とタモキシフェン),W. Bodmer(家族性癌研究の将来)であった。
さらにわが国の主な演者および口演内容としては,杉村隆(わが国の癌研究,以下括弧内は発表演題),武部啓(HUGO倫理委員会報告),三木義男(BRCA1/2診断),宮木美知子(HNPCCの分子生物学),湯浅保仁(HNPCCの分子生物学),横田淳(家族性胃癌),樋野興夫(結節性硬化症),岩間毅夫(家系登録),馬塲正三(遺伝性大腸癌の外科),高見博(MENの遺伝子診断),佐谷秀行(NFの分子生物学),星野一正(日本の生命倫理),恒松由記子(倫理問題等),大倉興司(遺伝カウンセラー),石川雄一(ウェルナー症候群)である。
●遺伝子素因診断の臨床的導入などが話題に
本シンポジウムでは,家族性腫瘍病態の民族・地域差,新しい家系,分子生物学的新知見などの発表が多く見られたが,特に注目すべき話題としては,諸刃の刃(やいば)といわれる遺伝子素因診断の臨床的導入の健全なる方策を探ることである。一般の癌の発癌責任遺伝子(APC,hMSH2/hMLH1,BRCA1/2,RET等)の同定単離により,胚細胞変異解析による発症前診断(いわゆる素因診断)が可能となった。しかしその精度・経済性の向上,臨床形質発現経過と様式の個体・家系・民族間特異性の認識等の生物学的諸問題とと もに,被験者の私秘侵害,生命保険上の不利,苦悩の遷延,結婚・就職の不利など「倫理・法律・心理・社会問題」が大きく浮き彫りにされた。前者は経済的利益・医学研究業績課題として必然的に推進され得るが,後者の研究は地味で医学者にとって魅力的とはいえない。
その意味では,UICCシンポジウムがグローバルな立場で登録組織,倫理ガイドライン,遺伝カウンセラーの必要性,看護領域の立場などの議論に多くのスペースを提供したのは大きな意味があった。特にわが国で大きく後退していた遺伝カウンセリングの領域に光があてられ,わが国の看護者が欧米の同僚と連携する機会があったことは成果の1つであると感じている。
事実,本シンポジウム以後,遺伝子診断の企業化に拍車がかかりつつある一方,家族性腫瘍研究会倫理委員会の活動も展開して,きたる9月25日から京都の京都国際会議場で開かれる第56回日本癌学会(第27回日本家族性腫瘍研究会同時開催)のサテライトシンポジウムとして,倫理等問題のガイドラインに関する公開説明討論会が行なわれる予定である。
UICCでは今回の成果を基に,Familial Cancer Prevention Projectのさらなる活動を展開することになった。また本シンポジウムの内容は,単行本としてまとめられ明年ブラジルのリオデジャネイロで開催(1998年8月23-30日)される第17回国際癌学会に向けて出版の予定である。
