1996年ノーベル医学・生理学賞解説
免疫機構におけるT細胞の 基本的な認識の仕組みを解明
谷口 克 千葉大学教授・高次機能制御研究センター免疫機能分野,日本免疫学会長昨年度のノーベル医学・生理学賞は,オーストラリアのRolf M.Zinkernagel(チューリヒ大実験免疫学研究所長)とPeter C.Doherty(テネシー大准教授)に授与された。受賞業績は,オーストラリア国立大での共同研究「細胞性免疫防御の特異性」。本紙では谷口克氏に,今回の授賞の対象となった業績の解説と評価をしていただいた。
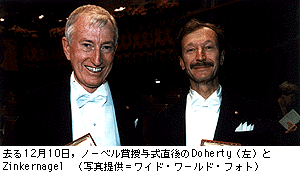
今回のノーベル医学・生理学賞を受賞したZinkernagelとDohertyの業績は,免疫機構において,リンパ球であるT細胞がどういう抗原認識の仕方をしているかを解明したというものです。この論文は1974年の「ネイチャー」誌に載りました。
T細胞はどのように認識しているか
 T細胞は1970年代の初頭に発見されましたが,それまでは,B細胞がつくり出す抗体の研究が行なわれていました。免疫系の2つの重大な特徴がとして,(1)非常に多様(あらゆる種類の異物に対処できる膨大なレパートリーを持つ)で,(2)特異性(ある異物を認識するものは他の異物には反応しない)を持つことが発見されたのは,抗体の研究によってなのです。
T細胞は1970年代の初頭に発見されましたが,それまでは,B細胞がつくり出す抗体の研究が行なわれていました。免疫系の2つの重大な特徴がとして,(1)非常に多様(あらゆる種類の異物に対処できる膨大なレパートリーを持つ)で,(2)特異性(ある異物を認識するものは他の異物には反応しない)を持つことが発見されたのは,抗体の研究によってなのです。
そこに,もう1つの重要なリンパ球であるT細胞の存在が明らかになりました。しかしT細胞の抗原認識の方法はわかりませんでした。
当時想像されていたのは,B細胞にある抗体と同じものがT細胞にもあって,B細胞と同じ認識の仕方をしているのではないかというものです。その根拠は,T細胞が抗体と同じような非常に高い特異性を持つということでした。例えばインフルエンザウイルスと反応するT細胞は,決してエイズウイルスとは反応しないというように。しかし宝探しの結果,抗体と同じではないことがわかり,T細胞には別の認識機構が存在するということになったのです。
自己に反応するMHC拘束性
多くの場合にそうなのですが,研究は,「現象論」と「モノ探し」という2つのまったく違うステップで進んでいくものです。現象論は重要で,それがモノすなわち構造を解く鍵になります。ZinkernagelとDohertyは,T細胞がどのように認識するのかという現象論をまず解明しようと考え,焦点を絞りました。細かい実験は省略しますが,まずネズミAに髄膜炎を起こすLCMウイルスを感染させて,それに対するキラーT細胞をつくり,そのキラーT細胞を取り出します。一方,Aとは遺伝的に異なるネズミB,Cにも同じウイルスを感染させます。そして試験管の中にAのキラーT細胞と,A,B,Cの感染細胞を入れると,Aのキラー細胞は,Aの感染細胞は殺すけれども,B,Cにはまったく影響しません。
これらの実験から,T細胞は異物を認識すると同時に,自分と遺伝的に同じMHC(主要組織適合抗原)を持つ細胞を認識して標的にする性質を持つことがわかりました。それを「遺伝的な拘束」と言います。
例えば,私がインフルエンザに感染した場合,私のT細胞は「私の」感染細胞を標的にすることができますが,同じインフルエンザウイルスに感染した別の人の細胞を一緒にしても,T細胞はその人の感染細胞を認識せずに無視してしまうのです。
2人は次に,MHC拘束性がどのように機能するのかという仮説を立てました。仮説の1つは,T細胞受容体は1つで,それが感染によって変化した自己(MHC)を認識するというもの(modified self)でした。そしてもう1つは,抗原を認識する受容体と自己を認識する受容体というように,T細胞に2つの受容体が存在するというもの(dual recognition)です(図)。
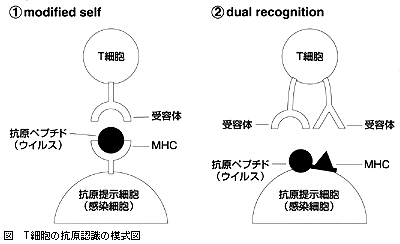
その後の研究に引き継がれたもの
彼らが仮説を出したので,多くの研究者がそれを検証するようになりました。そして結局,T細胞の受容体は1つで,感染細胞のMHC分子と,それに結合した抗原ペプチドの両方をセットで認識することが証明されました(図の(1))。T細胞の認識が物質レベルで語られるようになったのは,1984年にDavisやTak-MakによりT細胞抗原受容体遺伝子の構造が明らかになってからです。MHCクラスI分子の場合,MHCの持つ溝に抗原ペプチドがはまりこむような形で結合し,細胞表面で安定化します。そしてT細胞がMHCとペプチドを同時に認識するのです。自己であるMHC分子にペプチドが入ることによって自己がモディファイされるわけですね。これを立証したのは,1987年にMHCクラスI分子の結晶化に成功したBjorkmanです。
このMHCクラスI分子の溝に入るペプチドの長さは,アミノ酸9個分しかありません。そのうち数個はMHC側に結合しています。したがって,たった数個のアミノ酸で,T細胞受容体がなぜ特異的に認識できるのかという疑問があります。これに対しては,入れ物であるMHCが,中のアミノ酸配列によって形を変えるのではないかという考えがあります。
先日の「ネイチャー」(1996年11月14日号)に,D.C.Wileyらが,MHC分子に結合した抗原ペプチドとT細胞受容体との複合体の分子構造を完全に解明したと報告しています。これによると,T細胞受容体は,ペプチドをはさんだMHCに食いつくように結合しているようです。
食いつく口の大きさは決まっているため,うまく形がはまるものは限られています。それで特異性ができて,10の15乗の多様性を生むのかもしれません。目で見ると,非常にたくさんのことがわかります。
Zinkernagelのもう1つの業績
以上のように,ZinkernagelとDohertyの業績は,T細胞の認識についての明確な仕組みを考えるきっかけとなったルールを発見したことです。ところでZinkernagelはこれ以外にも重要な研究をしています。それは74年の発見が発展したもので,最終的に結果が出たのは1980年代半ば以降です。
免疫系は自己と非自己を区別するものといわれますが,彼は,T細胞が自己と非自己を区別する重要なリンパ球であり,しかもそれが胸腺によっているということを証明したのです。
先ほどのLCMウイルスの動物実験で確かめられたMHC拘束性は,どこで学習されるのかというのが彼の興味でした。彼は,T細胞は胸腺で育つから,胸腺に秘密があると考えました。そこで,ネズミAにネズミBの胸腺を移植し,Aにとって何が自己になるかを問うたのです。
Bの胸腺を移植したネズミAにウイルスを感染させて,それに対するキラーT細胞を作ります。一方,胸腺移植前のネズミAとネズミBにウイルスを感染させて感染細胞を作り,B胸腺移植ネズミAのキラーT細胞がどれを殺すのかを調べました。そうすると,Bの感染細胞は殺すけれどもAの感染細胞は殺しません。つまり胸腺がBになったために,リンパ球それ自身はAであるにもかかわらず,自分はBだとネズミAは思うのです。
すなわち,胸腺が自己と非自己を分けている臓器だと言えます。ノーベル賞の対象となった研究とこの研究を一緒に考えると非常にわかりやすいと思います。
「現象論」と「モノ探し」
サイエンスの進め方には,現象論と,物質を追いかけるモノ探しの2つの面があると言いました。最近のノーベル賞受賞者は,物質を根拠に謎を解明した人がほとんどですね。しかし今回の2人は最近のノーベル賞の傾向とは少し違い,現象論で受賞しました。そういう意味では,科学のもう一面を大切にした,ノーベル賞選考委員会の大ヒットだと思っています。対象の業績が出されてから20年以上たっての受賞ですが,これは無理もないことでしょう。現象論の評価の難しいところは,それがモノで証明されないと,価値がなかなかわからないことですね。現象論の研究に対しても周囲が支えていくシステムが必要でしょう。
最近の研究の方向として,森を見ずして木を見るようなものが多くなってきているのは事実です。そういう場合には,その研究が生物学の中でどういう意味を持つかを,常に問いかけなければいけないし,自分のしていることが,生物学の法則を見つけるための研究なのかどうかを常に問う必要があると思います。
(談)
