DDW-Japan 1996 in Kobe
日本消化器関連学会週間 開催
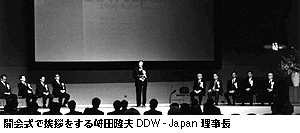
今年で4回目を迎えた1996年日本消化器関連学会週間(Digestive Disease Week-Japan 1996:DDW-Japan'96)がさる4月18-20日の3日間,神戸市の神戸国際展示場,他において開催さ れた。
周知のように,DDWは複数の関連学会を時と場所を同じくして開催することによって,費用や 時間の削減につながるとともに,集中学習できるメリットがあるという構想のもとにアメリカで生まれ, ヨーロッパ,そしてわが国で実現した経緯がある。ちなみにアメリカでは現在,肝臓学会(AASLD), 消化器病学会(AGA),消化器内視鏡学会(ASGE),消化器外科学会(SSAT)の4学会で構成されてい る。
今回は新たに日本肝臓学会の全面参加を得て,第51回消化器内視鏡学会(国立国際医療センター 梅田典嗣氏),第32回胆道学会(東女医大 大井至氏),第82回消化器病学会(阪市大 小林絢一氏), 第27回膵臓学会(神戸大 斎藤洋一氏),第32回肝臓学会(帝京大 山中正己氏)の5学会の全面参加に 加えて,消化器外科学会(東医歯大 遠藤光夫氏),消化器集団検診学会(日大 小黒八七郎氏),大腸 肛門病学会(帝京大 小平進氏),消化吸収学会(秋田大 正宗研氏)の部分参加となり(カッコ内は会 長),さらにまた今年は会期も1日短縮して3日間とするなど,DDWの本来の趣旨を実現するために会議 の運営上にもさまざまな工夫が試みられた。
開会式では,崎田隆夫DDW-Japan理事長をはじめとする各学会長が揃って,当初は大震災に見舞 われた神戸市での開催を危惧した事実を披瀝し,学会開催にいたるまでの関係者各位の尽力に深謝の辞を 示すとともに,「この学会の開催が神戸地区の復興に少しでも寄与できれば,という気持ちが会員の間に 大きく広まっていることも心暖まることである」と述懐し,しばし会場の共感を呼んだ。
本号では会議の中からいくつかの話題を拾ってみた(関連記事 「DDW-Japan 1996 パネルディスカッションより」)。


パネル「肝癌はどこまで解明されたか」
“molecular biologyとhumanismの対話”という消化器病学会のコンセプトにそって,今回のDDW‐ Japanではいくつかの“C & C(Consensus & Controversies)シリーズ”が企画されたが,開会式直後に開 かれたパネルディスカッション「肝癌はどこまで解明されたか-肝癌の早期診断,予防,治療について (消化器病・肝臓・消化器外科合同:司会=山口大 沖田 極,久留米大 神代正道,東大 幕内雅敏の 各氏)」もその1つである。高癌化状態およびstaging,gradingによる予知・予防
まず樋野興夫氏(癌研)は,「ヒト癌の発生・予防には,“高癌化状態(hypercarcinogenic state "の理 解が重要である」と指摘。高癌化状態とは,癌化のinitiation(起始)が起こりやすい状態,もしくは起始 細胞にpromotion(促進)のかかっている状態で,「遺伝子変化が生じやすく,また蓄積しやすい組織の 状態」と定義され,具体的な代表例としてヒトの慢性肝炎状態があげられる。樋野氏は,「高癌化状態か ら正ないし低癌化状態(normo-or hypocarcinogenic state)にすることが肝癌の発生・再発の予防につながる」 との視点から,高癌化状態からみたヒト肝癌発生の問題を考察した。八橋弘氏(国立長崎中央病院)は,肝癌発生時に非癌病変,慢性肝炎からの経過発癌例の肝組織 所見をstagingとgradingに区分して評価することによって,発癌の高危険群を明確化し,さらに発癌の予知 が可能かどうかを検討。その結果,発癌のリスクはgradingでなくstagingによって決定され,「stagingは恒 常的指標であり,肝癌発生母地となる肝硬変にいたる確率と期間を反映することで,発癌を予知する因子 となり,gradingは発癌発生の観点からは並列に位置するのではなく,stagingを上昇させる従属的因子であ る」と報告した。
血流動態による早期診断
工藤正俊氏(神戸市立中央市民病院)は,肝細胞癌の早期診断・早期治療の観点からは,前癌病変か ら初期病変への画像的変化を明確に認識することの重要性を指摘して,血流動態から肝癌の脱分化と進展 を分析した。工藤氏によれば,肝細胞癌やその境界病変の結節内血流動態は結節の生物学的特性をよく反 映しており,その結節の悪性度・治療的要求度・多段階発癌過程のどのステップにあるかなどを知ること ができるため,「血流動態から肝癌の脱分化と進展を分析することは重要である」と述べた。治療:PEITか切除か
小肝細胞癌に対する初回治療としては,PEIT(経皮的エタノール注入療法)と肝切除が選択されてい るが,田中正俊氏(久留米大)は,同じ条件のもとにおける両者の予後を比較検討。その結果,腫瘍径 20mm以下ではPEITと肝切除のいずれの治療選択でも同じような治療成績が得られるが,「21mm以上で 中低分化の肝細胞癌には肝切除,次いでPEITの順で治療を選択したほうがよい」という結論を得た。一方,外科の立場から切除・PEITおよびTAE(肝動脈塞栓療法)の治療成績を比較検討した竜崇 正氏(国立がんセンター東病院)は,有意な予後因子として(1)clinical stage,(2)腫瘍数,(3)腫瘍径をあげ, 「PEITで対応してもよい肝細胞癌は,腫瘍径21mm以下までで,それ以外のclinical stage I,IIの肝細胞癌に 対しては,まず切除を第一選択とすべき」と指摘した。
IFN治療と肝癌
近年,C型慢性肝炎に対してIFN(インターフェロン)療法が行なわれるようになり,C型肝癌の発生 母地そのものに対する治療が可能になってきた。横須賀収氏(千葉大)は,IFN治療がC型肝炎関連肝癌の発症予防につながるかどうかを,IFN非 投与例を対照として,著効例・非著効例における発癌率をも検討した。進行したC型慢性肝疾患ほど肝癌 の高危険群と考えられ,IFN治療によって各病型別でも肝癌発生率の低下が認められるが,横須賀氏は, 「特にIFN著効例では,肝癌の発生が極めて抑制されており,C型肝炎関連肝癌の発生予防をなしうる可 能性が示された」と報告した。
また,C型肝硬変に対するIFNによる肝発癌抑制効果を検討した西口修平氏(阪市大)も,「IFN はC型肝硬変の炎症を緩和し,経過中に大部分の症例で代償期が維持でき,IFN投与は肝癌の発生を有意 に抑制した」と述べた。


パネル「肝移植―実施に向けての医学的課題と将来」
パネルディスカッション「肝移植―実施に向けての医学的課題と将来」(司会=埼玉医大 藤原研司 氏,京大 山岡義生氏)では,はじめに司会の藤原氏より「肝移植の実施における臨床・基礎での医学的 課題に焦点を絞って問題点を明確にしていきたい」とディスカッションの狙いが述べられ,同じく山岡氏 からは「いざ実施する場合の臨床上の問題点」が(1)手術手技,(2)移植肝が働くかどうか,(3)免疫の3点に ついてスライドによって提示された。米国の肝移植の現場から
臨床からは2名の演者が登壇。古川博之氏(ピッツバーグ大)は米国において末期肝疾患に対する標 準的治療法として定着してきた脳死ドナー肝移植の現況と問題点を報告し会場の注目を集めた。古川氏は 今後の解決すべき課題として(1)免疫抑制療法,(2)レシピエントの選択,(3)臓器不足をあげ,とくに(1)に ついて,現在,免疫抑制剤からの離脱や長期的に免疫寛容を誘導するために肝移植と同時に骨髄移植が試 みられていることを示した。また日本における生体肝移植については田中紘一氏(京大)が報告。これまでの成績が提示され, 成人症例への適応拡大,医学面,社会面双方でのドナー選択などの今後の課題が指摘された。
