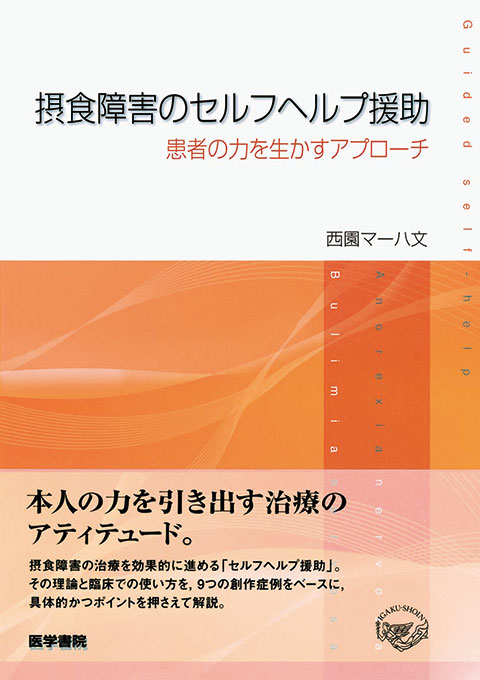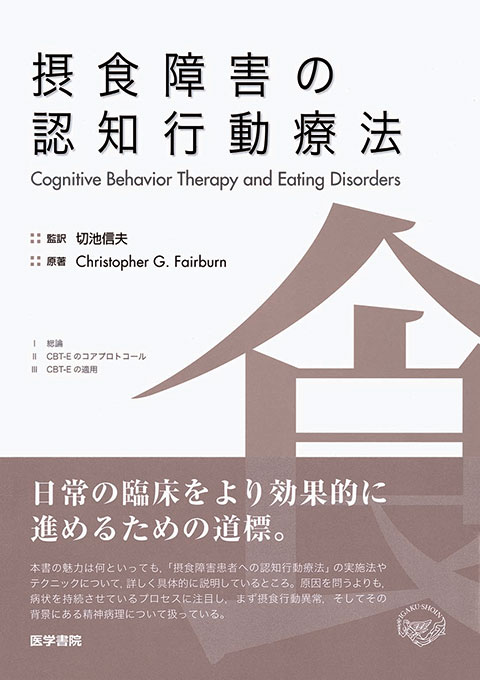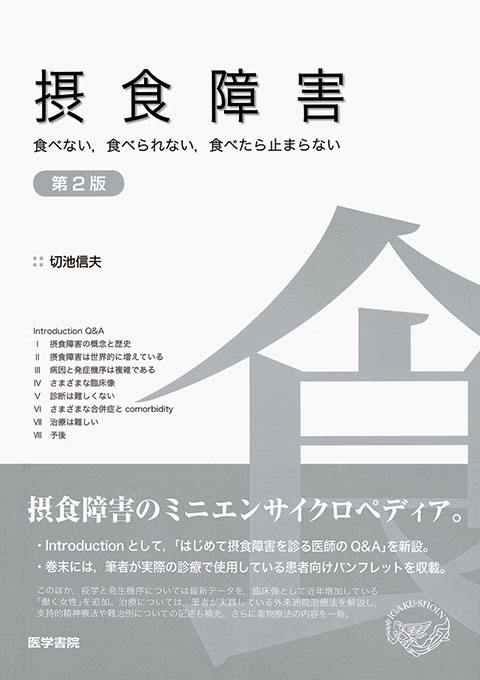摂食障害のセルフヘルプ援助
患者の力を生かすアプローチ
患者の力を生かして摂食障害の治療を効果的に進める
もっと見る
「セルフヘルプ援助」とは、患者本人の力を引き出しながら治療していくアティテュード。摂食障害の治療を効果的に進めるその理論と臨床での使い方について、9つの創作症例をベースに、さらに資料編の「患者の力を生かす13のツール」も交えながら、具体的かつポイントを押さえて解説。有機的で立体的に張り巡らされたクロスリファレンスによって、「知識がつながる。理解が深まる。そして実践したくなる!」
| 著 | 西園マーハ 文 |
|---|---|
| 発行 | 2010年05月判型:B5頁:232 |
| ISBN | 978-4-260-01044-3 |
| 定価 | 3,740円 (本体3,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
摂食障害は,近年,一般診療で目にする「普通の病気」になってきた。学生相談室など,医療以外の相談に訪れる者も多い。しかし残念ながら,摂食障害に本格的に取り組む専門家はなかなか増えない。摂食障害の治療は難しいというイメージが浸透してしまったようにも思われる。
一方,研究の世界では治療研究の進歩が著しい。しかし,研究対象となるのは,摂食障害の診断基準を満たし,併存診断がなく,年齢がある枠の範囲,しかも毎週治療に通えるなど,条件が整った模範的な対象である。実際には,このような患者は少なく,実地臨床と研究のギャップは大きい。現実の患者に対峙するときは,良い結果を誇る認知行動療法などの技法をどう実地に応用するかというところに臨床的センスが求められる。
摂食障害の本格的な治療法については,さまざまな参考書が手に入る。しかし,実地応用に必要な考え方については,これまで参考書がほとんどなかった。筆者は,実地応用の中では,「本人のセルフヘルプを援助する」姿勢(guided self-help)が非常に大事なのではないかと考え,これをテーマに本書を執筆することにした。この本のコアである症例部分は,「本人のセルフヘルプを援助する」場面をできるだけ臨場感を持って示すために書いた架空の症例である。「最初からこんなに言語化できる患者はいない」「こんなに診察時間はとれない」と思われる方も多いと思う。それぞれの治療者の臨床場面では,ここで挙げたことをさらに実地応用していただければと思う。
本書は,筆者がロンドンのInstitute of Psychiatryの摂食障害ユニットで研究をしながら,英国各地で摂食障害の治療に携わる方々の話を聞いていた1年の間に執筆したものである。本文で,「海外では」という記述の部分が英国の話に偏っているのはそのためである。いわゆる「箱モノ」的には,英国の病院がすべて日本より優れているとは言えない。しかし,治療技術,臨床的アイデア,職種間の連携には,学ぶべきことが非常に多かった。その基本にあったのが,この本で紹介した本人の力を引き出しつつ治療をしていく治療態度であった。今後,日本においても,摂食障害の専門家が増えることを切に願っているが,一方で「摂食障害に特化した専門家」でなくても,基本的なトレーニング,患者との信頼関係,周囲とのチームワーク,患者がおかれている状況に対する洞察力などを駆使すれば援助可能な対象も多いということは明るい希望である。このような仕事の際に,この本を道標に使っていただければと思う。
執筆中は,医学書院 西村僚一さんの遠隔指導に助けられた。締め切り時間がロンドンより8時間早いことに気付いて慌てたり,良い日本語が浮かばず困ったこともあった。1日のうちに,英国の仕事と執筆の両方をやっていたこの特殊な執筆状況が,この本の中の海外事情や海外からの参考書を読む際の距離感を縮めるのに少しでも役に立っていたら嬉しいことである。
2010年4月 桜の後の雪の日に
西園マーハ文
摂食障害は,近年,一般診療で目にする「普通の病気」になってきた。学生相談室など,医療以外の相談に訪れる者も多い。しかし残念ながら,摂食障害に本格的に取り組む専門家はなかなか増えない。摂食障害の治療は難しいというイメージが浸透してしまったようにも思われる。
一方,研究の世界では治療研究の進歩が著しい。しかし,研究対象となるのは,摂食障害の診断基準を満たし,併存診断がなく,年齢がある枠の範囲,しかも毎週治療に通えるなど,条件が整った模範的な対象である。実際には,このような患者は少なく,実地臨床と研究のギャップは大きい。現実の患者に対峙するときは,良い結果を誇る認知行動療法などの技法をどう実地に応用するかというところに臨床的センスが求められる。
摂食障害の本格的な治療法については,さまざまな参考書が手に入る。しかし,実地応用に必要な考え方については,これまで参考書がほとんどなかった。筆者は,実地応用の中では,「本人のセルフヘルプを援助する」姿勢(guided self-help)が非常に大事なのではないかと考え,これをテーマに本書を執筆することにした。この本のコアである症例部分は,「本人のセルフヘルプを援助する」場面をできるだけ臨場感を持って示すために書いた架空の症例である。「最初からこんなに言語化できる患者はいない」「こんなに診察時間はとれない」と思われる方も多いと思う。それぞれの治療者の臨床場面では,ここで挙げたことをさらに実地応用していただければと思う。
本書は,筆者がロンドンのInstitute of Psychiatryの摂食障害ユニットで研究をしながら,英国各地で摂食障害の治療に携わる方々の話を聞いていた1年の間に執筆したものである。本文で,「海外では」という記述の部分が英国の話に偏っているのはそのためである。いわゆる「箱モノ」的には,英国の病院がすべて日本より優れているとは言えない。しかし,治療技術,臨床的アイデア,職種間の連携には,学ぶべきことが非常に多かった。その基本にあったのが,この本で紹介した本人の力を引き出しつつ治療をしていく治療態度であった。今後,日本においても,摂食障害の専門家が増えることを切に願っているが,一方で「摂食障害に特化した専門家」でなくても,基本的なトレーニング,患者との信頼関係,周囲とのチームワーク,患者がおかれている状況に対する洞察力などを駆使すれば援助可能な対象も多いということは明るい希望である。このような仕事の際に,この本を道標に使っていただければと思う。
執筆中は,医学書院 西村僚一さんの遠隔指導に助けられた。締め切り時間がロンドンより8時間早いことに気付いて慌てたり,良い日本語が浮かばず困ったこともあった。1日のうちに,英国の仕事と執筆の両方をやっていたこの特殊な執筆状況が,この本の中の海外事情や海外からの参考書を読む際の距離感を縮めるのに少しでも役に立っていたら嬉しいことである。
2010年4月 桜の後の雪の日に
西園マーハ文
目次
開く
第1部 理論編
第1章 摂食障害の特徴と治療-治療の難しさを乗り越えるために
1 はじめに
2 症状の理解-セルフヘルプに導入しやすい症状
3 セルフヘルプ,指導付きセルフヘルプ
第2章 さまざまな治療法とセルフヘルプの生かし方
1 従来の治療法の再考
2 指導付きセルフヘルプに活用できる考え方と技法
3 セルフヘルプを援助する治療者像
4 実際の会話にみる治療関係
5 医学的処置が必要な状況
第3章 治療の流れとセルフヘルプの生かし方
1 多職種連携と本人の治療動機
2 組織を超えた初診時の連携
3 紹介時の注意点
第4章 指導付きセルフヘルプについて-さらに知っておくべきこと
1 症状モニターをしないほうがよいとき
2 ライフサイクルとセルフヘルプの位置付け
3 海外での試み
第2部 実践編
第5章 初診時の外来でのセルフヘルプの導入
CASE 1 テーマ:家族はあまり心配していない中学生に対する治療の導入
【小児科医×Aさん(15歳女性,中学3年)とその母親】
CASE 2 テーマ:家族の不安が強い高校生に対する治療
【内科医×Bさん(17歳女性,高校2年)とその母親】
CASE 3 テーマ:ライフイベントを動機付けに生かす(栄養指導の併用)
【精神科医と栄養士×Cさん(30歳女性,会社員)】
CASE 4 テーマ:症状悪化への気付き(過活動の理解)
【精神科医×Dさん(24歳女性,元会社員で現在資格試験浪人中)】
第6章 さまざまな場面でのセルフヘルプの導入
CASE 5 テーマ:健診結果から受診につなぐ
【養護教諭×Eさん(14歳女性,中学2年)】
CASE 6 テーマ:学生相談の途中で明らかになった過食嘔吐の問題
【臨床心理士×Fさん(19歳女性,大学1年)】
CASE 7 テーマ:子育て相談の中で明らかになった摂食障害とうつ状態
【保健師×Gさん(28歳女性,育児中の母親)】
CASE 8 テーマ:病棟での看護師の対応
【看護師×Hさん(20歳女性,入院中)】
第7章 過食症への対応
CASE 9(Part 1) テーマ:食生活の安定化と症状モニタリングの導入
【精神科医×Iさん(20代女性,会社員)】
CASE 9(Part 2) テーマ:背景の分析とより安定した症状コントロール
【精神科医×Iさん(20代女性,会社員)】
第3部 資料編
資料1 週2回の体重と脈の記録
資料2 家族の責任と本人の責任について話し合うためのチャート
資料3 食生活を変えたいかについての質問
資料4 変えたほうがよい理由と変えないほうがよい理由
資料5 食事の時間,場所,内容
資料6 安心食材リスト
資料7 経過表
資料8 成長曲線の記録用紙(女子用)/成長曲線の記録用紙(男子用)
資料9 1日の生活リズム記録表
資料10 症状がよくなったり悪くなったりするきっかけ
資料11 治療者が渡した記録表
資料13 今週のまとめシート
資料12-1 過食症の記録用紙(基本バージョン)
資料12-2 過食症の記録用紙(過食の背景を含めたバージョン)
資料12-3 過食症の記録用紙(症状出現時の状況を詳しく記入するバージョン)
参考文献
索引
第1章 摂食障害の特徴と治療-治療の難しさを乗り越えるために
1 はじめに
2 症状の理解-セルフヘルプに導入しやすい症状
3 セルフヘルプ,指導付きセルフヘルプ
第2章 さまざまな治療法とセルフヘルプの生かし方
1 従来の治療法の再考
2 指導付きセルフヘルプに活用できる考え方と技法
3 セルフヘルプを援助する治療者像
4 実際の会話にみる治療関係
5 医学的処置が必要な状況
第3章 治療の流れとセルフヘルプの生かし方
1 多職種連携と本人の治療動機
2 組織を超えた初診時の連携
3 紹介時の注意点
第4章 指導付きセルフヘルプについて-さらに知っておくべきこと
1 症状モニターをしないほうがよいとき
2 ライフサイクルとセルフヘルプの位置付け
3 海外での試み
第2部 実践編
第5章 初診時の外来でのセルフヘルプの導入
CASE 1 テーマ:家族はあまり心配していない中学生に対する治療の導入
【小児科医×Aさん(15歳女性,中学3年)とその母親】
CASE 2 テーマ:家族の不安が強い高校生に対する治療
【内科医×Bさん(17歳女性,高校2年)とその母親】
CASE 3 テーマ:ライフイベントを動機付けに生かす(栄養指導の併用)
【精神科医と栄養士×Cさん(30歳女性,会社員)】
CASE 4 テーマ:症状悪化への気付き(過活動の理解)
【精神科医×Dさん(24歳女性,元会社員で現在資格試験浪人中)】
第6章 さまざまな場面でのセルフヘルプの導入
CASE 5 テーマ:健診結果から受診につなぐ
【養護教諭×Eさん(14歳女性,中学2年)】
CASE 6 テーマ:学生相談の途中で明らかになった過食嘔吐の問題
【臨床心理士×Fさん(19歳女性,大学1年)】
CASE 7 テーマ:子育て相談の中で明らかになった摂食障害とうつ状態
【保健師×Gさん(28歳女性,育児中の母親)】
CASE 8 テーマ:病棟での看護師の対応
【看護師×Hさん(20歳女性,入院中)】
第7章 過食症への対応
CASE 9(Part 1) テーマ:食生活の安定化と症状モニタリングの導入
【精神科医×Iさん(20代女性,会社員)】
CASE 9(Part 2) テーマ:背景の分析とより安定した症状コントロール
【精神科医×Iさん(20代女性,会社員)】
第3部 資料編
資料1 週2回の体重と脈の記録
資料2 家族の責任と本人の責任について話し合うためのチャート
資料3 食生活を変えたいかについての質問
資料4 変えたほうがよい理由と変えないほうがよい理由
資料5 食事の時間,場所,内容
資料6 安心食材リスト
資料7 経過表
資料8 成長曲線の記録用紙(女子用)/成長曲線の記録用紙(男子用)
資料9 1日の生活リズム記録表
資料10 症状がよくなったり悪くなったりするきっかけ
資料11 治療者が渡した記録表
資料13 今週のまとめシート
資料12-1 過食症の記録用紙(基本バージョン)
資料12-2 過食症の記録用紙(過食の背景を含めたバージョン)
資料12-3 過食症の記録用紙(症状出現時の状況を詳しく記入するバージョン)
参考文献
索引
書評
開く
看護教育は「学生の力を生かす教育をしているか?」という問い─指導ではない援助を考える (雑誌『看護教育』より)
書評者: 米山 奈奈子 (秋田大学大学院医学系研究科教授)
本書は,摂食障害の治療において,『本人のセルフヘルプを援助する』姿勢が非常に重要なのではないかという著者の姿勢に基づいて書かれている。著者がイギリスで研究していた時期に,医療システムや組織の違いを超えて,多くの学びの基本にあったのが,こうした治療態度であったという。本来どんな患者であれ,もともとその人が持っている力を最大限に活用できるような支援が重要であるはずなのだが,そうしたことに着目できなくなっている日本の医療制度や現場の問題も大きいのかもしれない。また,摂食障害は,看護学生にも決して珍しくない疾患である。単なるダイエット,失恋やいじめ等がきっかけであることも多いが,背景には複雑な家族問題やトラウマが隠れている場合もある。加えて,学生自身が自ら不調を訴えて相談に来る場合はまれで,どちらかというと周囲に気づかれて問題が浮上する場合が多いのではないか。治療に繋がっても,症状が遷延化する場合もあり,危機的身体症状やうつ・自傷行為など,さまざまな合併症を呈する場合は特に,この疾患そのものをどのように理解し,どのような関わりが,摂食障害を抱える学生への支援になるのかと思い悩む教員も多いのではないだろうか。
そのためにも,教員が学生のセルフヘルプを援助する姿勢で関わることが,学生の成長や治療,疾患からの回復を援助することにつながるのではないかと私は考えるのだが,実際は,複数の教員でこうした情報を共有し,学生の支援体制を整えていくことは思いのほか容易なことではないかもしれない。しかし,こうした姿勢は,看護教育現場にも大変重要で,こうした教員のかかわりが学生に対して,患者への看護ケアのモデルにもなりうるのではないかと私は考えている。本書の実践編では,臨場感あふれる架空の症例が豊富に書かれている。最初からこんなに言語化できる患者はいない,と思われる方もいるだろう。しかし,援助者が自分の考えや見立てを誠実に伝え,かつ患者を尊重する姿勢を示し続けることは,患者の力を引き出す。それが,患者が新たなステップを踏み出すための,背中を押す大きな力になるということが,私の経験からも確かだと感じられる。
私は地域で摂食障害のサポートグループを主宰して6年になるが,限られた医療機関しかない地方では,当事者が孤立しないよう,限られたつながりを繋ぎとめることが非常に重要となる。摂食障害患者は,困難な状況を「摂食障害」という症状を抱えることによって,生き抜いてきた“サヴァイヴァー”であるともいえるのだ。本書は,患者のセルフヘルプを援助する目的で医療関係者向けに書かれているが,患者に限らず教育や援助を仕事とする専門家にも,患者や当事者と関わる姿勢について多くの示唆を与えてくれる本でもある。
(『看護教育』2010年12月号掲載)
臨床の困惑を見事に解消してくれる至極の一冊
書評者: 武田 綾 (NPO法人のびの会・心理療法士)
摂食障害の治療は,実にさまざまな困難を伴う。その結果,専門医療機関に患者が集中することになるのだが,限られた時間とエネルギーとマンパワーで対応していくために,本書の副題の通り,患者自身にも回復への取り組みの意欲を持たせる「患者の力を生かすアプローチ」がカギを握ると痛感している。しかしそれほど重要であるにもかかわらず,どのタイミングで,どのような言葉をきっかけに,どのような形で介入すればよいのかを示す実用書には,なかなか出合えなかった。加えて摂食障害の病態は従来よりも多彩化し複雑化し,専門医以外の者が本症の患者と遭遇する機会をもたらしたが,専門医以外の医療職や健康へのサポートをしている人たちは,ガイドのない中で個人プレーをするしかなかった。本書を一言で表現するとすれば,「その困惑を見事に解消してくれる至極の一冊」といえる。
第1部は理論編として,診断基準が詳しく説明されている。「診断基準以外の特徴」として,診断基準には該当しないが明らかに摂食障害の症状を呈していると思われる特徴的な病的行動や心理を拾い出すための着眼点も示されている。
本書の中心となる第2部は実践編で,会話の中に細かな心の機微まで感じられるような臨場感あふれる症例が提示されている。患者である彼女らは一見適応的な振る舞いを見せるが,常に他人の動向をうかがうあまり,実際の食事量や体重に関して大きく異なる内容を語ったり,些細な話題で傷ついたりする傾向がある。したがって,本書の中で具体的な会話のやり取りがマニュアルとして示されていることは非常に心強い。
摂食障害が「普通の病気」(本書「序」より)となった以上,医療者以外の人がどのようなタイプの患者にも,どのような場面でも遭遇することを想定してのことであろう。患者の年齢も,面接の担当者も,患者が置かれている状況も実にバラエティに富み,それらに対するまさに実地応用のガイドラインとなっている。特に,これまではあまり対象とされなかった地域保健所での健診場面や学校での学生相談などの場面が多く取り上げられ,近年,産後メンタルヘルスケアを研究テーマに活動のエリアを地域に広げ,実際に対応してきた著者ならではの経験が生かされている。
最後の第3部にはさまざまな資料が準備されており,第2部「実践編」で書かれた内容を自らの臨床に取り入れようとする読者にとっては,迅速かつ手軽なアイテムとして重宝するだろう。
著者はこれまでの著作の中で,患者自身が日頃から取り組めるような提案を行ってきた。本書はその患者のセルフヘルプを促す役割を担う,われわれのための実践書である。
患者の力を引き出して治療を進めるための道標
書評者: 高木 洲一郎 (自由が丘高木クリニック院長)
摂食障害の増加に対して,治療する側の対応は非常に遅れている。摂食障害は,外科治療のように医師が患部を取り除く疾患と異なり,治すのはあくまで本人であり,家族や治療者はその支援にとどまる。また著者が述べているように,摂食障害は休養と薬物療法で回復が期待できるタイプの疾患とは様相が異なり,単に「見守る」以上の対応を必要とする。本書は患者自身がそれを積極的に,具体的に進めることを助けるため,患者本人にかかわる職種への指針を具体的に示している。
摂食障害関連の書物も増えているが,本書の内容はユニークである。本書の題名にある「セルフへルプ援助」とは,患者の自己流ではないセルフヘルプを指導することにより,患者の力を引き出して治療を進めていくことをめざしている。摂食障害の専門家でなくても,「基本的なトレーニングを積んで,患者が置かれた状況に対する洞察力や患者との信頼関係を駆使すれば,援助可能な対象は多い」との考えのもとに,そのための道標になることを目的として本書は著された。
摂食障害には診断基準に示されている核となる症状だけでなく,いくつもの際立った特徴があり,治療にあたってはまず本症に対する幅広い理解が必要となる。第1部の「理論編」では症状についての詳しい説明がなされる。
ついで本書のおよそ2/3を占める第2部「実践編」では9例の面接場面が紹介される。事例ではさまざまな状況や場面が設定されており,面接者はそれぞれ小児科医,内科医,精神科医,栄養士,養護教諭,臨床心理士,保健師,看護師となっており,連携の例も示されている。本書の読者対象は主にこれらの職種の人たちで,セルフヘルプといっても患者や家族に薦めるための書物ではない。
巻末の第3部「資料編―患者の力を生かす『13』のツール」には,セルフへルプで使う記録用紙の書式(雛形)が示されており,これらは各人の状況により工夫して用いることができる。
臨床はすべからく応用問題である。セルフヘルプを実践するときは,読者は患者と対話し,患者からもアイデアを引き出しながら生活に根差した治療計画を練っていく。このセルフヘルプを援助する方法を学ぶことにより,読者は治療に関する多くのヒントを必ずや得られるはずである。読者は本書の読前と読後で,治療に対する意識が確実に変化しているであろう。
摂食障害の治療法が着実に進んでいることを実感させられる。
摂食障害のプライマリケアにかかわるすべての方への指南書
書評者: 鈴木(堀田) 眞理 (政策研究大学院大教授・保健管理センター)
摂食障害はcommon diseaseになったが,治療がやさしいという治療者はいない。神経性食欲不振症は「体重を増やしたくない」,神経性大食症は「止めたいけれど過食したい」患者である。つまり,摂食障害の治療の困難さは,「治したいけれど,治したくない」患者を対象にしているからである。
セルフヘルプとは,本人が主体的に治療に参加して自分をケアすることである。本書は,根源的な治療関係の困難さを持つ摂食障害患者にもセルフヘルプする気持ちを育てることができる,治療者は技術提供をして患者の力を最大限活用するというガイド付きセルフヘルプの診療スタイルなら専門医に行かずともプライマリケアである程度の有効性を得られる,という著者の英国での臨床経験に基づいて書かれた実用書である。身体疾患では基本的な診療スタイルであるが,最もなじまないと考えがちな摂食障害での実用を指南している点で,本書は画期的である。
その手法は,セルフヘルプしやすい症状に着目,リスト作りや症状の定量化という認知行動療法的なアプローチで治療の動機付け,患者からもアイデアを引き出すという共同作業,生活に根ざした,つまり,達成可能な治療計画,患者の感想や反論を聞くという患者の信頼感を得るスタンス,宿題をさせること,患者に治療が進んでいる感覚を与えるなどで,細やかな配慮を随所に交えてやさしく解説されている。読後すぐに実践できる気持ちになる。
本書の魅力の一つは,臨場感溢れる9例の面談例である。例えば,養護教諭の指示で小児科クリニックを受診した中学生という設定で,受診動機を確認させる導入から,症状や検査結果を治療意欲につなぎ,次の受診までの宿題を了解してもらうというプロセスを,一般医が日常臨床でできるような展開で書かれている。同席した母親への対応も忘れない。
著者は学校や保健所での健康相談の経験が多く,他職種連携や組織を越えた地域での連携の有用性を訴えるオピニオンリーダーでもある。医師だけでなく,栄養士,養護教諭,大学学生相談室の相談員,看護師など多職種との面談光景も掲載されており,日常,摂食障害にかかわる人なら誰にも役立つ。症状や言葉をなるべく具体化,数量化,可視化してアセスメントや共同作業フォーミュレーションに役立てるために,付録の表やグラフは使いやすい。セルフヘルプが不適切な事態も詳しく解説され,経験の豊富さが光る。
この診療スタイルは,治療者を気負いから生じる疲弊感や焦燥感から救うだろう。患者は治療者との共同戦線の中で,自分と自分の意見が尊重されることを知り,相談する技術を学び,試行錯誤を受容し,達成感を味わう可能性がある。診療が終わっても患者の生きるためのスキルとして残るだろう。それこそが摂食障害患者が回復するために必要なコーピングスキルである。良書である。
書評者: 米山 奈奈子 (秋田大学大学院医学系研究科教授)
本書は,摂食障害の治療において,『本人のセルフヘルプを援助する』姿勢が非常に重要なのではないかという著者の姿勢に基づいて書かれている。著者がイギリスで研究していた時期に,医療システムや組織の違いを超えて,多くの学びの基本にあったのが,こうした治療態度であったという。本来どんな患者であれ,もともとその人が持っている力を最大限に活用できるような支援が重要であるはずなのだが,そうしたことに着目できなくなっている日本の医療制度や現場の問題も大きいのかもしれない。また,摂食障害は,看護学生にも決して珍しくない疾患である。単なるダイエット,失恋やいじめ等がきっかけであることも多いが,背景には複雑な家族問題やトラウマが隠れている場合もある。加えて,学生自身が自ら不調を訴えて相談に来る場合はまれで,どちらかというと周囲に気づかれて問題が浮上する場合が多いのではないか。治療に繋がっても,症状が遷延化する場合もあり,危機的身体症状やうつ・自傷行為など,さまざまな合併症を呈する場合は特に,この疾患そのものをどのように理解し,どのような関わりが,摂食障害を抱える学生への支援になるのかと思い悩む教員も多いのではないだろうか。
そのためにも,教員が学生のセルフヘルプを援助する姿勢で関わることが,学生の成長や治療,疾患からの回復を援助することにつながるのではないかと私は考えるのだが,実際は,複数の教員でこうした情報を共有し,学生の支援体制を整えていくことは思いのほか容易なことではないかもしれない。しかし,こうした姿勢は,看護教育現場にも大変重要で,こうした教員のかかわりが学生に対して,患者への看護ケアのモデルにもなりうるのではないかと私は考えている。本書の実践編では,臨場感あふれる架空の症例が豊富に書かれている。最初からこんなに言語化できる患者はいない,と思われる方もいるだろう。しかし,援助者が自分の考えや見立てを誠実に伝え,かつ患者を尊重する姿勢を示し続けることは,患者の力を引き出す。それが,患者が新たなステップを踏み出すための,背中を押す大きな力になるということが,私の経験からも確かだと感じられる。
私は地域で摂食障害のサポートグループを主宰して6年になるが,限られた医療機関しかない地方では,当事者が孤立しないよう,限られたつながりを繋ぎとめることが非常に重要となる。摂食障害患者は,困難な状況を「摂食障害」という症状を抱えることによって,生き抜いてきた“サヴァイヴァー”であるともいえるのだ。本書は,患者のセルフヘルプを援助する目的で医療関係者向けに書かれているが,患者に限らず教育や援助を仕事とする専門家にも,患者や当事者と関わる姿勢について多くの示唆を与えてくれる本でもある。
(『看護教育』2010年12月号掲載)
臨床の困惑を見事に解消してくれる至極の一冊
書評者: 武田 綾 (NPO法人のびの会・心理療法士)
摂食障害の治療は,実にさまざまな困難を伴う。その結果,専門医療機関に患者が集中することになるのだが,限られた時間とエネルギーとマンパワーで対応していくために,本書の副題の通り,患者自身にも回復への取り組みの意欲を持たせる「患者の力を生かすアプローチ」がカギを握ると痛感している。しかしそれほど重要であるにもかかわらず,どのタイミングで,どのような言葉をきっかけに,どのような形で介入すればよいのかを示す実用書には,なかなか出合えなかった。加えて摂食障害の病態は従来よりも多彩化し複雑化し,専門医以外の者が本症の患者と遭遇する機会をもたらしたが,専門医以外の医療職や健康へのサポートをしている人たちは,ガイドのない中で個人プレーをするしかなかった。本書を一言で表現するとすれば,「その困惑を見事に解消してくれる至極の一冊」といえる。
第1部は理論編として,診断基準が詳しく説明されている。「診断基準以外の特徴」として,診断基準には該当しないが明らかに摂食障害の症状を呈していると思われる特徴的な病的行動や心理を拾い出すための着眼点も示されている。
本書の中心となる第2部は実践編で,会話の中に細かな心の機微まで感じられるような臨場感あふれる症例が提示されている。患者である彼女らは一見適応的な振る舞いを見せるが,常に他人の動向をうかがうあまり,実際の食事量や体重に関して大きく異なる内容を語ったり,些細な話題で傷ついたりする傾向がある。したがって,本書の中で具体的な会話のやり取りがマニュアルとして示されていることは非常に心強い。
摂食障害が「普通の病気」(本書「序」より)となった以上,医療者以外の人がどのようなタイプの患者にも,どのような場面でも遭遇することを想定してのことであろう。患者の年齢も,面接の担当者も,患者が置かれている状況も実にバラエティに富み,それらに対するまさに実地応用のガイドラインとなっている。特に,これまではあまり対象とされなかった地域保健所での健診場面や学校での学生相談などの場面が多く取り上げられ,近年,産後メンタルヘルスケアを研究テーマに活動のエリアを地域に広げ,実際に対応してきた著者ならではの経験が生かされている。
最後の第3部にはさまざまな資料が準備されており,第2部「実践編」で書かれた内容を自らの臨床に取り入れようとする読者にとっては,迅速かつ手軽なアイテムとして重宝するだろう。
著者はこれまでの著作の中で,患者自身が日頃から取り組めるような提案を行ってきた。本書はその患者のセルフヘルプを促す役割を担う,われわれのための実践書である。
患者の力を引き出して治療を進めるための道標
書評者: 高木 洲一郎 (自由が丘高木クリニック院長)
摂食障害の増加に対して,治療する側の対応は非常に遅れている。摂食障害は,外科治療のように医師が患部を取り除く疾患と異なり,治すのはあくまで本人であり,家族や治療者はその支援にとどまる。また著者が述べているように,摂食障害は休養と薬物療法で回復が期待できるタイプの疾患とは様相が異なり,単に「見守る」以上の対応を必要とする。本書は患者自身がそれを積極的に,具体的に進めることを助けるため,患者本人にかかわる職種への指針を具体的に示している。
摂食障害関連の書物も増えているが,本書の内容はユニークである。本書の題名にある「セルフへルプ援助」とは,患者の自己流ではないセルフヘルプを指導することにより,患者の力を引き出して治療を進めていくことをめざしている。摂食障害の専門家でなくても,「基本的なトレーニングを積んで,患者が置かれた状況に対する洞察力や患者との信頼関係を駆使すれば,援助可能な対象は多い」との考えのもとに,そのための道標になることを目的として本書は著された。
摂食障害には診断基準に示されている核となる症状だけでなく,いくつもの際立った特徴があり,治療にあたってはまず本症に対する幅広い理解が必要となる。第1部の「理論編」では症状についての詳しい説明がなされる。
ついで本書のおよそ2/3を占める第2部「実践編」では9例の面接場面が紹介される。事例ではさまざまな状況や場面が設定されており,面接者はそれぞれ小児科医,内科医,精神科医,栄養士,養護教諭,臨床心理士,保健師,看護師となっており,連携の例も示されている。本書の読者対象は主にこれらの職種の人たちで,セルフヘルプといっても患者や家族に薦めるための書物ではない。
巻末の第3部「資料編―患者の力を生かす『13』のツール」には,セルフへルプで使う記録用紙の書式(雛形)が示されており,これらは各人の状況により工夫して用いることができる。
臨床はすべからく応用問題である。セルフヘルプを実践するときは,読者は患者と対話し,患者からもアイデアを引き出しながら生活に根差した治療計画を練っていく。このセルフヘルプを援助する方法を学ぶことにより,読者は治療に関する多くのヒントを必ずや得られるはずである。読者は本書の読前と読後で,治療に対する意識が確実に変化しているであろう。
摂食障害の治療法が着実に進んでいることを実感させられる。
摂食障害のプライマリケアにかかわるすべての方への指南書
書評者: 鈴木(堀田) 眞理 (政策研究大学院大教授・保健管理センター)
摂食障害はcommon diseaseになったが,治療がやさしいという治療者はいない。神経性食欲不振症は「体重を増やしたくない」,神経性大食症は「止めたいけれど過食したい」患者である。つまり,摂食障害の治療の困難さは,「治したいけれど,治したくない」患者を対象にしているからである。
セルフヘルプとは,本人が主体的に治療に参加して自分をケアすることである。本書は,根源的な治療関係の困難さを持つ摂食障害患者にもセルフヘルプする気持ちを育てることができる,治療者は技術提供をして患者の力を最大限活用するというガイド付きセルフヘルプの診療スタイルなら専門医に行かずともプライマリケアである程度の有効性を得られる,という著者の英国での臨床経験に基づいて書かれた実用書である。身体疾患では基本的な診療スタイルであるが,最もなじまないと考えがちな摂食障害での実用を指南している点で,本書は画期的である。
その手法は,セルフヘルプしやすい症状に着目,リスト作りや症状の定量化という認知行動療法的なアプローチで治療の動機付け,患者からもアイデアを引き出すという共同作業,生活に根ざした,つまり,達成可能な治療計画,患者の感想や反論を聞くという患者の信頼感を得るスタンス,宿題をさせること,患者に治療が進んでいる感覚を与えるなどで,細やかな配慮を随所に交えてやさしく解説されている。読後すぐに実践できる気持ちになる。
本書の魅力の一つは,臨場感溢れる9例の面談例である。例えば,養護教諭の指示で小児科クリニックを受診した中学生という設定で,受診動機を確認させる導入から,症状や検査結果を治療意欲につなぎ,次の受診までの宿題を了解してもらうというプロセスを,一般医が日常臨床でできるような展開で書かれている。同席した母親への対応も忘れない。
著者は学校や保健所での健康相談の経験が多く,他職種連携や組織を越えた地域での連携の有用性を訴えるオピニオンリーダーでもある。医師だけでなく,栄養士,養護教諭,大学学生相談室の相談員,看護師など多職種との面談光景も掲載されており,日常,摂食障害にかかわる人なら誰にも役立つ。症状や言葉をなるべく具体化,数量化,可視化してアセスメントや共同作業フォーミュレーションに役立てるために,付録の表やグラフは使いやすい。セルフヘルプが不適切な事態も詳しく解説され,経験の豊富さが光る。
この診療スタイルは,治療者を気負いから生じる疲弊感や焦燥感から救うだろう。患者は治療者との共同戦線の中で,自分と自分の意見が尊重されることを知り,相談する技術を学び,試行錯誤を受容し,達成感を味わう可能性がある。診療が終わっても患者の生きるためのスキルとして残るだろう。それこそが摂食障害患者が回復するために必要なコーピングスキルである。良書である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。