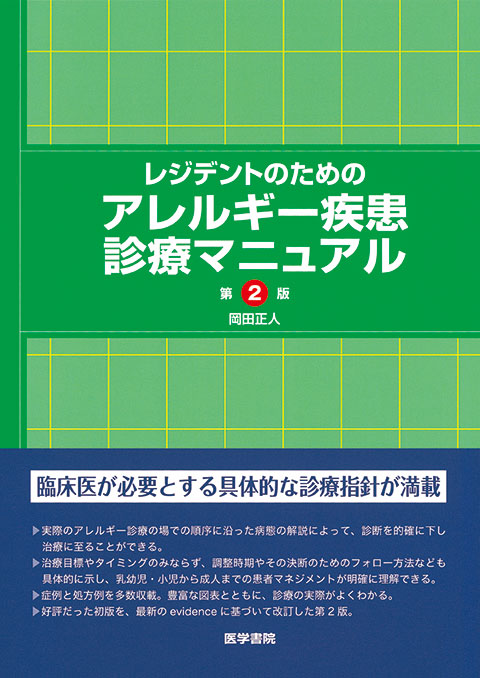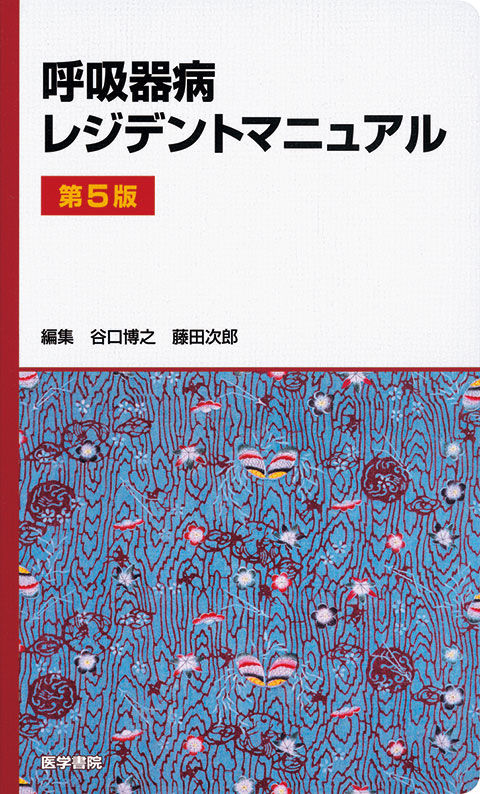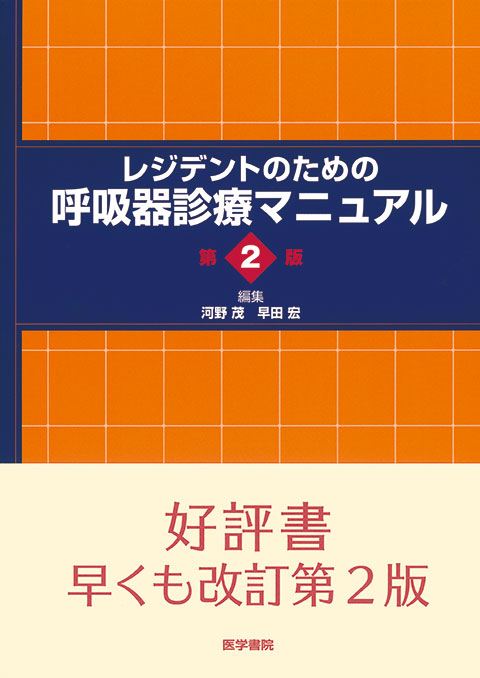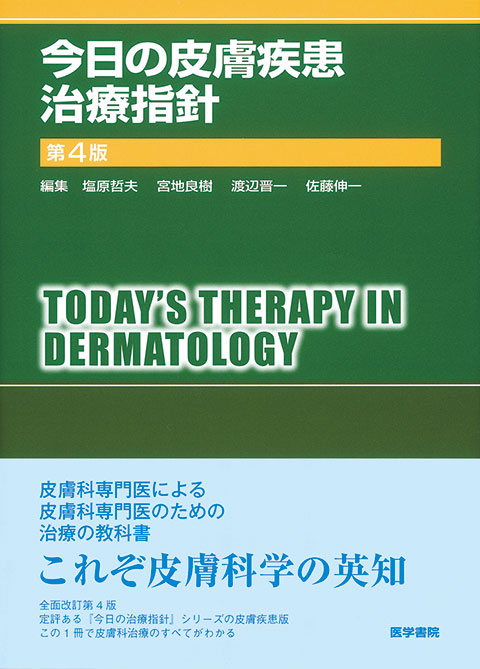レジデントのためのアレルギー疾患診療マニュアル 第2版
アレルギー診療の場における順序に沿った病態の解説が的確な診断・治療を導く
もっと見る
プライマリケア医にとって、アレルギー疾患の診療の重要性は近年とみに増している。本書は、最新のevidenceに基づき、「全身をよく診察する」というこの領域での診療の大原則に則り、実際の診療の場での順序に沿って病態を解説することで診断を的確に下すことができる。また、治療目標とタイミング、調整時期やその決断のためのフォロー方法なども具体的に示した大好評本の待望の改訂版。
| シリーズ | レジデントマニュアル |
|---|---|
| 著 | 岡田 正人 |
| 発行 | 2014年10月判型:A5頁:440 |
| ISBN | 978-4-260-02034-3 |
| 定価 | 5,280円 (本体4,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第2版の序
平成元年に医学部を卒業し,米国を中心に8年間,その後フランスで8年間,そして初版から今回の改訂までの約8年間を聖路加国際病院でアレルギー膠原病科医として診療にあたらせていただいています。初版はフランスで診療していたときに書いたものでしたが,今回は8年間の日本での経験をもとに,最新の知見も含めて日本での診療により即したものになるようにと考えて書き加えています。
まずは第1章を通読していただくことで,アレルギー全般に共通する考え方や診断と治療の原則を理解していただければと思います。その後の各論は,診断から患者さんへの説明,治療法の具体例など実際の診療につながる内容になっています。また,日本でのアレルギー診療における重要性の高い分野である薬物アレルギーの章は,特に大幅に内容を増やして改訂しています。実臨床で役に立てられるように,数多い薬物アレルギーそれぞれの臨床的特徴と原因薬物,そして治療に関して具体的に記載しました。また,重症薬疹に関しては,早期発見のための皮疹以外の所見の重要性,日常診療で重症薬疹を引き起こさないための処方上の注意点なども参考にしていただければと思います。抗菌薬,抗腫瘍薬などはアレルギーの既往があっても治療上必要になってしまうこともあるので,減感作治療プロトコールなどもより多くの薬剤に関して具体的に記載するようにしました。
全体的な内容としては,入院患者さんを中心に診療している若い先生に特に重要なアナフィラキシー,薬物アレルギーなどから,外来診療がメインの先生方に関連の深い,じん麻疹や接触性皮膚炎などのcommon diseasesまで,アレルギー疾患全般をカバーしています。アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患においては,ほんの少しの知識の向上が治療効果の大きな改善につながることが多いのが実情で,アレルギーを系統的に修得する機会の少なかった先生方のお役に立てればと思っています。
現在は基礎免疫学の進歩が,実際にアレルギー診療に応用される時代になっています。それぞれの薬剤の臨床的特徴のみでなく,免疫学的な機序を理解することは,薬を効率的かつ効果的に処方することだけでなく,実際の患者さんへの説明にも非常に役立ちます。とはいえ,基礎免疫学の論文や教科書を読む時間を確保することはなかなか難しいと思いますので,各章の間にコラムとして免疫学的な内容を単純化した図や実臨床における例を入れながら記載してあります。まずは第1章を読んでいただき,その後に各論のはじめにあるポイントと気になるところを眺めていただいてからこのコラムを1つずつでも読んでいただくと,より理解しやすいのではないかと思います。
私が米国でアレルギーの専門教育を受けてから約20年が経ちました。初版は一度目の更新試験を2005年に受けてから書いたものでしたが,今回の第2版は2015年の2度目の専門医更新試験受験資格を得るための何十時間にも及ぶ課題を提出したところで書かせていただきました。米国で学んだ臨床免疫学,フランスで何千人という患者さんたちから学ばせていただいたアレルギー診療の実際,そして日本での診療経験のすべてを記載したこの本が少しでも多くの先生とその患者さんたちのお役に立てばと願っています。
2014年9月
岡田正人
平成元年に医学部を卒業し,米国を中心に8年間,その後フランスで8年間,そして初版から今回の改訂までの約8年間を聖路加国際病院でアレルギー膠原病科医として診療にあたらせていただいています。初版はフランスで診療していたときに書いたものでしたが,今回は8年間の日本での経験をもとに,最新の知見も含めて日本での診療により即したものになるようにと考えて書き加えています。
まずは第1章を通読していただくことで,アレルギー全般に共通する考え方や診断と治療の原則を理解していただければと思います。その後の各論は,診断から患者さんへの説明,治療法の具体例など実際の診療につながる内容になっています。また,日本でのアレルギー診療における重要性の高い分野である薬物アレルギーの章は,特に大幅に内容を増やして改訂しています。実臨床で役に立てられるように,数多い薬物アレルギーそれぞれの臨床的特徴と原因薬物,そして治療に関して具体的に記載しました。また,重症薬疹に関しては,早期発見のための皮疹以外の所見の重要性,日常診療で重症薬疹を引き起こさないための処方上の注意点なども参考にしていただければと思います。抗菌薬,抗腫瘍薬などはアレルギーの既往があっても治療上必要になってしまうこともあるので,減感作治療プロトコールなどもより多くの薬剤に関して具体的に記載するようにしました。
全体的な内容としては,入院患者さんを中心に診療している若い先生に特に重要なアナフィラキシー,薬物アレルギーなどから,外来診療がメインの先生方に関連の深い,じん麻疹や接触性皮膚炎などのcommon diseasesまで,アレルギー疾患全般をカバーしています。アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患においては,ほんの少しの知識の向上が治療効果の大きな改善につながることが多いのが実情で,アレルギーを系統的に修得する機会の少なかった先生方のお役に立てればと思っています。
現在は基礎免疫学の進歩が,実際にアレルギー診療に応用される時代になっています。それぞれの薬剤の臨床的特徴のみでなく,免疫学的な機序を理解することは,薬を効率的かつ効果的に処方することだけでなく,実際の患者さんへの説明にも非常に役立ちます。とはいえ,基礎免疫学の論文や教科書を読む時間を確保することはなかなか難しいと思いますので,各章の間にコラムとして免疫学的な内容を単純化した図や実臨床における例を入れながら記載してあります。まずは第1章を読んでいただき,その後に各論のはじめにあるポイントと気になるところを眺めていただいてからこのコラムを1つずつでも読んでいただくと,より理解しやすいのではないかと思います。
私が米国でアレルギーの専門教育を受けてから約20年が経ちました。初版は一度目の更新試験を2005年に受けてから書いたものでしたが,今回の第2版は2015年の2度目の専門医更新試験受験資格を得るための何十時間にも及ぶ課題を提出したところで書かせていただきました。米国で学んだ臨床免疫学,フランスで何千人という患者さんたちから学ばせていただいたアレルギー診療の実際,そして日本での診療経験のすべてを記載したこの本が少しでも多くの先生とその患者さんたちのお役に立てばと願っています。
2014年9月
岡田正人
目次
開く
第1章 アレルギー疾患の診方・考え方
第2章 食物アレルギー
1 問診のポイント
2 原因・抗原
3 症状
4 診断
5 治療
1.原因食物の除去
2.薬物治療
6 食物アレルギーと交差反応
7 口腔アレルギー症候群
1.診断
2.治療
3.花粉・食物アレルギー症候群
4.ラテックス果物症候群
8 scombroid poisoning(サバ科の魚によるヒスタミン反応)
▸アニサキスアレルギー
9 食物依存運動誘発性アナフィラキシー
1.症状
2.危険因子
3.原因食物
4.診断
5.治療
6.予防
10 IgEを介さない食物過敏症(細胞性免疫介在)
11 食物アレルギーの自然経過
第3章 アナフィラキシーと虫刺されアレルギー
1 アナフィラキシーとアナフィラクトイド反応
1.原因
2.症状
3.二相性反応
4.臨床検査
5.ハイリスク患者への投与を避けるべき薬物
6.緊急一次処置
7.一次処置後,必要に応じて速やかに行う処置
8.重症例・特殊例に対する処置
2 虫刺されアレルギー
1.診断
2.治療
3.予防
▸エピペン処方の実際
3 全身性毛細血管漏出症候群
第4章 鼻炎
1 疫学
2 診断
1.臨床的診断
2.アレルギー性鼻炎のための検査
3 アレルギー性鼻炎の治療
1.抗原回避
2.薬物治療
▸抗ヒスタミン薬の作用機序と使い方
▸ステロイド筋注
3.小児の鼻炎治療
4.妊娠中の鼻炎治療
4 鼻炎の合併症と後遺症
5 アレルギー性結膜炎の治療
第5章 副鼻腔炎
1 副鼻腔炎の病態生理
2 急性副鼻腔炎
1.症状と診断
2.身体所見
3.起因菌と抗菌薬の選択
3 慢性副鼻腔炎
1.症状と診断
2.誘発因子
3.治療
▸マクロライド長期療法
4 アレルギー性真菌性副鼻腔炎
第6章 喘息
1 予防
2 診断
1.症状・身体所見
2.気道の過敏性
3.胸部X線写真
3 小児の喘鳴
4 治療
1.喘息の長期管理における重症度分類と治療
2.ガイドラインに示された第1選択薬
3.喘息の治療に用いる薬剤(コントローラー)
4.喘息の非薬物療法
5.アレルギー対策
6.減感作免疫療法
5 急性増悪発作
1.管理と重症度分類
2.急性増悪発作に使用される薬剤(リリーバー)
6 遷延性の咳嗽
7 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
8 過敏性肺炎
1.臨床症状
2.診断
3.治療
第7章 薬物アレルギー
1 機序
2 診断
1.臨床的データ
2.原因薬物の絞り込み
3.検査
4.薬物の中止および変更
5.再投与
3 治療
1.減感作療法
4 分類
1.I型:アナフィラキシー,じん麻疹など
2.II型:溶血性貧血,血小板減少症など
3.III型:血清病様反応,腎炎など
4.IV型:接触性皮膚炎など
5.時間経過による分類
5 薬物アレルギーに影響する因子
1.薬物および治療に関連する因子
2.患者に関連する因子
6 多薬剤アレルギー症候群
7 合併疾患
8 併用薬物
9 薬物過敏症の臨床症状
1.アナフィラキシーとアナフィラクトイド反応
10 薬疹
1.播種状紅斑丘疹型薬疹
2.じん麻疹
3.血管浮腫
4.固定薬疹
5.多形滲出性紅斑
6.光線過敏症
7.紫斑様発疹
8.結節性紅斑
9.接触性皮膚炎
10.苔癬型薬疹
11.水疱性薬疹
11 重症薬疹
1.Stevens-Johnson症候群,中毒性表皮壊死剥離症
2.薬剤性過敏症症候群
3.急性汎発性発疹性膿疱症
12 血清病もしくは血清病様反応
1.症状・検査所見
2.原因薬物
3.治療
13 薬剤熱
14 薬剤性ループス
1.症状
2.抗核抗体
3.治療
4.原因薬物
15 薬剤性ANCA関連性血管炎
1.症状,検査,治療
2.原因薬物
16 過敏性血管炎
17 薬物過敏症による内臓障害
1.肺疾患
2.血液学的障害
3.薬剤性免疫学的肝障害
4.腎障害
18 アレルギー反応を起こす特異的な薬物
1.β-ラクタム系抗菌薬
2.サルファ薬
3.アミノ配糖体系抗菌薬
4.グリコペプチド系抗菌薬
5.ニューキノロン系抗菌薬
6.テトラサイクリン系抗菌薬
7.マクロライド系抗菌薬
8.クリンダマイシン
9.メトロニダゾール
10.抗真菌薬
11.抗結核薬
12.アスピリンおよび非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)
13.アセトアミノフェン
14.造影剤
15.全身麻酔薬
16.局所麻酔薬
17.麻薬
18.ACE阻害薬とアンギオテンシンII受容体拮抗薬
19.インスリン
20.ワクチン
21.生物学的製剤
22.化学療法薬
第8章 アトピー性皮膚炎
1 頻度
2 遺伝的素因
3 アトピー素因
4 自然経過
5 臨床症状と診断
6 合併症
1.眼症状
2.手指皮膚炎
3.感染症
7 原因および増悪因子
1.精神的な因子
2.アレルゲンの役割
3.吸入性アレルゲン
4.微生物
5.自己抗原
8 治療
1.増悪因子の同定と除去
2.保湿剤
3.ステロイド外用薬
▸ステロイド外用薬使用の基本
4.タクロリムス軟膏
5.抗ヒスタミン薬・抗炎症外用薬
6.抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬
7.抗菌薬
8.ロイコトリエン受容体拮抗薬
9.probiotics
10.その他の外用薬
9 治療の留意点
第9章 じん麻疹・血管浮腫・接触性皮膚炎
1 じん麻疹
1.急性じん麻疹
2.慢性じん麻疹
2 血管浮腫
1.症状
2.診断
3.血管浮腫の種類
3 接触性皮膚炎
1.発症に影響する素因
2.診断
3.臨床症状
4.接触性皮膚炎の鑑別診断
5.パッチテストと原因物質の特徴
▸パッチテストの実際と注意点
6.治療
索引
第2章 食物アレルギー
1 問診のポイント
2 原因・抗原
3 症状
4 診断
5 治療
1.原因食物の除去
2.薬物治療
6 食物アレルギーと交差反応
7 口腔アレルギー症候群
1.診断
2.治療
3.花粉・食物アレルギー症候群
4.ラテックス果物症候群
8 scombroid poisoning(サバ科の魚によるヒスタミン反応)
▸アニサキスアレルギー
9 食物依存運動誘発性アナフィラキシー
1.症状
2.危険因子
3.原因食物
4.診断
5.治療
6.予防
10 IgEを介さない食物過敏症(細胞性免疫介在)
11 食物アレルギーの自然経過
第3章 アナフィラキシーと虫刺されアレルギー
1 アナフィラキシーとアナフィラクトイド反応
1.原因
2.症状
3.二相性反応
4.臨床検査
5.ハイリスク患者への投与を避けるべき薬物
6.緊急一次処置
7.一次処置後,必要に応じて速やかに行う処置
8.重症例・特殊例に対する処置
2 虫刺されアレルギー
1.診断
2.治療
3.予防
▸エピペン処方の実際
3 全身性毛細血管漏出症候群
第4章 鼻炎
1 疫学
2 診断
1.臨床的診断
2.アレルギー性鼻炎のための検査
3 アレルギー性鼻炎の治療
1.抗原回避
2.薬物治療
▸抗ヒスタミン薬の作用機序と使い方
▸ステロイド筋注
3.小児の鼻炎治療
4.妊娠中の鼻炎治療
4 鼻炎の合併症と後遺症
5 アレルギー性結膜炎の治療
第5章 副鼻腔炎
1 副鼻腔炎の病態生理
2 急性副鼻腔炎
1.症状と診断
2.身体所見
3.起因菌と抗菌薬の選択
3 慢性副鼻腔炎
1.症状と診断
2.誘発因子
3.治療
▸マクロライド長期療法
4 アレルギー性真菌性副鼻腔炎
第6章 喘息
1 予防
2 診断
1.症状・身体所見
2.気道の過敏性
3.胸部X線写真
3 小児の喘鳴
4 治療
1.喘息の長期管理における重症度分類と治療
2.ガイドラインに示された第1選択薬
3.喘息の治療に用いる薬剤(コントローラー)
4.喘息の非薬物療法
5.アレルギー対策
6.減感作免疫療法
5 急性増悪発作
1.管理と重症度分類
2.急性増悪発作に使用される薬剤(リリーバー)
6 遷延性の咳嗽
7 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症
8 過敏性肺炎
1.臨床症状
2.診断
3.治療
第7章 薬物アレルギー
1 機序
2 診断
1.臨床的データ
2.原因薬物の絞り込み
3.検査
4.薬物の中止および変更
5.再投与
3 治療
1.減感作療法
4 分類
1.I型:アナフィラキシー,じん麻疹など
2.II型:溶血性貧血,血小板減少症など
3.III型:血清病様反応,腎炎など
4.IV型:接触性皮膚炎など
5.時間経過による分類
5 薬物アレルギーに影響する因子
1.薬物および治療に関連する因子
2.患者に関連する因子
6 多薬剤アレルギー症候群
7 合併疾患
8 併用薬物
9 薬物過敏症の臨床症状
1.アナフィラキシーとアナフィラクトイド反応
10 薬疹
1.播種状紅斑丘疹型薬疹
2.じん麻疹
3.血管浮腫
4.固定薬疹
5.多形滲出性紅斑
6.光線過敏症
7.紫斑様発疹
8.結節性紅斑
9.接触性皮膚炎
10.苔癬型薬疹
11.水疱性薬疹
11 重症薬疹
1.Stevens-Johnson症候群,中毒性表皮壊死剥離症
2.薬剤性過敏症症候群
3.急性汎発性発疹性膿疱症
12 血清病もしくは血清病様反応
1.症状・検査所見
2.原因薬物
3.治療
13 薬剤熱
14 薬剤性ループス
1.症状
2.抗核抗体
3.治療
4.原因薬物
15 薬剤性ANCA関連性血管炎
1.症状,検査,治療
2.原因薬物
16 過敏性血管炎
17 薬物過敏症による内臓障害
1.肺疾患
2.血液学的障害
3.薬剤性免疫学的肝障害
4.腎障害
18 アレルギー反応を起こす特異的な薬物
1.β-ラクタム系抗菌薬
2.サルファ薬
3.アミノ配糖体系抗菌薬
4.グリコペプチド系抗菌薬
5.ニューキノロン系抗菌薬
6.テトラサイクリン系抗菌薬
7.マクロライド系抗菌薬
8.クリンダマイシン
9.メトロニダゾール
10.抗真菌薬
11.抗結核薬
12.アスピリンおよび非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)
13.アセトアミノフェン
14.造影剤
15.全身麻酔薬
16.局所麻酔薬
17.麻薬
18.ACE阻害薬とアンギオテンシンII受容体拮抗薬
19.インスリン
20.ワクチン
21.生物学的製剤
22.化学療法薬
第8章 アトピー性皮膚炎
1 頻度
2 遺伝的素因
3 アトピー素因
4 自然経過
5 臨床症状と診断
6 合併症
1.眼症状
2.手指皮膚炎
3.感染症
7 原因および増悪因子
1.精神的な因子
2.アレルゲンの役割
3.吸入性アレルゲン
4.微生物
5.自己抗原
8 治療
1.増悪因子の同定と除去
2.保湿剤
3.ステロイド外用薬
▸ステロイド外用薬使用の基本
4.タクロリムス軟膏
5.抗ヒスタミン薬・抗炎症外用薬
6.抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬
7.抗菌薬
8.ロイコトリエン受容体拮抗薬
9.probiotics
10.その他の外用薬
9 治療の留意点
第9章 じん麻疹・血管浮腫・接触性皮膚炎
1 じん麻疹
1.急性じん麻疹
2.慢性じん麻疹
2 血管浮腫
1.症状
2.診断
3.血管浮腫の種類
3 接触性皮膚炎
1.発症に影響する素因
2.診断
3.臨床症状
4.接触性皮膚炎の鑑別診断
5.パッチテストと原因物質の特徴
▸パッチテストの実際と注意点
6.治療
索引