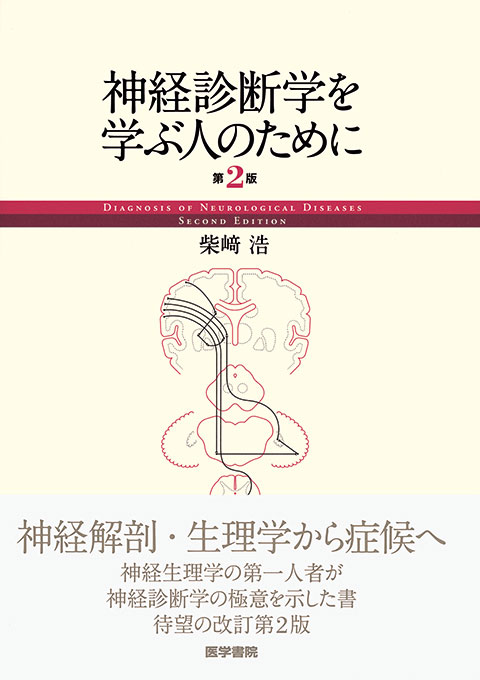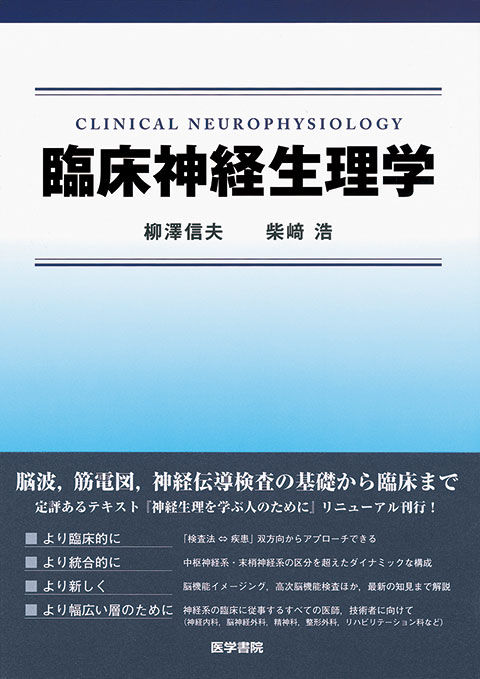神経診断学を学ぶ人のために
世界の神経生理学をリードしてきた第一人者による珠玉の神経診断学
もっと見る
日本のみならず世界の神経生理学をリードしてきた第一人者が、臨床神経学をこころざす後輩たちのために書き上げた珠玉の「神経診断学」。大脳、小脳、脳幹、脊髄、末梢神経、筋…といった構造(structure)ごとに書かれた本では決して捉えきれない神経系(system)のはたらき(「なぜ、どのような機序で症候が生じたか?」)が、神経生理学をきわめた著者ならではの明快な文章でクリアに見えてくる。
| 著 | 柴崎 浩 |
|---|---|
| 発行 | 2009年10月判型:B5頁:352 |
| ISBN | 978-4-260-00799-3 |
| 定価 | 9,350円 (本体8,500円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
序
神経疾患ほど多彩な症候を示す疾病は他の臓器には例を見ず,また1つの神経症候でもその性状と程度は症例によってさまざまである。さらに,画像上はほとんど同一に見える病変であっても,それに伴って現れる症候は症例によってその性状と程度が異なっている場合が多い。したがって,いくら電算化が進んでも神経診断学においては自動診断の実用化は無理であり,この点こそ臨床神経学が極めて興味深くかつ奥深い専門分野と考えられる大きな所以である。近年画像を中心とした種々の検査技術が発達して神経疾患の診断に盛んに利用されているが,形態画像で観察される異常所見と同部の神経組織のはたらきとは別問題であり,その機能脱落あるいは機能亢進状態はあくまでも神経症候から判断されなければならない。画像で脳・脊髄のある領域に明らかな異常がみられても,それに相当する神経脱落症候が観察されない場合には,その部分の機能は障害されていないか,あるいはその機能が代償されているために症候として現れていないことになる。また,画像では広範な領域に異常所見がみとめられても,症候学的にはそのうちの限られた部分の機能しか脱落していないことはしばしば経験するところである。すなわち,画像で異常信号域がみられても,同部の機能がどの程度障害されているか,またそれがどのように変化していくであろうかは,現れる症候とその発症様式および時間的経過からしか判断できないからである。一方,著明な神経脱落症候あるいは不随意運動がみとめられるのに,形態画像上は何も異常が検出されないことはしばしば経験されることである。もちろん,画像診断が果たす役割は極めて大きく,その診断学的価値を低く評価するものでは決してないが,限られた例外を除いて,画像所見だけに頼って診断を下すことは大きな誤りと考えられる。
実際の臨床現場では,少し熟練した神経内科医であれば,典型的な疾患をもつ患者が診察室に入って来た場合,その瞬間にほとんど直感的に診断をつけられることがまれでない。しかし,これは偶々診断が当たった場合は素晴らしいが,とんでもない誤診の原因になることもしばしばである。患者の健康と生命に責任をもつ立場からは,症候から種々の可能性を考慮に入れて病歴聴取と診察に当たり,理論的・系統的に考えて正しい診断に到達するのが妥当な方法である。ただし,神経内科医が普段の勉強を怠らずに経験を積んでくると,可能性のある状態をすべて網羅して考察しなくても,病歴聴取と診察の段階で自然に2,3の可能性に絞られてくる場合が多い。それは,長年の学習と経験の結果として,系統的な鑑別に対する考察過程が自動的に行われているからである。これは,おそらく囲碁や将棋において,初心者はあらゆる可能性を考慮したほうが間違いを少なくできるが,熟達した人にとってはほとんど直感的に2,3の可能性が浮かんできて,それに対してその先を深く‘読む’ことと同様と考えられる。
神経症候を正しく判定するには,それに関連した神経系の解剖学的知識と,関連構造を結ぶ連絡網すなわち神経ネットワーク,およびそのはたらきを正しく理解することが極めて大切である。本書は,主としてこれから臨床神経学を学ぶ人を対象として,神経解剖・生理学・薬理学から神経症候への橋渡し的内容について解説することを目的とした。一般に神経解剖学の解説書では,大脳,小脳,脳幹,脊髄,末梢神経,筋といった構造(structure)ごとの記載が多いが,本書ではそのような配列を避け,むしろ神経系(system)のはたらきに注目して章を設けた。また,神経疾患の各論およびその治療については完全にカバーすることはできないが,筆者が日頃から留意していることや,最近話題に上っている疾患については,それぞれ関連が深い章で取り上げたり,あるいはColumnを設けて述べることにした。また,必ずしも臨床神経学に従事する医師でなくても,看護師,理学療法士,言語療法士,臨床神経生理検査技師をはじめとして,神経疾患の診療に何らかのかたちで携わる人にもわかるような言葉を用いるように努めた。
本書では,通常の医学書と同様に,患者が訴える内容を症状(symptom),診察によって客観的にみとめられる所見を徴候(sign)と呼び,両者を合わせて症候(symptom and sign)と呼ぶことにする。また,神経組織の損傷を傷害(lesion),機能異常を障害(disturbance)と区別して呼ぶことにする。さらに,神経内科領域では中枢神経系,末梢神経系および筋の疾患を対象とするので,本書ではこれらすべてを含めて神経系(nervous system),神経学(neurology),神経学的(neurological)などと呼ぶことにする。すなわち,たとえば神経学的所見といった場合に,とくに指定しないかぎり中枢神経系,末梢神経系および筋に関する所見をすべて含めるという意味である。神経学的用語については,原則として日本神経学会および関連学会の用語集に沿うようにした(参考文献:日本神経学会用語委員会,2008;日本内科学会,1998)。なかには,筆者の判断で用語集に従わないほうがより妥当と考えられる用語を用いた場合もあるが,これは極めて例外である。また,外国人名の付いた疾患名や症候名などについては,一般にカナ読みで言い慣わされているものはカナ(原語)で,そうでないものや発音が難しいものは原語(カナ読み)で表現した。
中枢神経系の解剖学的位置関係を表現する場合に,左右は問題ないとしても,上下の位置関係については注意を要する。すなわち,たとえば脊髄の上下を例にとると,立位のヒトでは頸髄を上,腰髄を下と表現しても問題はないが,臥位ではその表現は厳密には正しくないことになる。すなわち,頭や身体の姿勢によって,脳と脊髄における各部位間の位置関係が変わってくる。したがって本書では,脳幹と脊髄については,頭に近い方向を吻側(rostral),足に近い方向を尾側(caudal)と表現することにする。しかし大脳半球に関しては,神経科学の領域では前頭部に近い方向を吻側,後頭部に近い方向を尾側と呼ぶことが多いが,ヒトの頭蓋内で吻側,尾側と呼ぶのは不自然であるので,原則として常識的に前後と表現することにする。また,大脳半球の外側面と内側面の位置関係については,神経科学領域の用語に従って,半球稜から遠い方向を腹側(ventral),半球稜に近い方向を背側(dorsal)と表現することにした。しかしこれについても,むしろ外側,内側の表現のほうがわかりやすいと考えられる場合には,必ずしも腹側・背側の表現にこだわらないことにした。
なお,本書で述べる内容は,筆者が九州大学神経内科教室に入局当時の教授黒岩義五郎先生,同じく助教授の荒木淑郎先生,ミネソタ大学神経内科にレジデントとして留学中に指導を受けたA. B. Baker先生,同じくJ. Logothetis先生(現在ギリシアのテサロニキ在住),英国ロンドンのQueen Square留学中に共同研究を行ったW. I. McDonald先生およびA. M. Halliday先生,京大在任中にお世話になった木村淳先生,および2003年から2年間共同研究を行った米国NIHの友人M. Hallett先生の影響を強く受けて,それらの知識を総合的に消化して自ら築き上げてきたものである。なお,これに類似した著書としては,筆者が中心となって編集した『ダイナミック神経診断学』(参考文献:柴崎ら,2001)があるが,それは多数の著者による分担執筆であったのに対して,本書は筆者が単独で執筆したものであり,内容はもちろんのこと,用語,形式,索引などすべての面において全体的な一貫性をもたせたことが特徴である。また,国内外の既存の教科書から文章を引用することをできるだけ避けて,筆者の知識として蓄えられた内容を自分の言葉で表現するように努めた。また,神経系の解剖図に関しては,本来脳の構造に対する理解が変化することはごく一部の例外を除いてないはずであるので,既存の図をそのまま模写することを避けてもある程度類似した図になることはやむを得ない。しかし,少なくとも機能的解剖図については,できるだけ筆者の原図を用いるようにした。さらに引用文献については,19世紀に発表された症例報告の原著も含めて,自分で直接目を通したものに限った。
本書の出版にあたっては,医学書院医学書籍編集部の井上弘子氏および同制作部の筒井進氏の的確な助言と綿密な配慮があったことを記し,深甚の謝意を表する。
2009年9月
柴崎 浩
神経疾患ほど多彩な症候を示す疾病は他の臓器には例を見ず,また1つの神経症候でもその性状と程度は症例によってさまざまである。さらに,画像上はほとんど同一に見える病変であっても,それに伴って現れる症候は症例によってその性状と程度が異なっている場合が多い。したがって,いくら電算化が進んでも神経診断学においては自動診断の実用化は無理であり,この点こそ臨床神経学が極めて興味深くかつ奥深い専門分野と考えられる大きな所以である。近年画像を中心とした種々の検査技術が発達して神経疾患の診断に盛んに利用されているが,形態画像で観察される異常所見と同部の神経組織のはたらきとは別問題であり,その機能脱落あるいは機能亢進状態はあくまでも神経症候から判断されなければならない。画像で脳・脊髄のある領域に明らかな異常がみられても,それに相当する神経脱落症候が観察されない場合には,その部分の機能は障害されていないか,あるいはその機能が代償されているために症候として現れていないことになる。また,画像では広範な領域に異常所見がみとめられても,症候学的にはそのうちの限られた部分の機能しか脱落していないことはしばしば経験するところである。すなわち,画像で異常信号域がみられても,同部の機能がどの程度障害されているか,またそれがどのように変化していくであろうかは,現れる症候とその発症様式および時間的経過からしか判断できないからである。一方,著明な神経脱落症候あるいは不随意運動がみとめられるのに,形態画像上は何も異常が検出されないことはしばしば経験されることである。もちろん,画像診断が果たす役割は極めて大きく,その診断学的価値を低く評価するものでは決してないが,限られた例外を除いて,画像所見だけに頼って診断を下すことは大きな誤りと考えられる。
実際の臨床現場では,少し熟練した神経内科医であれば,典型的な疾患をもつ患者が診察室に入って来た場合,その瞬間にほとんど直感的に診断をつけられることがまれでない。しかし,これは偶々診断が当たった場合は素晴らしいが,とんでもない誤診の原因になることもしばしばである。患者の健康と生命に責任をもつ立場からは,症候から種々の可能性を考慮に入れて病歴聴取と診察に当たり,理論的・系統的に考えて正しい診断に到達するのが妥当な方法である。ただし,神経内科医が普段の勉強を怠らずに経験を積んでくると,可能性のある状態をすべて網羅して考察しなくても,病歴聴取と診察の段階で自然に2,3の可能性に絞られてくる場合が多い。それは,長年の学習と経験の結果として,系統的な鑑別に対する考察過程が自動的に行われているからである。これは,おそらく囲碁や将棋において,初心者はあらゆる可能性を考慮したほうが間違いを少なくできるが,熟達した人にとってはほとんど直感的に2,3の可能性が浮かんできて,それに対してその先を深く‘読む’ことと同様と考えられる。
神経症候を正しく判定するには,それに関連した神経系の解剖学的知識と,関連構造を結ぶ連絡網すなわち神経ネットワーク,およびそのはたらきを正しく理解することが極めて大切である。本書は,主としてこれから臨床神経学を学ぶ人を対象として,神経解剖・生理学・薬理学から神経症候への橋渡し的内容について解説することを目的とした。一般に神経解剖学の解説書では,大脳,小脳,脳幹,脊髄,末梢神経,筋といった構造(structure)ごとの記載が多いが,本書ではそのような配列を避け,むしろ神経系(system)のはたらきに注目して章を設けた。また,神経疾患の各論およびその治療については完全にカバーすることはできないが,筆者が日頃から留意していることや,最近話題に上っている疾患については,それぞれ関連が深い章で取り上げたり,あるいはColumnを設けて述べることにした。また,必ずしも臨床神経学に従事する医師でなくても,看護師,理学療法士,言語療法士,臨床神経生理検査技師をはじめとして,神経疾患の診療に何らかのかたちで携わる人にもわかるような言葉を用いるように努めた。
本書では,通常の医学書と同様に,患者が訴える内容を症状(symptom),診察によって客観的にみとめられる所見を徴候(sign)と呼び,両者を合わせて症候(symptom and sign)と呼ぶことにする。また,神経組織の損傷を傷害(lesion),機能異常を障害(disturbance)と区別して呼ぶことにする。さらに,神経内科領域では中枢神経系,末梢神経系および筋の疾患を対象とするので,本書ではこれらすべてを含めて神経系(nervous system),神経学(neurology),神経学的(neurological)などと呼ぶことにする。すなわち,たとえば神経学的所見といった場合に,とくに指定しないかぎり中枢神経系,末梢神経系および筋に関する所見をすべて含めるという意味である。神経学的用語については,原則として日本神経学会および関連学会の用語集に沿うようにした(参考文献:日本神経学会用語委員会,2008;日本内科学会,1998)。なかには,筆者の判断で用語集に従わないほうがより妥当と考えられる用語を用いた場合もあるが,これは極めて例外である。また,外国人名の付いた疾患名や症候名などについては,一般にカナ読みで言い慣わされているものはカナ(原語)で,そうでないものや発音が難しいものは原語(カナ読み)で表現した。
中枢神経系の解剖学的位置関係を表現する場合に,左右は問題ないとしても,上下の位置関係については注意を要する。すなわち,たとえば脊髄の上下を例にとると,立位のヒトでは頸髄を上,腰髄を下と表現しても問題はないが,臥位ではその表現は厳密には正しくないことになる。すなわち,頭や身体の姿勢によって,脳と脊髄における各部位間の位置関係が変わってくる。したがって本書では,脳幹と脊髄については,頭に近い方向を吻側(rostral),足に近い方向を尾側(caudal)と表現することにする。しかし大脳半球に関しては,神経科学の領域では前頭部に近い方向を吻側,後頭部に近い方向を尾側と呼ぶことが多いが,ヒトの頭蓋内で吻側,尾側と呼ぶのは不自然であるので,原則として常識的に前後と表現することにする。また,大脳半球の外側面と内側面の位置関係については,神経科学領域の用語に従って,半球稜から遠い方向を腹側(ventral),半球稜に近い方向を背側(dorsal)と表現することにした。しかしこれについても,むしろ外側,内側の表現のほうがわかりやすいと考えられる場合には,必ずしも腹側・背側の表現にこだわらないことにした。
なお,本書で述べる内容は,筆者が九州大学神経内科教室に入局当時の教授黒岩義五郎先生,同じく助教授の荒木淑郎先生,ミネソタ大学神経内科にレジデントとして留学中に指導を受けたA. B. Baker先生,同じくJ. Logothetis先生(現在ギリシアのテサロニキ在住),英国ロンドンのQueen Square留学中に共同研究を行ったW. I. McDonald先生およびA. M. Halliday先生,京大在任中にお世話になった木村淳先生,および2003年から2年間共同研究を行った米国NIHの友人M. Hallett先生の影響を強く受けて,それらの知識を総合的に消化して自ら築き上げてきたものである。なお,これに類似した著書としては,筆者が中心となって編集した『ダイナミック神経診断学』(参考文献:柴崎ら,2001)があるが,それは多数の著者による分担執筆であったのに対して,本書は筆者が単独で執筆したものであり,内容はもちろんのこと,用語,形式,索引などすべての面において全体的な一貫性をもたせたことが特徴である。また,国内外の既存の教科書から文章を引用することをできるだけ避けて,筆者の知識として蓄えられた内容を自分の言葉で表現するように努めた。また,神経系の解剖図に関しては,本来脳の構造に対する理解が変化することはごく一部の例外を除いてないはずであるので,既存の図をそのまま模写することを避けてもある程度類似した図になることはやむを得ない。しかし,少なくとも機能的解剖図については,できるだけ筆者の原図を用いるようにした。さらに引用文献については,19世紀に発表された症例報告の原著も含めて,自分で直接目を通したものに限った。
本書の出版にあたっては,医学書院医学書籍編集部の井上弘子氏および同制作部の筒井進氏の的確な助言と綿密な配慮があったことを記し,深甚の謝意を表する。
2009年9月
柴崎 浩
目次
開く
1 神経疾患の診断(総論)
2 病歴聴取
3 診察の手順
4 意識状態の把握
5 脳神経領域と脳幹
6 嗅覚
7 視覚
8 瞳孔と調節
9 外眼筋,注視,眼球運動
10 三叉神経
11 顔面神経
12 聴覚
13 平衡覚
14 舌咽神経,迷走神経,舌下神経
15 頸部と体幹
16 四肢の運動機能
17 腱反射と病的反射
18 不随意運動
19 体性感覚系
20 自律神経系
21 姿勢・歩行
22 精神・認知機能
23 失語・失行・失認
24 認知症
25 発作性・機能性神経疾患
26 心因性神経疾患
27 視床下部と神経内分泌
28 神経内科的緊急症
29 日常生活障害度
30 機能回復と予後
31 検査方針の立て方
文献
あとがき
索引
2 病歴聴取
3 診察の手順
4 意識状態の把握
5 脳神経領域と脳幹
6 嗅覚
7 視覚
8 瞳孔と調節
9 外眼筋,注視,眼球運動
10 三叉神経
11 顔面神経
12 聴覚
13 平衡覚
14 舌咽神経,迷走神経,舌下神経
15 頸部と体幹
16 四肢の運動機能
17 腱反射と病的反射
18 不随意運動
19 体性感覚系
20 自律神経系
21 姿勢・歩行
22 精神・認知機能
23 失語・失行・失認
24 認知症
25 発作性・機能性神経疾患
26 心因性神経疾患
27 視床下部と神経内分泌
28 神経内科的緊急症
29 日常生活障害度
30 機能回復と予後
31 検査方針の立て方
文献
あとがき
索引
書評
開く
いかにして正しい診断に到達できるか
書評者: 水野 美邦 (順天堂越谷病院院長)
このたび,柴崎浩先生が『神経診断学を学ぶ人のために』という本を書かれた。わが国における臨床神経学・神経生理学の第一人者である先生の単著である。アメリカでのレジデント生活の経験も持たれる先生の御本で大変期待の持たれる単行本である。先生は,京大臨床神経学講座の主任教授を務められ,今は退官して武田総合病院の顧問をしておられる。
目次を拝見すると,神経疾患の診断(総論),病歴聴取,診察の手順,意識状態の把握,脳神経領域と脳幹と続き,後者はさらに嗅覚,視覚から舌下神経まで,詳しく記載されている。次は,頸部と体幹,四肢の運動機能,腱反射と病的反射,不随意運動,体性感覚系,自律神経系,姿勢・歩行と続き,神経学的診察が完了する。さらにその先には,精神・認知機能,失語・失行・失認,認知症,発作性・機能性神経疾患,心因性神経疾患,視床下部と神経内分泌,神経内科的緊急症,日常生活障害度,機能回復と予後,検査方針の立て方と続き,神経学的診察の結果から,どのようにして病因診断に進むのかがわかるように配慮されている。
最初の神経疾患の診断の項目を紐解くと,神経疾患の三段階診断法の重要性をまず強調され,部位診断,病因診断,臨床診断の順になされるべきことが強調されている。病歴聴取では,若年者の脳血管障害の重要性が強調されている。若年者にも,高血圧,高脂血症,糖尿病などの危険因子が広がり,脳血栓や脳出血がまれでないことが強調され,さらにSLE(全身性エリテマトーデス)やホモシスチン尿症などにも気をつけることが記されている。脳神経に至っては,詳細に図での解説を含みながら,種々の症候が出てくる状態が記載されている。
不随意運動の項は,柴崎先生の御専門領域で,各不随意運動の詳細が,ご自身の研究成果を踏まえた図を取り入れながら解説されており,専門家にとっても貴重な内容である。例えばミオクローヌスの項では,皮質反射性ミオクローヌス,脳幹起源のミオクローヌス,脊髄起源のミオクローヌス,分類未定のミオクローヌスに分け,それぞれどのような疾患があるか記載されている。さらに嬉しいことには,主な疾患の解説が,Columnの形で随所に挿入されていることである。
本書は神経症状を有する患者さんを拝見する神経内科医が,いかにして正しい診断に到達できるか,最初の診断からのプロセスを丁寧に解説した素晴らしい書物である。病歴聴取での大切な要点,すなわち,部位診断,病因診断,臨床診断に分けて診断を記載することに始まり,そこからどのような検査プランを立てればよいかがわかるように記載されている。さらに,診察の過程で生じるさまざまな疑問に答えるべく,それぞれの異常を出す,主な疾患にも触れ,さらに視床下部と神経内分泌や神経内科的緊急症にも触れ,どのような患者さんに接しても不自由を感じないように配慮されている。
本書は,神経内科の臨床を始めた初心者のみならず,初心者の指導に当たっている熟練の神経内科医にも読むことが薦められる良書である。この本の作成に当たられた柴崎浩先生に深甚の謝意を申し上げたい。
第一級の神経診断学として推薦する
書評者: 荒木 淑郎 (熊本大名誉教授)
この度,日本を代表する臨床神経生理学者で,かつ優れた神経内科医である京都大学名誉教授 柴崎浩氏により,新しい神経診断学の書物が刊行された。国内はもちろん,国際的にも高名な著者による診断学の手引書であり,この機会を借りて心から喜び,お祝いを伝えたい。
日本で最初に神経内科の講座が文部省により承認されたのは1963年,九州大学医学部であった。翌年には,附属病院に独立の神経内科が発足した。黒岩義五郎教授,私が助教授を務めたとき,柴崎氏は入局した。この出会いを通じて,氏の性格,態度を知ることができた。柴崎氏は,素直で,真摯な努力家であり,優れた才能を持ちながら謙虚であり,友人を大切にする,素晴らしい人格者であることを知り,将来必ずや嘱望される医師になるであろうと期待していた。果たせるかな,米国ミネソタ大学神経内科レジデントを終え,英国留学で神経生理学を深く学び研究業績を挙げ,今や国際的に活躍する学者へと成長した。同門の一人として喜びに堪えない。
特に,京都大学退官後,米国(NINDB)のFogarty Scholarに選ばれ,2年間自由な研究に従事できるという日本人として最初の栄誉を与えられたことは,いかに,柴崎氏の研究業績が高く国際的に評価されているかを示すものであるといえよう。
さて,この書物は,著者の単独執筆であり,書物全体に一貫性を持って,診断の基礎的記述,神経解剖図,用語に至るまで並々ならぬ工夫がなされている。柴崎氏の臨床家として,また教育者としての親切な指導が感じられ,まさに,第一級の神経診断書といっても過言ではない。
まだ,画像診断学が今日のように進歩していない時代に臨床神経学を学んだ私たちの時代は,患者から詳しい病歴をとり,頭部から下肢に及ぶ神経診断手技から,神経学的異常所見をとらえそれを総合して,臨床診断を考えていた。それには,神経学的ポジティブ所見とネガティブ所見があることを知った上での診断であった。診断に至る過程こそ臨床神経学の魅力であった。この診断法は時代が変わっても不変である。
一般に多くの人から,神経学は“診断は謎を解くようで面白いが,診断ができても治療法がない”と批判されたことは事実である。しかし,批判されても人間の脳の機能はいまだ十分解明されておらず,神秘性を保っており,挑戦に値する研究分野であることは万人が認めている。さらに神経病の治療は最近,治療薬の開発が進み,リハビリテーションの導入によって進歩していることは事実である。
ところで最近,画像診断やその他の診断技術が進み,神経症状や徴候をおろそかにする傾向が出てきた。また,診察に当たり,呼吸器ならば肺,消化器ならば胃腸といった局所だけを診るようになり,全身を診ようとしない医師が増えてきたことは憂うべきことである。この点,神経診断学はベッドサイドで患者の全身を診ながら,神経系統を診ることを基礎としている唯一の診断学であることを強調したい。
この書物は,31章からなり,解剖から生理機構を介して理解しやすいように配慮されている。また最近話題となっている病気,徴候,分類などをColumnとして簡潔明瞭に説明されている。このColumnを読んで学ぶことが多い。本書は臨床神経学に興味を持つ医師,看護師,理学療法士,言語療法士,臨床神経生理学検査技師を対象としてわかりやすく説明された最良の診断学として推薦したい。値段も手ごろである。
神経診断学の極意を解き明かす
書評者: 田代 邦雄 (北大名誉教授/北祐会神経内科病院顧問)
神経学,神経内科学,神経症候学,神経生理学,神経病理学など,神経に関する書名のある教科書はわが国においても数多く出版されているが,「神経診断学」を冠するものとしては,本書の著者である柴崎浩先生らがまとめられた「ダイナミック神経診断学」(柴崎浩,田川皓一,湯浅龍彦 共編)とする分担執筆があるのみである。
このたび,柴崎浩先生(著)の単行本が世に出ることとなったことは画期的であり「神経診断学とは何か!」が語りかけられることとなった。本書の意図,特徴はその序に詳しく述べられており,その内のエッセンスの一部をそのまま引用すれば,“少し熟練した神経内科医であれば,典型的な疾患をもつ患者が診察室に入って来た場合,その瞬間にほとんど直感的に診断をつけられることがまれでない”,しかし“症候から種々の可能性を考慮に入れて病歴聴取と診察に当たり,理論的・系統的に考えて正しい診断に到達するのが妥当な方法である”(序より一部引用)という言葉に集約されると思われる。
本書は,膨大な神経学の知識と,米国での神経内科レジデントも修められた臨床経験,さらには現在も臨床神経生理学の世界的権威として誰もが認める存在である先生が,神経学の原点ともいえる「神経診断学のエッセンス」を明解に説いておられる珠玉の名著である。
第1章「神経疾患の診断(総論)」から第31章「検査方針の立て方」,そして主要文献一覧と,最後に「神経学をこれから学ぼうという人へ―あとがきに代えて」という締めのメッセージまで実に細やかに神経診断学の極意を解き明かされたことに感動する次第である。
本書の読み方はいろいろあると考える。まず全体を通読し先生のコンセプトを理解することをお勧めしたい。それは,過去の教科書の引用ではなく,それらを踏まえ,しかし,すべてを自分の目でみるという先生自身による信念が感じられ,実に読んでいて楽しく,先生から直接手を取るように指導をしていただいているような実感がわいてくるからである。
本書は通読も可,しかし興味ある項目ごとにピックアップし,自分の考えと比較してQ&Aを想定し,柴崎先生との対話,意見の交換,さらに論議する,という楽しさもわき上がってくる。すなわち自分の手技や考え方と比べてお互いの主張を戦わせることも大切である。
神経診断学には流派による違いもあるであろう。しかし,本書ではそれらを理解された上で,御自身の経験を踏まえ,より理解しやすいように語りかけるという配慮が随所に感じられるのである。
本書が“神経診断学を学ぶ人のために”大きな道標になり続けること,ひいては日本の臨床神経学の向上,さらなる発展への原動力となることを確信する次第である。
先生は1964年九大卒,在日米陸軍病院インターン,九大神経内科,そして米国での神経内科レジデントと臨床神経内科医であるばかりでなく,英国,米国,そして世界の神経学・脳科学のリーダーとともに日本の代表としての御活躍は周知の事実であり,先生の今後ますますの御発展を心からお祈りする次第である。
書評者: 水野 美邦 (順天堂越谷病院院長)
このたび,柴崎浩先生が『神経診断学を学ぶ人のために』という本を書かれた。わが国における臨床神経学・神経生理学の第一人者である先生の単著である。アメリカでのレジデント生活の経験も持たれる先生の御本で大変期待の持たれる単行本である。先生は,京大臨床神経学講座の主任教授を務められ,今は退官して武田総合病院の顧問をしておられる。
目次を拝見すると,神経疾患の診断(総論),病歴聴取,診察の手順,意識状態の把握,脳神経領域と脳幹と続き,後者はさらに嗅覚,視覚から舌下神経まで,詳しく記載されている。次は,頸部と体幹,四肢の運動機能,腱反射と病的反射,不随意運動,体性感覚系,自律神経系,姿勢・歩行と続き,神経学的診察が完了する。さらにその先には,精神・認知機能,失語・失行・失認,認知症,発作性・機能性神経疾患,心因性神経疾患,視床下部と神経内分泌,神経内科的緊急症,日常生活障害度,機能回復と予後,検査方針の立て方と続き,神経学的診察の結果から,どのようにして病因診断に進むのかがわかるように配慮されている。
最初の神経疾患の診断の項目を紐解くと,神経疾患の三段階診断法の重要性をまず強調され,部位診断,病因診断,臨床診断の順になされるべきことが強調されている。病歴聴取では,若年者の脳血管障害の重要性が強調されている。若年者にも,高血圧,高脂血症,糖尿病などの危険因子が広がり,脳血栓や脳出血がまれでないことが強調され,さらにSLE(全身性エリテマトーデス)やホモシスチン尿症などにも気をつけることが記されている。脳神経に至っては,詳細に図での解説を含みながら,種々の症候が出てくる状態が記載されている。
不随意運動の項は,柴崎先生の御専門領域で,各不随意運動の詳細が,ご自身の研究成果を踏まえた図を取り入れながら解説されており,専門家にとっても貴重な内容である。例えばミオクローヌスの項では,皮質反射性ミオクローヌス,脳幹起源のミオクローヌス,脊髄起源のミオクローヌス,分類未定のミオクローヌスに分け,それぞれどのような疾患があるか記載されている。さらに嬉しいことには,主な疾患の解説が,Columnの形で随所に挿入されていることである。
本書は神経症状を有する患者さんを拝見する神経内科医が,いかにして正しい診断に到達できるか,最初の診断からのプロセスを丁寧に解説した素晴らしい書物である。病歴聴取での大切な要点,すなわち,部位診断,病因診断,臨床診断に分けて診断を記載することに始まり,そこからどのような検査プランを立てればよいかがわかるように記載されている。さらに,診察の過程で生じるさまざまな疑問に答えるべく,それぞれの異常を出す,主な疾患にも触れ,さらに視床下部と神経内分泌や神経内科的緊急症にも触れ,どのような患者さんに接しても不自由を感じないように配慮されている。
本書は,神経内科の臨床を始めた初心者のみならず,初心者の指導に当たっている熟練の神経内科医にも読むことが薦められる良書である。この本の作成に当たられた柴崎浩先生に深甚の謝意を申し上げたい。
第一級の神経診断学として推薦する
書評者: 荒木 淑郎 (熊本大名誉教授)
この度,日本を代表する臨床神経生理学者で,かつ優れた神経内科医である京都大学名誉教授 柴崎浩氏により,新しい神経診断学の書物が刊行された。国内はもちろん,国際的にも高名な著者による診断学の手引書であり,この機会を借りて心から喜び,お祝いを伝えたい。
日本で最初に神経内科の講座が文部省により承認されたのは1963年,九州大学医学部であった。翌年には,附属病院に独立の神経内科が発足した。黒岩義五郎教授,私が助教授を務めたとき,柴崎氏は入局した。この出会いを通じて,氏の性格,態度を知ることができた。柴崎氏は,素直で,真摯な努力家であり,優れた才能を持ちながら謙虚であり,友人を大切にする,素晴らしい人格者であることを知り,将来必ずや嘱望される医師になるであろうと期待していた。果たせるかな,米国ミネソタ大学神経内科レジデントを終え,英国留学で神経生理学を深く学び研究業績を挙げ,今や国際的に活躍する学者へと成長した。同門の一人として喜びに堪えない。
特に,京都大学退官後,米国(NINDB)のFogarty Scholarに選ばれ,2年間自由な研究に従事できるという日本人として最初の栄誉を与えられたことは,いかに,柴崎氏の研究業績が高く国際的に評価されているかを示すものであるといえよう。
さて,この書物は,著者の単独執筆であり,書物全体に一貫性を持って,診断の基礎的記述,神経解剖図,用語に至るまで並々ならぬ工夫がなされている。柴崎氏の臨床家として,また教育者としての親切な指導が感じられ,まさに,第一級の神経診断書といっても過言ではない。
まだ,画像診断学が今日のように進歩していない時代に臨床神経学を学んだ私たちの時代は,患者から詳しい病歴をとり,頭部から下肢に及ぶ神経診断手技から,神経学的異常所見をとらえそれを総合して,臨床診断を考えていた。それには,神経学的ポジティブ所見とネガティブ所見があることを知った上での診断であった。診断に至る過程こそ臨床神経学の魅力であった。この診断法は時代が変わっても不変である。
一般に多くの人から,神経学は“診断は謎を解くようで面白いが,診断ができても治療法がない”と批判されたことは事実である。しかし,批判されても人間の脳の機能はいまだ十分解明されておらず,神秘性を保っており,挑戦に値する研究分野であることは万人が認めている。さらに神経病の治療は最近,治療薬の開発が進み,リハビリテーションの導入によって進歩していることは事実である。
ところで最近,画像診断やその他の診断技術が進み,神経症状や徴候をおろそかにする傾向が出てきた。また,診察に当たり,呼吸器ならば肺,消化器ならば胃腸といった局所だけを診るようになり,全身を診ようとしない医師が増えてきたことは憂うべきことである。この点,神経診断学はベッドサイドで患者の全身を診ながら,神経系統を診ることを基礎としている唯一の診断学であることを強調したい。
この書物は,31章からなり,解剖から生理機構を介して理解しやすいように配慮されている。また最近話題となっている病気,徴候,分類などをColumnとして簡潔明瞭に説明されている。このColumnを読んで学ぶことが多い。本書は臨床神経学に興味を持つ医師,看護師,理学療法士,言語療法士,臨床神経生理学検査技師を対象としてわかりやすく説明された最良の診断学として推薦したい。値段も手ごろである。
神経診断学の極意を解き明かす
書評者: 田代 邦雄 (北大名誉教授/北祐会神経内科病院顧問)
神経学,神経内科学,神経症候学,神経生理学,神経病理学など,神経に関する書名のある教科書はわが国においても数多く出版されているが,「神経診断学」を冠するものとしては,本書の著者である柴崎浩先生らがまとめられた「ダイナミック神経診断学」(柴崎浩,田川皓一,湯浅龍彦 共編)とする分担執筆があるのみである。
このたび,柴崎浩先生(著)の単行本が世に出ることとなったことは画期的であり「神経診断学とは何か!」が語りかけられることとなった。本書の意図,特徴はその序に詳しく述べられており,その内のエッセンスの一部をそのまま引用すれば,“少し熟練した神経内科医であれば,典型的な疾患をもつ患者が診察室に入って来た場合,その瞬間にほとんど直感的に診断をつけられることがまれでない”,しかし“症候から種々の可能性を考慮に入れて病歴聴取と診察に当たり,理論的・系統的に考えて正しい診断に到達するのが妥当な方法である”(序より一部引用)という言葉に集約されると思われる。
本書は,膨大な神経学の知識と,米国での神経内科レジデントも修められた臨床経験,さらには現在も臨床神経生理学の世界的権威として誰もが認める存在である先生が,神経学の原点ともいえる「神経診断学のエッセンス」を明解に説いておられる珠玉の名著である。
第1章「神経疾患の診断(総論)」から第31章「検査方針の立て方」,そして主要文献一覧と,最後に「神経学をこれから学ぼうという人へ―あとがきに代えて」という締めのメッセージまで実に細やかに神経診断学の極意を解き明かされたことに感動する次第である。
本書の読み方はいろいろあると考える。まず全体を通読し先生のコンセプトを理解することをお勧めしたい。それは,過去の教科書の引用ではなく,それらを踏まえ,しかし,すべてを自分の目でみるという先生自身による信念が感じられ,実に読んでいて楽しく,先生から直接手を取るように指導をしていただいているような実感がわいてくるからである。
本書は通読も可,しかし興味ある項目ごとにピックアップし,自分の考えと比較してQ&Aを想定し,柴崎先生との対話,意見の交換,さらに論議する,という楽しさもわき上がってくる。すなわち自分の手技や考え方と比べてお互いの主張を戦わせることも大切である。
神経診断学には流派による違いもあるであろう。しかし,本書ではそれらを理解された上で,御自身の経験を踏まえ,より理解しやすいように語りかけるという配慮が随所に感じられるのである。
本書が“神経診断学を学ぶ人のために”大きな道標になり続けること,ひいては日本の臨床神経学の向上,さらなる発展への原動力となることを確信する次第である。
先生は1964年九大卒,在日米陸軍病院インターン,九大神経内科,そして米国での神経内科レジデントと臨床神経内科医であるばかりでなく,英国,米国,そして世界の神経学・脳科学のリーダーとともに日本の代表としての御活躍は周知の事実であり,先生の今後ますますの御発展を心からお祈りする次第である。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。