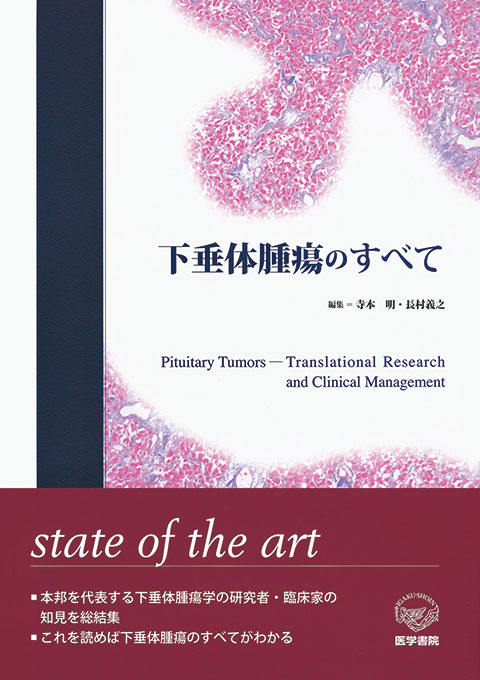下垂体腫瘍のすべて
下垂体腫瘍の決定版。すべての下垂体疾患治療に携わる医師のために。
もっと見る
世界でも例をみない下垂体手術2,250例を手がけた脳神経外科医とその症例の病理検索を手がけた病理医を編者に、日本全国の下垂体腫瘍のエキスパートが執筆した下垂体腫瘍にあらゆる方向からアプローチした専門書。下垂体腫瘍の基礎から臨床までを網羅する、「The 下垂体腫瘍」ともいうべき決定版。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
下垂体腫瘍は脳腫瘍に分類されるが,通常の脳腫瘍とは明らかに異質な疾患である.その理由は,発生母地である下垂体という内分泌腺の特異性にある.すなわち,下垂体は直接的なホルモン分泌の司令塔であり全身に影響を及ぼすものの,一方では自らもフィードバックを受けること,頭蓋内ではあるが髄液腔内ではないという特有な解剖学的特徴を有すること,さらにトルコ鞍という神経頭蓋と顔面頭蓋の境界部に局在することなどに由来すると思われる.そのため,組織形態から分類される大半の脳腫瘍と異なり,下垂体腫瘍は主としてそのホルモン分泌能の観点から命名や分類がなされている.病理組織学の分野でもいち早く免疫組織化学が適用され,機能的病理学の先駆けとなった.腫瘍から過剰に分泌されたホルモンや,一方では不足となったホルモンの影響で,極めて多様な臨床症候が展開される.これは例えばgliomaや髄膜腫のような一般の脳腫瘍にはみられない大きな特徴である.治療法に関しても,有効な内分泌療法が数多く知られており,手術も主として鼻腔のほうからアプローチするという特異な診療分野を形成している.その病態や臨床を研究し,治療成績を向上させる目的で日本間脳下垂体腫瘍学会という独自の学会が存在している.ここでは間脳下垂体内分泌学の発展を背景としながら,基礎医学者,内分泌内科医,脳神経外科医,放射線科医などが下垂体腫瘍学に関して白熱した議論を戦わせている.
編者らは,1970年代に大学医学部を卒業し,70年代以後に飛躍的に発展した間脳下垂体内分泌学の研究や臨床に魅せられ,40年近くにわたって一途にこの道の仕事に打ち込んできた.その私たちの集大成の事業の一つとして,現時点で最良の下垂体腫瘍学の成書を作成したいと考えた次第である.欧米からは,ほぼ毎年のごとく下垂体あるいは下垂体腫瘍に関する成書が刊行されているが,わが国では下垂体腫瘍を基礎・臨床の両面から総合的に取りまとめたものがない.言うまでもなく,この分野の研究や臨床の広がりと深みからみて,私たちだけではとても全体をカバーできるものでないため,研究畑や臨床分野の多くのエキスパートに執筆をお願いした次第である.それゆえ,本書の筆者としては,現在のわが国を代表する下垂体あるいは下垂体腫瘍学に関する現役の研究者や臨床家がほぼ網羅されているものと考えられる.
80数名に及ぶ本書の筆者らに,それぞれの得意分野の最新情報を中心に,実に内容の充実した原稿を書き上げていただいた.そのため,本書は現時点における下垂体腫瘍学のstate of the artといっても過言ではなく,今後少なくとも10年間は下垂体腫瘍の研究や臨床を目指す人の指標となりうるものと信じている.
2009年8月
寺本 明
長村義之
下垂体腫瘍は脳腫瘍に分類されるが,通常の脳腫瘍とは明らかに異質な疾患である.その理由は,発生母地である下垂体という内分泌腺の特異性にある.すなわち,下垂体は直接的なホルモン分泌の司令塔であり全身に影響を及ぼすものの,一方では自らもフィードバックを受けること,頭蓋内ではあるが髄液腔内ではないという特有な解剖学的特徴を有すること,さらにトルコ鞍という神経頭蓋と顔面頭蓋の境界部に局在することなどに由来すると思われる.そのため,組織形態から分類される大半の脳腫瘍と異なり,下垂体腫瘍は主としてそのホルモン分泌能の観点から命名や分類がなされている.病理組織学の分野でもいち早く免疫組織化学が適用され,機能的病理学の先駆けとなった.腫瘍から過剰に分泌されたホルモンや,一方では不足となったホルモンの影響で,極めて多様な臨床症候が展開される.これは例えばgliomaや髄膜腫のような一般の脳腫瘍にはみられない大きな特徴である.治療法に関しても,有効な内分泌療法が数多く知られており,手術も主として鼻腔のほうからアプローチするという特異な診療分野を形成している.その病態や臨床を研究し,治療成績を向上させる目的で日本間脳下垂体腫瘍学会という独自の学会が存在している.ここでは間脳下垂体内分泌学の発展を背景としながら,基礎医学者,内分泌内科医,脳神経外科医,放射線科医などが下垂体腫瘍学に関して白熱した議論を戦わせている.
編者らは,1970年代に大学医学部を卒業し,70年代以後に飛躍的に発展した間脳下垂体内分泌学の研究や臨床に魅せられ,40年近くにわたって一途にこの道の仕事に打ち込んできた.その私たちの集大成の事業の一つとして,現時点で最良の下垂体腫瘍学の成書を作成したいと考えた次第である.欧米からは,ほぼ毎年のごとく下垂体あるいは下垂体腫瘍に関する成書が刊行されているが,わが国では下垂体腫瘍を基礎・臨床の両面から総合的に取りまとめたものがない.言うまでもなく,この分野の研究や臨床の広がりと深みからみて,私たちだけではとても全体をカバーできるものでないため,研究畑や臨床分野の多くのエキスパートに執筆をお願いした次第である.それゆえ,本書の筆者としては,現在のわが国を代表する下垂体あるいは下垂体腫瘍学に関する現役の研究者や臨床家がほぼ網羅されているものと考えられる.
80数名に及ぶ本書の筆者らに,それぞれの得意分野の最新情報を中心に,実に内容の充実した原稿を書き上げていただいた.そのため,本書は現時点における下垂体腫瘍学のstate of the artといっても過言ではなく,今後少なくとも10年間は下垂体腫瘍の研究や臨床を目指す人の指標となりうるものと信じている.
2009年8月
寺本 明
長村義之
目次
開く
I部 視床下部・下垂体の正常構造と機能
1章 視床下部・下垂体の発生
2章 視床下部・下垂体の正常構造
3章 下垂体ホルモンの分泌機構
II部 下垂体腫瘍の基礎研究
1章 下垂体腫瘍の分子生物学:転写因子と機能発現のメカニズム
2章 下垂体腺腫の分子病理学
3章 下垂体腫瘍の実験モデル
4章 下垂体腫瘍浸潤のメカニズム
5章 下垂体腫瘍の疫学・家族発症
6章 下垂体前葉の培養細胞株
7章 薬物療法の分子メカニズム
III部 下垂体腫瘍の病理
1章 下垂体腫瘍の機能的病理分類
2章 その特殊型と関連腫瘍
IV部 下垂体腫瘍の診断(内分泌検査と画像検査)
1章 内分泌検査とその実際
2章 画像による鑑別診断
3章 微小腺腫の画像診断
4章 3T-MRIの応用と有用性
5章 海綿静脈洞サンプリング
V部 主な下垂体腫瘍の診断と治療
1章 下垂体腫瘍 臨床総論
2章 非機能性腺腫の診断と治療
3章 先端巨大症の診断と治療
4章 プロラクチン産生腺腫
5章 ACTH産生腺腫
6章 ゴナドトロピン産生腺腫
7章 TSH産生下垂体腺腫
VI部 特異な疾患概念
1章 下垂体偶発腫
2章 Subclinical Cushing disease
3章 小児下垂体腺腫
4章 下垂体卒中
5章 異所性下垂体腺腫
6章 多発性内分泌腫瘍症1型など
VII部 腫瘍類似病変
1章 Rathke嚢胞
2章 くも膜嚢胞および非特異的嚢胞
3章 リンパ球性下垂体炎(含:肉芽腫性下垂体炎)
4章 下垂体過形成
5章 Empty sella(トルコ鞍空洞症)
6章 Langerhans細胞組織球症
7章 神経サルコイドーシス
VIII部 下垂体腫瘍の治療
1章 手術療法
2章 薬物療法-現状と今後の展開
3章 放射線療法
4章 下垂体ホルモン補償療法
IX部 下垂体腫瘍の長期予後
付録 下垂体腫瘍臨床のガイドラインとデータブック
付録1 先端巨大症および下垂体性巨人症の診断と治療の手引き
付録2 プロラクチン(PRL)分泌過剰症の治療の手引き
付録3 Cushing病の診断と治療の手引き
付録4 Pre(sub)-clinical Cushing病の診断と治療の手引き
付録5 下垂体ゴナドトロピン産生腫瘍の診断の手引き
付録6 下垂体偶発腫(インシデンタローマ)の診断の手引き
付録7 Knosp分類(下垂体腫瘍の側方進展度)
付録8 成人成長ホルモン(GH)分泌不全症の診断と治療の手引き
付録9 下垂体関連ホルモン基準値
付録10 日本人血中IGF-1濃度基準範囲(「第一」キット)
索引
1章 視床下部・下垂体の発生
2章 視床下部・下垂体の正常構造
3章 下垂体ホルモンの分泌機構
II部 下垂体腫瘍の基礎研究
1章 下垂体腫瘍の分子生物学:転写因子と機能発現のメカニズム
2章 下垂体腺腫の分子病理学
3章 下垂体腫瘍の実験モデル
4章 下垂体腫瘍浸潤のメカニズム
5章 下垂体腫瘍の疫学・家族発症
6章 下垂体前葉の培養細胞株
7章 薬物療法の分子メカニズム
III部 下垂体腫瘍の病理
1章 下垂体腫瘍の機能的病理分類
2章 その特殊型と関連腫瘍
IV部 下垂体腫瘍の診断(内分泌検査と画像検査)
1章 内分泌検査とその実際
2章 画像による鑑別診断
3章 微小腺腫の画像診断
4章 3T-MRIの応用と有用性
5章 海綿静脈洞サンプリング
V部 主な下垂体腫瘍の診断と治療
1章 下垂体腫瘍 臨床総論
2章 非機能性腺腫の診断と治療
3章 先端巨大症の診断と治療
4章 プロラクチン産生腺腫
5章 ACTH産生腺腫
6章 ゴナドトロピン産生腺腫
7章 TSH産生下垂体腺腫
VI部 特異な疾患概念
1章 下垂体偶発腫
2章 Subclinical Cushing disease
3章 小児下垂体腺腫
4章 下垂体卒中
5章 異所性下垂体腺腫
6章 多発性内分泌腫瘍症1型など
VII部 腫瘍類似病変
1章 Rathke嚢胞
2章 くも膜嚢胞および非特異的嚢胞
3章 リンパ球性下垂体炎(含:肉芽腫性下垂体炎)
4章 下垂体過形成
5章 Empty sella(トルコ鞍空洞症)
6章 Langerhans細胞組織球症
7章 神経サルコイドーシス
VIII部 下垂体腫瘍の治療
1章 手術療法
2章 薬物療法-現状と今後の展開
3章 放射線療法
4章 下垂体ホルモン補償療法
IX部 下垂体腫瘍の長期予後
付録 下垂体腫瘍臨床のガイドラインとデータブック
付録1 先端巨大症および下垂体性巨人症の診断と治療の手引き
付録2 プロラクチン(PRL)分泌過剰症の治療の手引き
付録3 Cushing病の診断と治療の手引き
付録4 Pre(sub)-clinical Cushing病の診断と治療の手引き
付録5 下垂体ゴナドトロピン産生腫瘍の診断の手引き
付録6 下垂体偶発腫(インシデンタローマ)の診断の手引き
付録7 Knosp分類(下垂体腫瘍の側方進展度)
付録8 成人成長ホルモン(GH)分泌不全症の診断と治療の手引き
付録9 下垂体関連ホルモン基準値
付録10 日本人血中IGF-1濃度基準範囲(「第一」キット)
索引
書評
開く
下垂体腫瘍の基礎から臨床までのすべてが1冊に
書評者: 松谷 雅生 (埼玉医大国際医療センター病院長・脳神経外科学)
長らく渇望していた書がついに発刊された。下垂体腫瘍の診断と治療の第一人者である寺本明教授と,下垂体細胞および下垂体腫瘍(細胞)の病理学と生物学の第一人者である長村義之教授が,わが国の碩学の方々を執筆者に揃えて編んだ本書である。
第1章は視床下部・下垂体の発生である。ヒトにおいては妊娠12-17週の間に視床下部-下垂体の神経内分泌系は活動し始め,そこに至るまでには種々の転写因子やその供役因子である内因性増殖因子などが関与している。まことにヒトの生命誕生は神秘的であり,驚嘆を禁じ得ない。この章に続く下垂体ホルモンの分泌機構の章は,下垂体腫瘍の臨床において極めて重要である。
手術方法の章は豊富なカラー図と極めて理解しやすい模式図とともに,かつて類を見ない手術書となっている。ゴナドトロピン産生腫瘍,TSH産生腺腫,などのまれな腺腫の臨床像にも詳しい。さらに,周辺疾患であるsubclinical Cushing disease, Rathke嚢胞,くも膜嚢胞,リンパ球性下垂体炎,下垂体過形成,などの臨床像にも十分な紙面を割いている。下垂体腫瘍の長期予後の章と腺腫治療の各論を組み合わせると,治療による再発率,治癒率,あるいは二次性腫瘍発生率などがよく理解できる。
さらに,下垂体ホルモン補償療法の章には,治療後の生活指導の重要ポイントがよく整理されている。ヒドロコルチゾン(コートリル®)の投与方法の注意はもとより,プロラクチン産生腫瘍患者が妊娠した場合にドパミン作動薬の投与をどうするか? 治療後ゴナドトロピン分泌不全を呈する女性患者が挙児を希望した場合にどうするか? など詳細に記されている。このように本書には下垂体腫瘍の基礎から臨床まですべてが記されている。英文名の“Pituitary Tumors-Translational Research and Clinical Management”は真に本書の内容を表している。
巻末付録として下垂体腺腫の診断・治療ガイドラインとデータブックがまとめられているのは,臨床現場で苦労している医師への優しい配慮である。本書はまさに下垂体腺腫に関するencyclopediaである。
下垂体腺腫の本質は良性腫瘍であるが,治療後に汎下垂体機能不全症に陥る場合もあれば,逆にホルモン分泌過多が長期間持続することもある。したがってホルモン値を正常域におさめることが腫瘍を制御することと同じく治療の重要ポイントである。プロラクチン産生腫瘍の手術摘出による再発率を差し引いた長期治癒率はmicroadenomaで60%,macroadenomaで25%という数字は,薬物治療との併用という点で興味深い。GH産生腫瘍においては,全体の標準化死亡比は健常人の1.72倍に及ぶが,治療後GHが正常化すれば死亡率は健常人の1.09倍となり,ほぼ差はない。Cushing病においては管理不全が死につながることはよく知られている。非機能腺腫でも再発率に差はあるが,ほぼ10年では50%が再発-再手術を要していて,長期の追跡が必要である。良性腫瘍とはいえ,QOLの高い生活と腫瘍の制御にはすべての面での完全寛解が求められている。まことに奥の深い学問分野である。本書が下垂体腫瘍についてさらに深い知識を得ようとする臨床医と基礎医学者にとって,極めて有益な書であることを確信している。
わが国における下垂体腫瘍の決定版
書評者: 森 昌朋 (群馬大大学院教授・内科学)
脳腫瘍患者ではその占拠性病巣のために,脳細胞障害による種々の脳機能低下が生来する。一方,下垂体腫瘍は脳腫瘍に属するが,下垂体には種々の内分泌ホルモン産生細胞が局在する特徴を有することより,下垂体腫瘍患者では下垂体由来のホルモン過剰分泌による下垂体機能亢進症を呈することが多い。また,逆に非機能性下垂体腫瘍の増大により下垂体に局在するホルモン産生細胞が圧迫障害され,下垂体機能低下症で発見される患者も存在する。
下垂体細胞由来のホルモンとしてプロラクチン(PRL),ACTH,GH,LH,FSH,TSH,Oxytocin,ADHなどが挙げられ,下垂体から分泌されたこれらのホルモンは末梢血中に放出されて,全身に分布する標的臓器に達して生理作用を発揮する。また,これらの下垂体ホルモンは視床下部に存在する視床下部ホルモンによって,合成と分泌が制御されている。下垂体ホルモンのなかで生命維持に必要なホルモンはACTHとTSHであるが,他のホルモンも日常の恒常的機能維持には必須であり,下垂体ホルモン分泌の過剰や低下により種々の症状や臨床所見が生ずる。
また,下垂体機能亢進症を惹起する最も頻度の高い腫瘍はPRL産生腫瘍である。剖検時に下垂体検索を行った報告によると,腫瘍径が1cm未満のmicroadenomaを含めた際のPRL腫瘍の女性での発見率は25%以上の頻度であるという報告がなされており,日常の一般臨床を行う上でも,下垂体疾患は大変身近な存在であると言える。
さらに,わが国において最近,間脳下垂体腫瘍に基づく下垂体機能障害は特定疾患医療給付の対象疾患として認定された。このことは,下垂体疾患に悩む患者さんにとっては朗報であり,診療現場に携わる医師にとっては治療が行いやすくなった利点がある。一方,その反面医師は,下垂体疾患に関するupdateを常に把握して臨床にあたる責任も課せられている。
上記に述べた事柄が背景としてありながら,下垂体腫瘍に関しての,病理から始まる総括的な病態と疾患の臨床的鑑別と治療をupdateに網羅した本はわが国ではこれまでになかった。このたび,日本医科大学・寺本 明先生,東海大学・長村義之先生の編集により上梓された本書は,65項目,472ページ,執筆者85名に上る大著となったが,その記述は下垂体腫瘍の基礎から臨床までを網羅するまさにわが国における下垂体腫瘍の決定版ともいうべきものである。本書は,下垂体疾患の臨床を行う上でも,また下垂体研究に携わる上でも非常に有益な書となることは間違いない。
書評者: 松谷 雅生 (埼玉医大国際医療センター病院長・脳神経外科学)
長らく渇望していた書がついに発刊された。下垂体腫瘍の診断と治療の第一人者である寺本明教授と,下垂体細胞および下垂体腫瘍(細胞)の病理学と生物学の第一人者である長村義之教授が,わが国の碩学の方々を執筆者に揃えて編んだ本書である。
第1章は視床下部・下垂体の発生である。ヒトにおいては妊娠12-17週の間に視床下部-下垂体の神経内分泌系は活動し始め,そこに至るまでには種々の転写因子やその供役因子である内因性増殖因子などが関与している。まことにヒトの生命誕生は神秘的であり,驚嘆を禁じ得ない。この章に続く下垂体ホルモンの分泌機構の章は,下垂体腫瘍の臨床において極めて重要である。
手術方法の章は豊富なカラー図と極めて理解しやすい模式図とともに,かつて類を見ない手術書となっている。ゴナドトロピン産生腫瘍,TSH産生腺腫,などのまれな腺腫の臨床像にも詳しい。さらに,周辺疾患であるsubclinical Cushing disease, Rathke嚢胞,くも膜嚢胞,リンパ球性下垂体炎,下垂体過形成,などの臨床像にも十分な紙面を割いている。下垂体腫瘍の長期予後の章と腺腫治療の各論を組み合わせると,治療による再発率,治癒率,あるいは二次性腫瘍発生率などがよく理解できる。
さらに,下垂体ホルモン補償療法の章には,治療後の生活指導の重要ポイントがよく整理されている。ヒドロコルチゾン(コートリル®)の投与方法の注意はもとより,プロラクチン産生腫瘍患者が妊娠した場合にドパミン作動薬の投与をどうするか? 治療後ゴナドトロピン分泌不全を呈する女性患者が挙児を希望した場合にどうするか? など詳細に記されている。このように本書には下垂体腫瘍の基礎から臨床まですべてが記されている。英文名の“Pituitary Tumors-Translational Research and Clinical Management”は真に本書の内容を表している。
巻末付録として下垂体腺腫の診断・治療ガイドラインとデータブックがまとめられているのは,臨床現場で苦労している医師への優しい配慮である。本書はまさに下垂体腺腫に関するencyclopediaである。
下垂体腺腫の本質は良性腫瘍であるが,治療後に汎下垂体機能不全症に陥る場合もあれば,逆にホルモン分泌過多が長期間持続することもある。したがってホルモン値を正常域におさめることが腫瘍を制御することと同じく治療の重要ポイントである。プロラクチン産生腫瘍の手術摘出による再発率を差し引いた長期治癒率はmicroadenomaで60%,macroadenomaで25%という数字は,薬物治療との併用という点で興味深い。GH産生腫瘍においては,全体の標準化死亡比は健常人の1.72倍に及ぶが,治療後GHが正常化すれば死亡率は健常人の1.09倍となり,ほぼ差はない。Cushing病においては管理不全が死につながることはよく知られている。非機能腺腫でも再発率に差はあるが,ほぼ10年では50%が再発-再手術を要していて,長期の追跡が必要である。良性腫瘍とはいえ,QOLの高い生活と腫瘍の制御にはすべての面での完全寛解が求められている。まことに奥の深い学問分野である。本書が下垂体腫瘍についてさらに深い知識を得ようとする臨床医と基礎医学者にとって,極めて有益な書であることを確信している。
わが国における下垂体腫瘍の決定版
書評者: 森 昌朋 (群馬大大学院教授・内科学)
脳腫瘍患者ではその占拠性病巣のために,脳細胞障害による種々の脳機能低下が生来する。一方,下垂体腫瘍は脳腫瘍に属するが,下垂体には種々の内分泌ホルモン産生細胞が局在する特徴を有することより,下垂体腫瘍患者では下垂体由来のホルモン過剰分泌による下垂体機能亢進症を呈することが多い。また,逆に非機能性下垂体腫瘍の増大により下垂体に局在するホルモン産生細胞が圧迫障害され,下垂体機能低下症で発見される患者も存在する。
下垂体細胞由来のホルモンとしてプロラクチン(PRL),ACTH,GH,LH,FSH,TSH,Oxytocin,ADHなどが挙げられ,下垂体から分泌されたこれらのホルモンは末梢血中に放出されて,全身に分布する標的臓器に達して生理作用を発揮する。また,これらの下垂体ホルモンは視床下部に存在する視床下部ホルモンによって,合成と分泌が制御されている。下垂体ホルモンのなかで生命維持に必要なホルモンはACTHとTSHであるが,他のホルモンも日常の恒常的機能維持には必須であり,下垂体ホルモン分泌の過剰や低下により種々の症状や臨床所見が生ずる。
また,下垂体機能亢進症を惹起する最も頻度の高い腫瘍はPRL産生腫瘍である。剖検時に下垂体検索を行った報告によると,腫瘍径が1cm未満のmicroadenomaを含めた際のPRL腫瘍の女性での発見率は25%以上の頻度であるという報告がなされており,日常の一般臨床を行う上でも,下垂体疾患は大変身近な存在であると言える。
さらに,わが国において最近,間脳下垂体腫瘍に基づく下垂体機能障害は特定疾患医療給付の対象疾患として認定された。このことは,下垂体疾患に悩む患者さんにとっては朗報であり,診療現場に携わる医師にとっては治療が行いやすくなった利点がある。一方,その反面医師は,下垂体疾患に関するupdateを常に把握して臨床にあたる責任も課せられている。
上記に述べた事柄が背景としてありながら,下垂体腫瘍に関しての,病理から始まる総括的な病態と疾患の臨床的鑑別と治療をupdateに網羅した本はわが国ではこれまでになかった。このたび,日本医科大学・寺本 明先生,東海大学・長村義之先生の編集により上梓された本書は,65項目,472ページ,執筆者85名に上る大著となったが,その記述は下垂体腫瘍の基礎から臨床までを網羅するまさにわが国における下垂体腫瘍の決定版ともいうべきものである。本書は,下垂体疾患の臨床を行う上でも,また下垂体研究に携わる上でも非常に有益な書となることは間違いない。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。