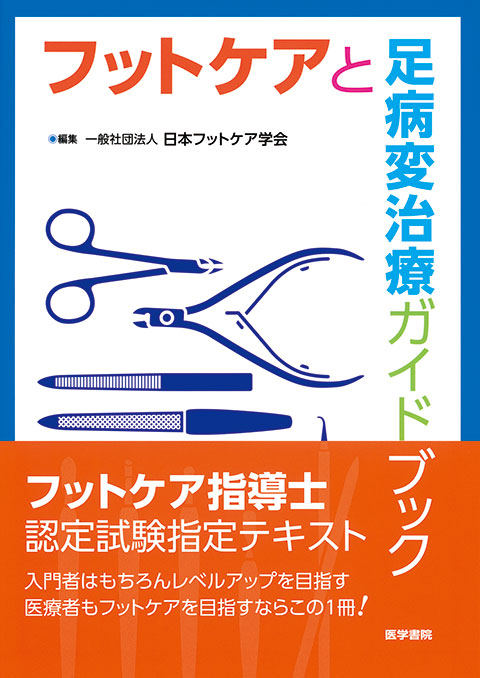糖尿病患者のフットケア
フットケア外来のシステムとケアの実際
看護の新しい分野としてのフットケア
もっと見る
糖尿病患者にとって,足病変はときに下肢切断に至る大きな問題である。足病変の誘因の第1位はくつずれ。くつずれ対策をどうすればよいのか。医師・看護師・くつ専門家との連携で,ここまで予防できるという実例を満載。フットケアのすべてをまとめた。足病変予防を目的としたフットケアは看護の新しい分野として注目を集めるだろう。
| 編集 | 京都大学医学部附属病院看護実践開発センター |
|---|---|
| 発行 | 2004年09月判型:B5頁:140 |
| ISBN | 978-4-260-33361-0 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
I フットケア外来ができるまで
II フットケア外来の体制と業務
III 糖尿病と足病変-足病変はなぜ起きる
IV フットケアに必要な看護アセスメント
V フットケアの基本技術
VI 糖尿病患者の状態に合わせたケア
VII はきもの-くつ・くつ下の選び方
索引
II フットケア外来の体制と業務
III 糖尿病と足病変-足病変はなぜ起きる
IV フットケアに必要な看護アセスメント
V フットケアの基本技術
VI 糖尿病患者の状態に合わせたケア
VII はきもの-くつ・くつ下の選び方
索引
書評
開く
書評 (雑誌『看護教育』より)
書評者: 横井 郁子 (東京都立保健科学大学助教授)
◆たかが爪切り,されど……
実習で一人の学生が「爪切ってもいいんですか?」という質問をしてきた。私の爪がのびているという指摘を受けてのことである。学生は爪切りの‘法的解釈’を確認したかったのである。本書も最初にここを押さえている。私はプロとして認識が甘かった。「しっかり現場と協議しておかなくては」と反省。さあやろう,という段になって,病棟に適切な道具がない。そして受け持ちの高齢患者の足の爪は非常に硬く,厚かった……。
本書の「たかが爪切り,されど……」に示された気づきと実践力には遥かに及ばないが,私にとっても爪切りは気になるテーマとなり,本書はそのテーマに看護職が取り組むことの重要さを示した貴重なものである。
◆糖尿病患者でなくても使える一冊
上記の「爪切り」体験から,個人的に本書を高齢者看護学の講義資料にさせてもらおうと思っている。足の皮膚,循環,知覚といったフィジカルアセスメントからその足に適した靴なのか,それによって生活の活動量は……と,生活のアセスメント,そして具体的な患者指導の実践が手に取るようにわかる。
学生が基礎で習得した「足浴」をより意義深いものにし,改めて看護職の役割も考えさせられるのではないか,といろいろアイデアが湧いてくる。
◆看護管理の実践書
さすが実践者だ,と感心させられたところは数多い。そのひとつであるリスク度のアセスメントは,患者を見つめ続けた成果である。これらが京大病院という制約が多いであろう大病院の看護師が成し遂げていることに,胸がすく思いがした。そして,立ち上げから現在に至るまで苦情がないという事実。患者―医療者関係の原点を見るようである。しかし,勤務時間外も足のことに思い悩むことが多かったであろうことは容易に想像できる。フットケア外来の立ち上げと定着の軌跡,「足病変での緊急入院をゼロ」,「8割の患者の足の除痛を図る」実践の記録でもある本書は,管理を学ぶ実践書としても有用である。
(『看護教育』2005年2月号掲載)
患者の側に立つことで生まれた明るく輝く看護実践の成果 (雑誌『訪問看護と介護』より)
書評者: 細野 容子 (岐阜大学医学部看護学科教授)
「手が届かないから,足の爪を切ってほしい」と高齢の糖尿病患者に頼まれ,その患者が来院するたびに爪を切り,患者の話を聞くうちに,フットケアの重要性に気づいた1人の看護師がいた。
そして彼女たちはフットケア外来を立ち上げ,足浴やマッサージを続け,その効果を足背動脈血流ドプラーで測定し,自宅でも患者が足浴を続けられるような支援を始めた。フットケア外来の開設時には,事務や医局を巻き込んで,フットケアの必要を認めさせたという。
そのうちに,靴ずれが足病変の原因の第1位だと知り,足に合った靴を探して苦労した末に,靴の専門家を見つけ適切な靴を作るよう交渉した。また,旅行にはお金を使っても,靴にはお金を使おうとしない患者が,結婚式に履く靴のことを看護師に相談したときを捉え,看護師は靴のオーダーを勧めた。その後,その患者は履き心地のよさから旅行用としてさらに2足注文したという。
本書は,このように患者あっての医療であることを意識し,糖尿病足病変の予防と進行防止のための患者支援システムを作り上げ,実効があることを証明した,看護師チームの活動の成果である。
たとえば,靴との関係で見るならば,「糖尿病と履き物」(重要な靴ずれ対策,靴適正度の査定,患者の意向別分類,靴選択後のズレも問題)という解説を経て,「室内履き・靴下選び」そして「手持ち靴の補正」「日常の注意と手入れ法」,全国の「足の悩みを相談できる靴専門家・靴店の住所,電話番号」なども紹介されている。
看護は実践である。本書によって,実践家だけが会得できる看護を見せてもらったように思う。
私たちの大学では現在実習の最中だが,足浴を提案して実施したことで患者に喜んでもらえたと誇らしく語る学生がいる。その一方で,そうした看護ができない理由として,診療補助行為の忙しさに逃げている看護師がいることを,私は悲しく思う。清拭や洗髪など,看護の基本的な技術が,患者を清潔にするだけでなく,患者との信頼関係を築くきっかけにもなることを,すべての看護師に知ってほしいと思う。
かつて精神科病院でボランティアをしたとき,素敵な香りのする石鹸で足浴をした患者さんの笑顔や,素足で芝生を踏み,感嘆の声を上げた患者さんの様子が思い出される。しかし当時,私ができたのは足浴が精一杯だった。本書の「ケアの実際」の項に書かれているような観察のポイント,アセスメントの方法などの知識があったならば,看護介入も違ったものになっていたと思う。
患者の側に立つと,看護師がやらなければならないことがたくさん見えてくる。外来看護が期待されている今,著者らのように患者の一言から看護の役割を認識し,他部門との学際的な交流や医療経済への関与までを考えることの必要性に気づかされる。この「看護の社会化」が,看護の質を向上させ,支援システムを作り上げるのだと思う。
本書によって,明るく輝く看護を紹介してもらった。看護職を引退後に京都で過ごすことになる私には,大きな希望と感謝の念でいっぱいである。
最後に,本書はフットケアについて,病院の看護師ばかりでなく,訪問看護師や患者にも使える指導書であることをつけ加えたい。
(『訪問看護と介護』2005年1月号掲載)
患者さんの全体像を看る,1つの手段としてのフットケア (雑誌『精神看護』より)
書評者: 相原 友直 (東京武蔵野病院・看護師)
私たち看護師は普段から忙しい業務などで病棟を駆けずり回っていますよね。だけど,足に合わない靴を選んでいませんか? クッションが悪くて滑りやすくて,内反足や踵などが硬くなっていたりしませんか? 私自身靴にはちょっとうるさいほうで,業務でこれだけ足を使っているのに支給される靴でいいのか,なんて思ったものですから,結構気にして活動性に合いそうな靴を自分で選んでいます。
本書には,京都大学医学部附属病院で開設された「フットケア外来」の活動が紹介されています。私はまず,フットケアの部分で看護の専門性を発揮しようという観点を賞賛したいと思いました。大学病院という,すでに診療科なども細分化された専門性の高い病院の中で,さらなる専門性を発揮していこうとする努力はすごい。本書には,フットケアの存在や重要性を認めてもらうまでの経緯や,単独で外来を開設するまでの苦労がさらりと書かれているのですが,私には伝わってきました。さぞや大変なことであったろうと。
私自身,本書に出会うまで,患者さんがどれだけフットケアに関してニーズをもっているのかといったことや,どれだけ神経障害で知覚が麻痺しているのかについては考えたことがありませんでした。私は病棟勤務の経験しかないのですが,精神科身体合併症病棟で,実際に足病変を患った患者さんを何人か受け持ったことがあります。その際,足浴をまめにしたり,靴を大きめにして圧迫を避けるなどの工夫はしていましたが,末梢循環の悪さは感じていながら,知覚を厳密に調べたり指導したりはしていませんでした。認知の障害が大きい患者さんのことを,もっと考える必要があったと後悔します。
そして現在,精神科慢性期開放病棟に異動してからも,患者さんをみているといくつか考えさせられることがあります。ある患者さんが「足が痛い」と訴えてくるので靴を脱ぐよう促したのですが,なかなか脱がないのです。やっとのことで靴は脱いだのですが,靴下に血と浸出液がにじんでいるではありませんか。大変だと思い靴下も脱ぐように促したのですが,これまたなかなか脱がないのです。困り果てているうちに何とか脱いでくれたのですが,何と爪が大変なことになっていました。どれだけの年月伸ばしていたのかわからないほど爪が伸び,先端が巻き込んで足の裏側のほうまで達していました。それが歩いたりするうち幾度となく肉に食い込み,切れて創傷になっていたのでした。退院を目指す入院生活として目先のケアにばかりとらわれて,患者さんの全体像をとらえてみることができていなかったことが悔やまれます。
今回書評を書くにあたって本書を読んでみて,患者さんのケアに対してもう一歩踏み込んでみようと,気持ちが改められた思いです。とにかく患者さんが体験している感覚を,看護者が感じとる必要があります。一部の症状をみるのではなく,患者さん自身をみる,全体像をみる。その方法の1つにフットケアという手段はあると思います。精神科でどう活用するかは考える必要があると思いますが,この技術と専門性は,糖尿病を患った患者さんに対してだけでなく,広く一般的な看護においても必要なものだと感じました。
フットケアに取り組むには,まずは私たち看護師が足の健康に興味をもつことが大切です。本書に触発された私は,一度シューフィッターにみてもらおうかな,という気にさえなっているのでした。
(『精神看護』2005年3月号掲載)
フットケアをはじめてみませんか? (雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 和田 幹子 (日看協)
現在,「糖尿病を強く疑われている人」のうち,約1.6%の方が壊疽を合併しているといわれています。また,糖尿病患者さんの60~70%が,軽度から重度の神経障害をもっているといわれています。妊娠時の検査で初めて糖尿病と診断された方は,比較的発症後間もない若い方が多いかもしれません。しかし,糖尿病の足病変に直結する神経障害は糖尿病と診断されたころから徐々に進行が始まっています。初期のうちに動機づけができれば,将来,壊疽を予防することもできます。
本書は周産期にある方にフットケアをはじめたいと考えている助産師・看護師や,糖尿病の妊婦さんや患者さんに生活の指導をする機会が多い医療者にぜひ参考にしてほしいフットケアの実践書です。
糖尿病の妊婦さんの生活指導を行なうとき,血糖のこと,食事のこと,運動のこと……で終わっていることが間々あると思います。「血糖,食事,運動だけでも大変なボリュームになるし,実はそれ以外のことはあまり知らない……」という方も多いのではないでしょうか。目の前の糖尿病妊婦さんの足の先までは見たことがない医療スタッフも決して少なくないのではないかと思います。
妊娠後期で足の手入れが難しかったり,切迫早産などで長期に入院されている妊産褥婦さんの足を,一度足先までしっかり観察してみませんか? 本書は,ポイントを絞った足病変の観察から,べんち・鶏眼の削り方まで,ケアの1つひとつに丁寧な解説を交えたマニュアル形式でフットケア初心者を導いてくれます。
足病変の誘因は「くつずれ」が断然トップであり,全体のおよそ7割を占めているそうです(本書50頁より)。これらの誘因を取り除かなければ,足病変に移行する確率は高くなります。執筆者の1人である阿部邦子氏(京都大学医学部附属病院・師長)は,実際に健康くつを履き,靴調整士やシューフィッターに会い,適正なくつ選びのために実践した多くのことを惜しみなく著してくれています。本書を読むことで,くつの観察ポイントとくつ選びの要点に気づくことができます。フットケアのことをあまりよく知らないという方でも安心してください。足病変の発生機序や予防・治療についても大変わかりやすくまとめられ,実際に活用されているケア経過表や評価表,診療報酬の算定方法の掲載もあります。‘まさにすぐにでも使える’実践者のためのテキストです。
臨床の場では,不思議とフットケアの際に患者さんが悩みをうちあけてくれることが多く,日常生活や療養上で困っていることに気づく機会も多いように思います。本書にも「たかが爪切りと思っていたが,Tさんに喜んでもらい,心の交流にもなるこの時間を大切にしよう」(本書10頁より)とあり,フットケアの時間を大切にしている執筆者の思いが伝わってきます。患者さんの足を大切に思いケアをすることは,患者さん自身を大切にすることにつながり,心の交流が生まれ,患者さんの本音に触れることができるのではないでしょうか。
第一線で周産期の妊産褥婦さんや糖尿病の患者さんの指導に携わっている方にこそ,ぜひ参考にしていただきたい一冊です。
(『助産雑誌』2005年3月号掲載)
現場を変えるナースの軌跡とその成果
書評者: 安酸 史子 (福岡県立大看護学部長・成人看護学)
看護師の,看護師による,看護師のための待望のフットケアの本が出版された。
本書は,「今まで我々は,経験と勘を頼りに足のリスク分類をしてきた。しかし,経験のない新人でも,迷わずにリスク分類できる方法はないだろうかとずっと考えてきた。」と,フットケアのベテランの技を可能な限りモデル化し,新人でも活用できる実用書に仕上げてある。本書は以下の7つの部門で構成されている。
「I フットケア外来ができるまで」「II フットケア外来の体制と業務」「III 糖尿病と足病変」「IV フットケアに必要な看護アセスメント」「V フットケアの基本技術」「VI 糖尿病患者の状態に合わせたケア」「VII はきもの―くつ・くつ下の選び方」である。
今後,自分の病院でフットケア外来を立ち上げたいと考えている看護師にとっては,I部とII部は具体的で現実的なロールモデルの紹介だと思う。「まずは現在いる看護師で,やれることから始めることが大切である」と力むことなく,医師を始め周りの専門家を徐々に巻き込みながら,体制作りをしていく様は見事である。足病変の発生機序や治療法を勉強したい人は,III部を読むとよい。具体的なフットケアの実際をまず知りたい人は,V部から読みはじめるとよい。写真やイラストを多用し,看護師の視点での具体的なフットケアについての知識や技術が満載され,さらに靴選びに関して専門家・靴店まで紹介してある。
秀逸なのは,IV部のアセスメントの方法である。『どんなに丁寧なケアができていても,ハイリスク患者を「ハイリスク」と認知できていないことほどリスキーなことはない』と述べ,最大危険因子である神経障害を軸に,独自のリスク度アセスメント基本図を考案している。検証例は少ないとしているが,具体例を示しながらアセスメントの実際を解説しているので,フットのアセスメントを行う際の頼りになるガイドといえる。ただし,このリスク度アセスメント基本図に関しては,フローチャートとしてはもう少しすっきりできたらと欲張りな感想を持った。今後検証を続け修正もしたいと考えているとあるので期待したい。
書評者: 横井 郁子 (東京都立保健科学大学助教授)
◆たかが爪切り,されど……
実習で一人の学生が「爪切ってもいいんですか?」という質問をしてきた。私の爪がのびているという指摘を受けてのことである。学生は爪切りの‘法的解釈’を確認したかったのである。本書も最初にここを押さえている。私はプロとして認識が甘かった。「しっかり現場と協議しておかなくては」と反省。さあやろう,という段になって,病棟に適切な道具がない。そして受け持ちの高齢患者の足の爪は非常に硬く,厚かった……。
本書の「たかが爪切り,されど……」に示された気づきと実践力には遥かに及ばないが,私にとっても爪切りは気になるテーマとなり,本書はそのテーマに看護職が取り組むことの重要さを示した貴重なものである。
◆糖尿病患者でなくても使える一冊
上記の「爪切り」体験から,個人的に本書を高齢者看護学の講義資料にさせてもらおうと思っている。足の皮膚,循環,知覚といったフィジカルアセスメントからその足に適した靴なのか,それによって生活の活動量は……と,生活のアセスメント,そして具体的な患者指導の実践が手に取るようにわかる。
学生が基礎で習得した「足浴」をより意義深いものにし,改めて看護職の役割も考えさせられるのではないか,といろいろアイデアが湧いてくる。
◆看護管理の実践書
さすが実践者だ,と感心させられたところは数多い。そのひとつであるリスク度のアセスメントは,患者を見つめ続けた成果である。これらが京大病院という制約が多いであろう大病院の看護師が成し遂げていることに,胸がすく思いがした。そして,立ち上げから現在に至るまで苦情がないという事実。患者―医療者関係の原点を見るようである。しかし,勤務時間外も足のことに思い悩むことが多かったであろうことは容易に想像できる。フットケア外来の立ち上げと定着の軌跡,「足病変での緊急入院をゼロ」,「8割の患者の足の除痛を図る」実践の記録でもある本書は,管理を学ぶ実践書としても有用である。
(『看護教育』2005年2月号掲載)
患者の側に立つことで生まれた明るく輝く看護実践の成果 (雑誌『訪問看護と介護』より)
書評者: 細野 容子 (岐阜大学医学部看護学科教授)
「手が届かないから,足の爪を切ってほしい」と高齢の糖尿病患者に頼まれ,その患者が来院するたびに爪を切り,患者の話を聞くうちに,フットケアの重要性に気づいた1人の看護師がいた。
そして彼女たちはフットケア外来を立ち上げ,足浴やマッサージを続け,その効果を足背動脈血流ドプラーで測定し,自宅でも患者が足浴を続けられるような支援を始めた。フットケア外来の開設時には,事務や医局を巻き込んで,フットケアの必要を認めさせたという。
そのうちに,靴ずれが足病変の原因の第1位だと知り,足に合った靴を探して苦労した末に,靴の専門家を見つけ適切な靴を作るよう交渉した。また,旅行にはお金を使っても,靴にはお金を使おうとしない患者が,結婚式に履く靴のことを看護師に相談したときを捉え,看護師は靴のオーダーを勧めた。その後,その患者は履き心地のよさから旅行用としてさらに2足注文したという。
本書は,このように患者あっての医療であることを意識し,糖尿病足病変の予防と進行防止のための患者支援システムを作り上げ,実効があることを証明した,看護師チームの活動の成果である。
たとえば,靴との関係で見るならば,「糖尿病と履き物」(重要な靴ずれ対策,靴適正度の査定,患者の意向別分類,靴選択後のズレも問題)という解説を経て,「室内履き・靴下選び」そして「手持ち靴の補正」「日常の注意と手入れ法」,全国の「足の悩みを相談できる靴専門家・靴店の住所,電話番号」なども紹介されている。
看護は実践である。本書によって,実践家だけが会得できる看護を見せてもらったように思う。
私たちの大学では現在実習の最中だが,足浴を提案して実施したことで患者に喜んでもらえたと誇らしく語る学生がいる。その一方で,そうした看護ができない理由として,診療補助行為の忙しさに逃げている看護師がいることを,私は悲しく思う。清拭や洗髪など,看護の基本的な技術が,患者を清潔にするだけでなく,患者との信頼関係を築くきっかけにもなることを,すべての看護師に知ってほしいと思う。
かつて精神科病院でボランティアをしたとき,素敵な香りのする石鹸で足浴をした患者さんの笑顔や,素足で芝生を踏み,感嘆の声を上げた患者さんの様子が思い出される。しかし当時,私ができたのは足浴が精一杯だった。本書の「ケアの実際」の項に書かれているような観察のポイント,アセスメントの方法などの知識があったならば,看護介入も違ったものになっていたと思う。
患者の側に立つと,看護師がやらなければならないことがたくさん見えてくる。外来看護が期待されている今,著者らのように患者の一言から看護の役割を認識し,他部門との学際的な交流や医療経済への関与までを考えることの必要性に気づかされる。この「看護の社会化」が,看護の質を向上させ,支援システムを作り上げるのだと思う。
本書によって,明るく輝く看護を紹介してもらった。看護職を引退後に京都で過ごすことになる私には,大きな希望と感謝の念でいっぱいである。
最後に,本書はフットケアについて,病院の看護師ばかりでなく,訪問看護師や患者にも使える指導書であることをつけ加えたい。
(『訪問看護と介護』2005年1月号掲載)
患者さんの全体像を看る,1つの手段としてのフットケア (雑誌『精神看護』より)
書評者: 相原 友直 (東京武蔵野病院・看護師)
私たち看護師は普段から忙しい業務などで病棟を駆けずり回っていますよね。だけど,足に合わない靴を選んでいませんか? クッションが悪くて滑りやすくて,内反足や踵などが硬くなっていたりしませんか? 私自身靴にはちょっとうるさいほうで,業務でこれだけ足を使っているのに支給される靴でいいのか,なんて思ったものですから,結構気にして活動性に合いそうな靴を自分で選んでいます。
本書には,京都大学医学部附属病院で開設された「フットケア外来」の活動が紹介されています。私はまず,フットケアの部分で看護の専門性を発揮しようという観点を賞賛したいと思いました。大学病院という,すでに診療科なども細分化された専門性の高い病院の中で,さらなる専門性を発揮していこうとする努力はすごい。本書には,フットケアの存在や重要性を認めてもらうまでの経緯や,単独で外来を開設するまでの苦労がさらりと書かれているのですが,私には伝わってきました。さぞや大変なことであったろうと。
私自身,本書に出会うまで,患者さんがどれだけフットケアに関してニーズをもっているのかといったことや,どれだけ神経障害で知覚が麻痺しているのかについては考えたことがありませんでした。私は病棟勤務の経験しかないのですが,精神科身体合併症病棟で,実際に足病変を患った患者さんを何人か受け持ったことがあります。その際,足浴をまめにしたり,靴を大きめにして圧迫を避けるなどの工夫はしていましたが,末梢循環の悪さは感じていながら,知覚を厳密に調べたり指導したりはしていませんでした。認知の障害が大きい患者さんのことを,もっと考える必要があったと後悔します。
そして現在,精神科慢性期開放病棟に異動してからも,患者さんをみているといくつか考えさせられることがあります。ある患者さんが「足が痛い」と訴えてくるので靴を脱ぐよう促したのですが,なかなか脱がないのです。やっとのことで靴は脱いだのですが,靴下に血と浸出液がにじんでいるではありませんか。大変だと思い靴下も脱ぐように促したのですが,これまたなかなか脱がないのです。困り果てているうちに何とか脱いでくれたのですが,何と爪が大変なことになっていました。どれだけの年月伸ばしていたのかわからないほど爪が伸び,先端が巻き込んで足の裏側のほうまで達していました。それが歩いたりするうち幾度となく肉に食い込み,切れて創傷になっていたのでした。退院を目指す入院生活として目先のケアにばかりとらわれて,患者さんの全体像をとらえてみることができていなかったことが悔やまれます。
今回書評を書くにあたって本書を読んでみて,患者さんのケアに対してもう一歩踏み込んでみようと,気持ちが改められた思いです。とにかく患者さんが体験している感覚を,看護者が感じとる必要があります。一部の症状をみるのではなく,患者さん自身をみる,全体像をみる。その方法の1つにフットケアという手段はあると思います。精神科でどう活用するかは考える必要があると思いますが,この技術と専門性は,糖尿病を患った患者さんに対してだけでなく,広く一般的な看護においても必要なものだと感じました。
フットケアに取り組むには,まずは私たち看護師が足の健康に興味をもつことが大切です。本書に触発された私は,一度シューフィッターにみてもらおうかな,という気にさえなっているのでした。
(『精神看護』2005年3月号掲載)
フットケアをはじめてみませんか? (雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 和田 幹子 (日看協)
現在,「糖尿病を強く疑われている人」のうち,約1.6%の方が壊疽を合併しているといわれています。また,糖尿病患者さんの60~70%が,軽度から重度の神経障害をもっているといわれています。妊娠時の検査で初めて糖尿病と診断された方は,比較的発症後間もない若い方が多いかもしれません。しかし,糖尿病の足病変に直結する神経障害は糖尿病と診断されたころから徐々に進行が始まっています。初期のうちに動機づけができれば,将来,壊疽を予防することもできます。
本書は周産期にある方にフットケアをはじめたいと考えている助産師・看護師や,糖尿病の妊婦さんや患者さんに生活の指導をする機会が多い医療者にぜひ参考にしてほしいフットケアの実践書です。
糖尿病の妊婦さんの生活指導を行なうとき,血糖のこと,食事のこと,運動のこと……で終わっていることが間々あると思います。「血糖,食事,運動だけでも大変なボリュームになるし,実はそれ以外のことはあまり知らない……」という方も多いのではないでしょうか。目の前の糖尿病妊婦さんの足の先までは見たことがない医療スタッフも決して少なくないのではないかと思います。
妊娠後期で足の手入れが難しかったり,切迫早産などで長期に入院されている妊産褥婦さんの足を,一度足先までしっかり観察してみませんか? 本書は,ポイントを絞った足病変の観察から,べんち・鶏眼の削り方まで,ケアの1つひとつに丁寧な解説を交えたマニュアル形式でフットケア初心者を導いてくれます。
足病変の誘因は「くつずれ」が断然トップであり,全体のおよそ7割を占めているそうです(本書50頁より)。これらの誘因を取り除かなければ,足病変に移行する確率は高くなります。執筆者の1人である阿部邦子氏(京都大学医学部附属病院・師長)は,実際に健康くつを履き,靴調整士やシューフィッターに会い,適正なくつ選びのために実践した多くのことを惜しみなく著してくれています。本書を読むことで,くつの観察ポイントとくつ選びの要点に気づくことができます。フットケアのことをあまりよく知らないという方でも安心してください。足病変の発生機序や予防・治療についても大変わかりやすくまとめられ,実際に活用されているケア経過表や評価表,診療報酬の算定方法の掲載もあります。‘まさにすぐにでも使える’実践者のためのテキストです。
臨床の場では,不思議とフットケアの際に患者さんが悩みをうちあけてくれることが多く,日常生活や療養上で困っていることに気づく機会も多いように思います。本書にも「たかが爪切りと思っていたが,Tさんに喜んでもらい,心の交流にもなるこの時間を大切にしよう」(本書10頁より)とあり,フットケアの時間を大切にしている執筆者の思いが伝わってきます。患者さんの足を大切に思いケアをすることは,患者さん自身を大切にすることにつながり,心の交流が生まれ,患者さんの本音に触れることができるのではないでしょうか。
第一線で周産期の妊産褥婦さんや糖尿病の患者さんの指導に携わっている方にこそ,ぜひ参考にしていただきたい一冊です。
(『助産雑誌』2005年3月号掲載)
現場を変えるナースの軌跡とその成果
書評者: 安酸 史子 (福岡県立大看護学部長・成人看護学)
看護師の,看護師による,看護師のための待望のフットケアの本が出版された。
本書は,「今まで我々は,経験と勘を頼りに足のリスク分類をしてきた。しかし,経験のない新人でも,迷わずにリスク分類できる方法はないだろうかとずっと考えてきた。」と,フットケアのベテランの技を可能な限りモデル化し,新人でも活用できる実用書に仕上げてある。本書は以下の7つの部門で構成されている。
「I フットケア外来ができるまで」「II フットケア外来の体制と業務」「III 糖尿病と足病変」「IV フットケアに必要な看護アセスメント」「V フットケアの基本技術」「VI 糖尿病患者の状態に合わせたケア」「VII はきもの―くつ・くつ下の選び方」である。
今後,自分の病院でフットケア外来を立ち上げたいと考えている看護師にとっては,I部とII部は具体的で現実的なロールモデルの紹介だと思う。「まずは現在いる看護師で,やれることから始めることが大切である」と力むことなく,医師を始め周りの専門家を徐々に巻き込みながら,体制作りをしていく様は見事である。足病変の発生機序や治療法を勉強したい人は,III部を読むとよい。具体的なフットケアの実際をまず知りたい人は,V部から読みはじめるとよい。写真やイラストを多用し,看護師の視点での具体的なフットケアについての知識や技術が満載され,さらに靴選びに関して専門家・靴店まで紹介してある。
秀逸なのは,IV部のアセスメントの方法である。『どんなに丁寧なケアができていても,ハイリスク患者を「ハイリスク」と認知できていないことほどリスキーなことはない』と述べ,最大危険因子である神経障害を軸に,独自のリスク度アセスメント基本図を考案している。検証例は少ないとしているが,具体例を示しながらアセスメントの実際を解説しているので,フットのアセスメントを行う際の頼りになるガイドといえる。ただし,このリスク度アセスメント基本図に関しては,フローチャートとしてはもう少しすっきりできたらと欲張りな感想を持った。今後検証を続け修正もしたいと考えているとあるので期待したい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。