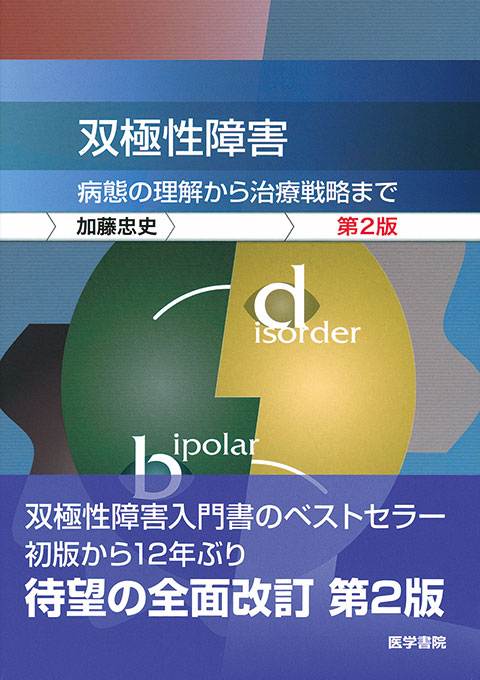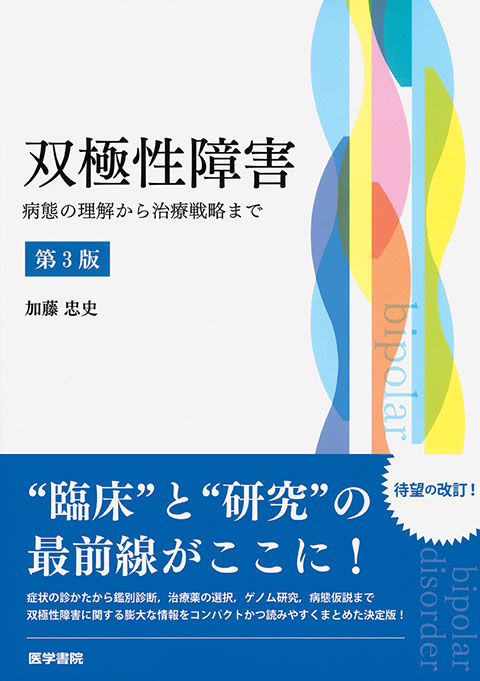双極性障害 第2版
病態の理解から治療戦略まで
双極性障害入門書のベストセラー、全面改訂第2版
もっと見る
近年大きな注目を集める双極性障害(躁うつ病)の決定版入門書、待望の改訂版。概念、症状、診断、治療薬の薬理、生物学的研究まで網羅し、この1冊で双極性障害の全体像がつかめる、ミニエンサイクロペディア的な内容構成。最近のトピックスも満載、診療・研究の最前線が分かる。著者の豊富な臨床経験をベースに、最新のエビデンスに裏打ちされた治療戦略を提示。明日からの臨床にすぐ役立つ実践的な知識・情報を随所に掲載。
| 著 | 加藤 忠史 |
|---|---|
| 発行 | 2011年05月判型:A5頁:352 |
| ISBN | 978-4-260-01329-1 |
| 定価 | 5,170円 (本体4,700円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第2版の序
本書初版を執筆した1999年から12年余の間に,双極性障害を取り巻く環境は,あまりにも大きく変わってしまった.
当時は,「双極性障害」という書名に違和感があるといわれたが,現在では,むしろ初版の副題に入れていた「躁うつ病」の方に違和感があるほどである.
病相はそのたびに治るといっても,反復するうつ状態や躁状態における逸脱行動などから,大きな社会生活の障害を引き起こすこと,そのため,治療においては何より予防療法が重要であることなど,双極性障害への認識も,以前に比べればかなり浸透してきた.
双極性障害の専門書,一般書も,うつ病ほどではないにしても,多く出版されるようになり,患者さんも,気軽に病気について学ぶことができるようになった.患者さんの間でも,病名の呼称は躁うつ病から双極性障害へと,シフトしつつある.
さらに,双極性障害の治療薬も,バルプロ酸の適応病名として正式に「躁うつ病」が加わったのを皮切りに,2010年10月にはオランザピンも「双極性障害の躁症状の改善」に対して適応が拡大された.その他にも,双極性障害に対する有効性のエビデンスが確立した薬剤として,ラモトリギン,クエチアピン,アリピプラゾールなどが期待されている.
病態研究においても,ゲノムワイド関連研究やモデルマウスなど,様々な進歩があった.
一方,双極II型障害概念が浸透するにつれて,その輪郭が次第に変遷を遂げ,その多彩な臨床像,境界性パーソナリティとの異同,診断・治療の困難さなど,双極II型障害診療の難しさもクローズアップされてきた.
そして,双極II型障害の診断基準すら満たさない,双極スペクトラムの概念がよく知られるようになり,双極性障害の概念はますます拡大した.そして,うつ病患者の中に潜在的な双極性障害患者が含まれていて,こうした患者では抗うつ薬で悪化するのではないかという問題意識が,臨床上の大きな課題となりつつある.
一方,主として特定不能の双極性障害と診断される,子どもの双極性障害がアメリカを中心に急増した.こうした新たな病気の出現の背景に,製薬会社と精神科医の癒着が疑われる一方,宗教団体による反精神医学的活動が行われるなど,社会状況に疾患概念が翻弄される事態となっている.
初版を出して数年で,改訂の必要性を感じ始めたが,いよいよ改訂となったときには,もはや少しの改訂では追いつかず,内容の完全な刷新が必要となっていた.
そんなわけで,本書の改訂ができないままに10年以上が過ぎてしまい,これだけ多くの双極性障害に関する書物が出版されている現在,もはや本書の役割は終えたか,と思ったときもあった.
今や,単著で書かれた双極性障害の教科書は,ほとんど見当たらない.膨大な文献が世にあふれる時代,すべてを総説することはもはや不可能ということかもしれない.
実は,医学書院の編集担当者からは,内容を大幅に増やす方向で改訂してはどうか,との話も頂いた.確かに,すべての文献を渉猟してまとめていく,という方向性も考えられよう.しかし,Goodwin & Jamisonの教科書「Manic Depressive Illness」の初版や,1983年の渡辺昌祐博士の大著「リチウム」を前にしただけでもひるんでしまうのに,2000年以降に出版された双極性障害に関する文献は,12,000本を超えており,これらの文献をすべて読んで総説することは,もはや不可能と言わざるを得ない.
このように,情報があふれる一方,ほとんどの情報が検索可能となりつつある現代において,情報を集積して羅列するだけでは,もはや意義はないかもしれない.一方,あふれる断片的な情報を読み解き,一つの流れとして把握し,こうした知識を臨床実践に利用可能な知恵として昇華させていくことの必要性は,以前にもまして高まっている.
本書がそのような意義をもつ書物となり得るかどうかは甚だ不安ではあるが,情報過多の現代こそ,個人の見解を述べる本書のような書物に,それなりの意義はあるかもしれないと思い直し,何とか改訂を進めることにした次第である.
このように本書は,膨大な文献の情報をすべて盛り込むことを目指すよりも,筆者が理解している範囲の内容を軸に,なるべくコンパクトにまとめたため,双極性障害のすべてを網羅できているわけではない.しかし,双極性障害の概観をつかむためには,むしろその方が理解しやすいかもしれないと考えている.
そんなわけで,本書は双極性障害理解の入り口でしかない.読者には,本書を入り口として,各自の臨床経験や研究経験の中から,それぞれの双極性障害像を育んで頂ければと思う.
本書初版の出版以来12年の間のあまりにも大きな変化を思うと,今後10年,20年の間に,双極性障害に何が起きるかは,全く予想できない.筆者としては,双極性障害患者の朗報となるような研究成果を挙げられるよう,精進したいと思いつつ,願わくは,若き読者の中から,双極性障害研究の歴史を変えるような知見を発表する医師,研究者が次々と生まれて欲しいと期待している.
2011年4月
加藤忠史
本書初版を執筆した1999年から12年余の間に,双極性障害を取り巻く環境は,あまりにも大きく変わってしまった.
当時は,「双極性障害」という書名に違和感があるといわれたが,現在では,むしろ初版の副題に入れていた「躁うつ病」の方に違和感があるほどである.
病相はそのたびに治るといっても,反復するうつ状態や躁状態における逸脱行動などから,大きな社会生活の障害を引き起こすこと,そのため,治療においては何より予防療法が重要であることなど,双極性障害への認識も,以前に比べればかなり浸透してきた.
双極性障害の専門書,一般書も,うつ病ほどではないにしても,多く出版されるようになり,患者さんも,気軽に病気について学ぶことができるようになった.患者さんの間でも,病名の呼称は躁うつ病から双極性障害へと,シフトしつつある.
さらに,双極性障害の治療薬も,バルプロ酸の適応病名として正式に「躁うつ病」が加わったのを皮切りに,2010年10月にはオランザピンも「双極性障害の躁症状の改善」に対して適応が拡大された.その他にも,双極性障害に対する有効性のエビデンスが確立した薬剤として,ラモトリギン,クエチアピン,アリピプラゾールなどが期待されている.
病態研究においても,ゲノムワイド関連研究やモデルマウスなど,様々な進歩があった.
一方,双極II型障害概念が浸透するにつれて,その輪郭が次第に変遷を遂げ,その多彩な臨床像,境界性パーソナリティとの異同,診断・治療の困難さなど,双極II型障害診療の難しさもクローズアップされてきた.
そして,双極II型障害の診断基準すら満たさない,双極スペクトラムの概念がよく知られるようになり,双極性障害の概念はますます拡大した.そして,うつ病患者の中に潜在的な双極性障害患者が含まれていて,こうした患者では抗うつ薬で悪化するのではないかという問題意識が,臨床上の大きな課題となりつつある.
一方,主として特定不能の双極性障害と診断される,子どもの双極性障害がアメリカを中心に急増した.こうした新たな病気の出現の背景に,製薬会社と精神科医の癒着が疑われる一方,宗教団体による反精神医学的活動が行われるなど,社会状況に疾患概念が翻弄される事態となっている.
初版を出して数年で,改訂の必要性を感じ始めたが,いよいよ改訂となったときには,もはや少しの改訂では追いつかず,内容の完全な刷新が必要となっていた.
そんなわけで,本書の改訂ができないままに10年以上が過ぎてしまい,これだけ多くの双極性障害に関する書物が出版されている現在,もはや本書の役割は終えたか,と思ったときもあった.
今や,単著で書かれた双極性障害の教科書は,ほとんど見当たらない.膨大な文献が世にあふれる時代,すべてを総説することはもはや不可能ということかもしれない.
実は,医学書院の編集担当者からは,内容を大幅に増やす方向で改訂してはどうか,との話も頂いた.確かに,すべての文献を渉猟してまとめていく,という方向性も考えられよう.しかし,Goodwin & Jamisonの教科書「Manic Depressive Illness」の初版や,1983年の渡辺昌祐博士の大著「リチウム」を前にしただけでもひるんでしまうのに,2000年以降に出版された双極性障害に関する文献は,12,000本を超えており,これらの文献をすべて読んで総説することは,もはや不可能と言わざるを得ない.
このように,情報があふれる一方,ほとんどの情報が検索可能となりつつある現代において,情報を集積して羅列するだけでは,もはや意義はないかもしれない.一方,あふれる断片的な情報を読み解き,一つの流れとして把握し,こうした知識を臨床実践に利用可能な知恵として昇華させていくことの必要性は,以前にもまして高まっている.
本書がそのような意義をもつ書物となり得るかどうかは甚だ不安ではあるが,情報過多の現代こそ,個人の見解を述べる本書のような書物に,それなりの意義はあるかもしれないと思い直し,何とか改訂を進めることにした次第である.
このように本書は,膨大な文献の情報をすべて盛り込むことを目指すよりも,筆者が理解している範囲の内容を軸に,なるべくコンパクトにまとめたため,双極性障害のすべてを網羅できているわけではない.しかし,双極性障害の概観をつかむためには,むしろその方が理解しやすいかもしれないと考えている.
そんなわけで,本書は双極性障害理解の入り口でしかない.読者には,本書を入り口として,各自の臨床経験や研究経験の中から,それぞれの双極性障害像を育んで頂ければと思う.
本書初版の出版以来12年の間のあまりにも大きな変化を思うと,今後10年,20年の間に,双極性障害に何が起きるかは,全く予想できない.筆者としては,双極性障害患者の朗報となるような研究成果を挙げられるよう,精進したいと思いつつ,願わくは,若き読者の中から,双極性障害研究の歴史を変えるような知見を発表する医師,研究者が次々と生まれて欲しいと期待している.
2011年4月
加藤忠史
目次
開く
第1章 概念の歴史
A.症状の記載
B.疾患としての記載
C.反精神医学
D.非定型精神病概念の流れ
E.DSM-III
F.双極II型障害の登場
G.双極スペクトラム概念の登場
H.DSM-IV
I.特定不能の双極性障害
J.双極性障害の今後
K.病名
第2章 疫学と社会的影響
A.疫学
B.社会的影響
C.生命予後
D.双極性障害と犯罪
E.双極性障害と創造性
第3章 症状・経過
A.はじめに
B.躁状態
C.うつ状態
D.混合状態
E.軽躁状態
F.躁転・うつ転
G.精神病症状
H.緊張病症状
I.急速交代型
J.人格変化,閾値下気分症状
K.認知機能障害
L.衝動性
M.病前性格・気質
N.発達障害との併発
O.経過
第4章 診断
A.診断基準
B.診断の実際
第5章 治療戦略
A.総論-エビデンスに基づいた治療を目指すために
B.躁状態の治療
C.うつ状態の治療
D.修正型電気けいれん療法
E.その他の身体療法
F.自殺予防
G.維持療法-双極I型障害
H.心理社会的治療
I.双極II型障害の治療
J.急速交代型の治療
K.新薬,サプリメント,あるいは食事療法
L.妊娠・出産
第6章 治療薬とその薬理
A.気分安定薬とは何か
B.リチウム
C.バルプロ酸
D.カルバマゼピン
E.オランザピン
F.ラモトリギン
G.クエチアピン
H.アリピプラゾール
I.ゾテピン
J.リスペリドン
K.その他
L.ベンゾジアゼピン
M.抗うつ薬
第7章 ゲノム研究
A.遺伝の関与
B.連鎖解析
C.関連解析
D.G72
E.関連研究における再現性の欠如
F.エンドフェノタイプ
G.DNAマイクロアレイによる候補遺伝子探索
H.統合失調症との接点
I.ゲノムワイド関連研究
J.コピー数多型
K.まれな変異
第8章 脳研究
A.形態
B.生化学
C.機能
D.ゲノム・エピゲノム
第9章 バイオマーカー研究
A.はじめに
B.モノアミン
C.デキサメサゾン抑制試験
D.カルシウム
E.BDNF
F.培養リンパ芽球の遺伝子発現
G.酸化ストレスマーカー
H.免疫学的マーカー
第10章 病態仮説
A.はじめに
B.薬理学研究に基づく仮説
C.生物リズム仮説
D.小胞体ストレス反応障害仮説
E.ミトコンドリア機能障害仮説
おわりに
索引
A.症状の記載
B.疾患としての記載
C.反精神医学
D.非定型精神病概念の流れ
E.DSM-III
F.双極II型障害の登場
G.双極スペクトラム概念の登場
H.DSM-IV
I.特定不能の双極性障害
J.双極性障害の今後
K.病名
第2章 疫学と社会的影響
A.疫学
B.社会的影響
C.生命予後
D.双極性障害と犯罪
E.双極性障害と創造性
第3章 症状・経過
A.はじめに
B.躁状態
C.うつ状態
D.混合状態
E.軽躁状態
F.躁転・うつ転
G.精神病症状
H.緊張病症状
I.急速交代型
J.人格変化,閾値下気分症状
K.認知機能障害
L.衝動性
M.病前性格・気質
N.発達障害との併発
O.経過
第4章 診断
A.診断基準
B.診断の実際
第5章 治療戦略
A.総論-エビデンスに基づいた治療を目指すために
B.躁状態の治療
C.うつ状態の治療
D.修正型電気けいれん療法
E.その他の身体療法
F.自殺予防
G.維持療法-双極I型障害
H.心理社会的治療
I.双極II型障害の治療
J.急速交代型の治療
K.新薬,サプリメント,あるいは食事療法
L.妊娠・出産
第6章 治療薬とその薬理
A.気分安定薬とは何か
B.リチウム
C.バルプロ酸
D.カルバマゼピン
E.オランザピン
F.ラモトリギン
G.クエチアピン
H.アリピプラゾール
I.ゾテピン
J.リスペリドン
K.その他
L.ベンゾジアゼピン
M.抗うつ薬
第7章 ゲノム研究
A.遺伝の関与
B.連鎖解析
C.関連解析
D.G72
E.関連研究における再現性の欠如
F.エンドフェノタイプ
G.DNAマイクロアレイによる候補遺伝子探索
H.統合失調症との接点
I.ゲノムワイド関連研究
J.コピー数多型
K.まれな変異
第8章 脳研究
A.形態
B.生化学
C.機能
D.ゲノム・エピゲノム
第9章 バイオマーカー研究
A.はじめに
B.モノアミン
C.デキサメサゾン抑制試験
D.カルシウム
E.BDNF
F.培養リンパ芽球の遺伝子発現
G.酸化ストレスマーカー
H.免疫学的マーカー
第10章 病態仮説
A.はじめに
B.薬理学研究に基づく仮説
C.生物リズム仮説
D.小胞体ストレス反応障害仮説
E.ミトコンドリア機能障害仮説
おわりに
索引
書評
開く
研修医,専門医,研究者にとってバイブル的存在価値のある書籍
書評者: 山脇 成人 (広島大大学院教授・精神神経医科学)
双極性障害(躁うつ病)について評価の高かった初版が出版され12年を経過した。その間に社会情勢の変化や脳科学の進歩に伴い双極性障害に関する認識や知識も大きく変化し,改訂が望まれていた。初版当時は,双極性障害という病名に違和感を覚えていた精神科医は少なくなかったが,今では一般にも浸透しつつある。著者が精神科医になったときから個人的に懇意にさせていただいているが,当初から双極性障害に強い関心を持ち,臨床および病態研究に情熱を注いでこられたわが国におけるこの領域の第一人者である。
今回の全面改訂では,膨大な文献に基づいて双極性障害の疫学,疾病概念,診断,治療,病態に関して実にわかりやすくかみ砕いてまとめてあり,研修医にとっても読破することは不可能でないであろう。
一方で,記載されている内容はキャリアを積んだ精神科専門医や研究者にとっても大変有用な内容がふんだんに盛り込まれている。この種の専門書では,ともすると欧米の文献の紹介に終始する傾向があるが,本書は日本の論文も多く引用し,わが国の実際の臨床に役立つ実践書でもあることが特徴である。
著者は,現在は理化学研究所という研究機関で双極性障害の病態研究に全力を注ぎ,ゲノム解析,モデル動物,死後脳解析などの分子病態研究を展開し,インパクトの高い多数の論文を発表しているが,一方で双極性障害の患者さんや家族とも直接触れ合い,そのニーズを謙虚に受け止め,研究成果を患者さんに還元することを常に念頭に置きつつ研究を展開されている点が尊敬に値する。
本書の最後に記載されている双極性障害のミトコンドリア機能異常仮説は,著者が提唱したオリジナルの仮説である。当初は,あまり話題になることはなかったが,ハーバード大学の研究グループが行った死後脳研究によりミトコンドリア関連遺伝子の変化が報じられてから一躍注目を浴びるようになり,ミトコンドリア病の治療薬を双極性障害に応用する臨床研究も展開されるなど,著者の仮説は国際的に高く評価され,今や多くの国際学会での招待講演,国際雑誌での総説依頼を受けるなど,日本の精神医学の国際的プレゼンス向上に大きく貢献している。
双極性障害は,著名な芸術家,科学者,実業家が罹患しており,知的レベルの高い人々を脅かす疾患であり,その社会的影響は甚大であるため,この疾患の病態解明とそれに基づく治療法の開発は急務である。本書はこうした社会的要請に応えるべく生まれた,研修医,一般臨床医,精神科専門医,研究者のバイブル的存在価値のある著書といっても過言ではない。
双極性障害のフロントラインをくまなく眺望できる珠玉の書
書評者: 神庭 重信 (九大大学院医学研究院教授・精神病態医学)
双極性障害は,若年で発症し,慢性に経過しやすい疾患である。うつ病相は治療抵抗性で遷延しがちである。そうかと思えば,たちまち躁転してしまい,浪費を重ねたり,上司や家族に向かって怒鳴り散らしたりして,家族が困って急に連絡がきたりもする。治療がうまく進み,何年も安定していたからといって気分安定薬を中止すると,しばらくして多弁となりあちこち旅行に行きだしたりして,あわてて投薬を再開することになる。しかも双極性障害は,寿命・健康損失の大きさ(DALY)では,うつ病,認知症,統合失調症に次ぐ精神障害である。精神科医にとって,双極性障害の診断のための知識は必須であり,気分安定薬を使いこなせることは最低限求められる技術であろう。
著者の加藤忠史氏は,ここで紹介するまでもなく,わが国を代表する双極性障害の研究者である。彼のトップクラスの研究から導かれたミトコンドリア機能障害仮説(酸化ストレス仮説)は,国際的に高く評価されており,病態仮説に則った新薬の臨床開発が進められている。一連の研究の発端は,双極性障害の患者の脳内にミトコンドリア機能の異常と一致する所見を見いだしたことに始まると聞く。本書のおよそ3分の1が臨床精神薬理学と神経科学の病態仮説で占められているのも,彼の本ならではの特徴であろう。しかしながら,本書を一読するならば,加藤氏が双極性障害の臨床にも精通していることがよくわかる。その豊富な経験から,心理社会的治療の重要性が幾度となく強調されており,疾患教育なくして双極性障害の治療は成り立たないと言い切る。
初版から12年を経て改訂された本書は,臨床のエビデンスと基礎的知見を盛り込んで,330ページに及ぶテキストとなっている。広範なトピックスが,簡潔かつ正確にまとめられており,しかもそのレベルは妥協を許していない。もう一つの特徴は,生き生きとした自験例が全章にわたりちりばめられ,本文の記述を補っていることである。読者は,症例を読みながら,悪戦苦闘する著者の姿に同感したり,あるいは見事に難局を切り抜ける著者に拍手を送りたくなるだろう。しかしなんといっても珠玉の章は,治療戦略と題された第5章である。基本的にはエビデンス重視で治療論が展開されるのだが,随所に,エビデンスからは決して生まれない著者の臨床の技が披露されている。入院したがらない躁病の患者をどのように入院へと導くか,長期にわたる服薬をどう続けてもらうか,病状が不安定になり自分が何をしているかわからなくなったときどうするかなど,臨床の知が次から次へと紹介されている。
このように,本書は,双極性障害の入門書としてまぎれもなく秀逸なだけでなく,経験ある精神科医にとっても,重要な最新情報をもれなく知っておく上で恰好な文献となっている。いずれにせよ,本書を読み終えたとき,読者は双極性障害のフロントラインをくまなく眺望したことになる。
書評者: 山脇 成人 (広島大大学院教授・精神神経医科学)
双極性障害(躁うつ病)について評価の高かった初版が出版され12年を経過した。その間に社会情勢の変化や脳科学の進歩に伴い双極性障害に関する認識や知識も大きく変化し,改訂が望まれていた。初版当時は,双極性障害という病名に違和感を覚えていた精神科医は少なくなかったが,今では一般にも浸透しつつある。著者が精神科医になったときから個人的に懇意にさせていただいているが,当初から双極性障害に強い関心を持ち,臨床および病態研究に情熱を注いでこられたわが国におけるこの領域の第一人者である。
今回の全面改訂では,膨大な文献に基づいて双極性障害の疫学,疾病概念,診断,治療,病態に関して実にわかりやすくかみ砕いてまとめてあり,研修医にとっても読破することは不可能でないであろう。
一方で,記載されている内容はキャリアを積んだ精神科専門医や研究者にとっても大変有用な内容がふんだんに盛り込まれている。この種の専門書では,ともすると欧米の文献の紹介に終始する傾向があるが,本書は日本の論文も多く引用し,わが国の実際の臨床に役立つ実践書でもあることが特徴である。
著者は,現在は理化学研究所という研究機関で双極性障害の病態研究に全力を注ぎ,ゲノム解析,モデル動物,死後脳解析などの分子病態研究を展開し,インパクトの高い多数の論文を発表しているが,一方で双極性障害の患者さんや家族とも直接触れ合い,そのニーズを謙虚に受け止め,研究成果を患者さんに還元することを常に念頭に置きつつ研究を展開されている点が尊敬に値する。
本書の最後に記載されている双極性障害のミトコンドリア機能異常仮説は,著者が提唱したオリジナルの仮説である。当初は,あまり話題になることはなかったが,ハーバード大学の研究グループが行った死後脳研究によりミトコンドリア関連遺伝子の変化が報じられてから一躍注目を浴びるようになり,ミトコンドリア病の治療薬を双極性障害に応用する臨床研究も展開されるなど,著者の仮説は国際的に高く評価され,今や多くの国際学会での招待講演,国際雑誌での総説依頼を受けるなど,日本の精神医学の国際的プレゼンス向上に大きく貢献している。
双極性障害は,著名な芸術家,科学者,実業家が罹患しており,知的レベルの高い人々を脅かす疾患であり,その社会的影響は甚大であるため,この疾患の病態解明とそれに基づく治療法の開発は急務である。本書はこうした社会的要請に応えるべく生まれた,研修医,一般臨床医,精神科専門医,研究者のバイブル的存在価値のある著書といっても過言ではない。
双極性障害のフロントラインをくまなく眺望できる珠玉の書
書評者: 神庭 重信 (九大大学院医学研究院教授・精神病態医学)
双極性障害は,若年で発症し,慢性に経過しやすい疾患である。うつ病相は治療抵抗性で遷延しがちである。そうかと思えば,たちまち躁転してしまい,浪費を重ねたり,上司や家族に向かって怒鳴り散らしたりして,家族が困って急に連絡がきたりもする。治療がうまく進み,何年も安定していたからといって気分安定薬を中止すると,しばらくして多弁となりあちこち旅行に行きだしたりして,あわてて投薬を再開することになる。しかも双極性障害は,寿命・健康損失の大きさ(DALY)では,うつ病,認知症,統合失調症に次ぐ精神障害である。精神科医にとって,双極性障害の診断のための知識は必須であり,気分安定薬を使いこなせることは最低限求められる技術であろう。
著者の加藤忠史氏は,ここで紹介するまでもなく,わが国を代表する双極性障害の研究者である。彼のトップクラスの研究から導かれたミトコンドリア機能障害仮説(酸化ストレス仮説)は,国際的に高く評価されており,病態仮説に則った新薬の臨床開発が進められている。一連の研究の発端は,双極性障害の患者の脳内にミトコンドリア機能の異常と一致する所見を見いだしたことに始まると聞く。本書のおよそ3分の1が臨床精神薬理学と神経科学の病態仮説で占められているのも,彼の本ならではの特徴であろう。しかしながら,本書を一読するならば,加藤氏が双極性障害の臨床にも精通していることがよくわかる。その豊富な経験から,心理社会的治療の重要性が幾度となく強調されており,疾患教育なくして双極性障害の治療は成り立たないと言い切る。
初版から12年を経て改訂された本書は,臨床のエビデンスと基礎的知見を盛り込んで,330ページに及ぶテキストとなっている。広範なトピックスが,簡潔かつ正確にまとめられており,しかもそのレベルは妥協を許していない。もう一つの特徴は,生き生きとした自験例が全章にわたりちりばめられ,本文の記述を補っていることである。読者は,症例を読みながら,悪戦苦闘する著者の姿に同感したり,あるいは見事に難局を切り抜ける著者に拍手を送りたくなるだろう。しかしなんといっても珠玉の章は,治療戦略と題された第5章である。基本的にはエビデンス重視で治療論が展開されるのだが,随所に,エビデンスからは決して生まれない著者の臨床の技が披露されている。入院したがらない躁病の患者をどのように入院へと導くか,長期にわたる服薬をどう続けてもらうか,病状が不安定になり自分が何をしているかわからなくなったときどうするかなど,臨床の知が次から次へと紹介されている。
このように,本書は,双極性障害の入門書としてまぎれもなく秀逸なだけでなく,経験ある精神科医にとっても,重要な最新情報をもれなく知っておく上で恰好な文献となっている。いずれにせよ,本書を読み終えたとき,読者は双極性障害のフロントラインをくまなく眺望したことになる。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。