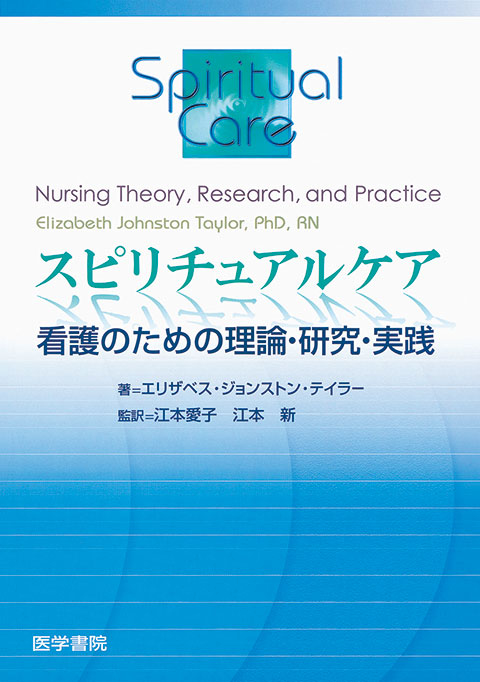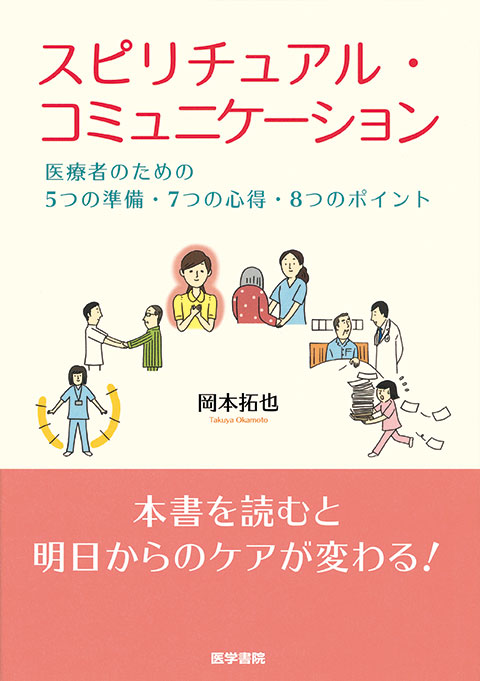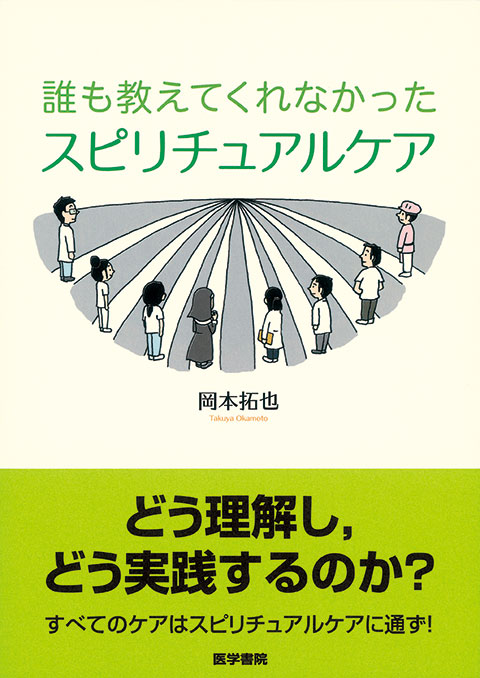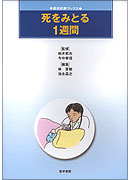スピリチュアルケア
看護のための理論・研究・実践
公平な視点からスピリチュアルケアの理論と実践を解説
もっと見る
スピリチュアルケアは看護診断の1つとして取り上げられており、ナースの重要な役割になりつつある。本書には、スピリチュアルケアを初めて試みる人にも役立つ実際的なヒントと実例が豊富に紹介されている。また特定の宗教をもたないナースにもできるケアの方法が示されている。文献と研究に基づいた確かな実践を展開。
| 著 | エリザベス・ジョンストン・テイラー |
|---|---|
| 監訳 | 江本 愛子 / 江本 新 |
| 発行 | 2008年01月判型:A5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-00536-4 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
推薦のことば(日野原重明)/日本語版へのメッセージ(原著者)/監訳者まえがき
推薦のことば
看護の理論と実践と研究法についての多年の経歴をもつロマリンダ大学の教職にあるエリザベス・ジョンストン・テイラー博士は,同大学がアドベンチスト派のキリスト教主義の背景をもつ大学であるだけに,スピリチュアルケアを重視する環境のなかで教職活動をされてきたものと思う.こうした環境のなかで,スピリチュアリティの本質を探究しながら,この面を重視した看護ケアがいかに実践され,研究されるべきかを著者は理論的に探求し本書をまとめられた.
スピリチュアリティという概念をWHOの健康憲章のなかに取り入れるべきだと提言したのは,オックスフォードの独立型ホスピスのSobell Houseの所長をされWHOのコンサルタントでもあるロバート・トワイクロス博士である.彼はシシリー・ソンダース医師と共にホスピス運動の世界的先駆者であり,1958年に設定されたWHOの健康の憲章のなかに,「身体的,精神的,社会的なwell-being〈安寧〉に加えてspiritualという霊的側面を付加すべき」ことを1998年の理事会に提言した.しかし,日本を含め,2, 3の国の賛同が得られなかったため,これはそのまま凍結されて,今日に至っている.
彼はホスピスケアのなかでは死の近い患者を霊的な環境のなかに置くことの重要性を説かれたのである.彼は,何かの宗教的信仰のある人のほかに,一定の宗教をもたない患者でも人間の本性のなかには隠れて存在する深い魂が秘められていると考えたからである.
著者は,欧米の宗教に限らず,仏教を含む世界の五大宗教の信条,儀式,慣習をもよく研究されている.その結果として,いろいろな宗教をもつ患者,またこれという特殊な宗教をもたない人でも,その心の根底に存在するあるものを引き出し,看護の実践のなかにスピリチュアルケアを行うアートについての研究の成果を書かれたのである.
日本人にとっての宗教は,仏教が圧倒的に多数であり,キリスト教信者は国民のわずか1%に過ぎない.本当の宗教的信仰をもつものの数は日本では非常に少ないといわれているが,しかし,根源的な魂の存在を体感している人々の数は決して少なくないであろう.
聖職者が入院中の病者に霊的な指導をする訓練が,英米の病院では行われている.これはpastoral careといわれるが,その方法論には看護者によるスピリチュアルケアに合一されるものがあるように思う.
日本人が何らかの病気にかかったり,または死が近づいたりしたとき,ナースは看護の専門職としてきめ細かいケアが要請される.人間の心の底に存在するスピリチュアリティを大切にして,スピリチュアルな面からどうすれば個別的,または即応的なケアがなされるかの実践のアートとこれを研究するための理論が本書には丁寧に説明されている.その意味で看護の教官や研究者にはもちろんのこと,一般の臨床ナースにも本書が広く読まれることを期待したい.
その翻訳には難解な箇所があったと思うが,これをわかりやすく翻訳する上で監修された江本愛子氏と江本新氏のご努力に感謝し,また,このような書を出版に導かれた医学書院の七尾清・石井伸和の両氏にも敬意を表したい.
聖路加国際病院名誉院長
聖路加看護大学名誉学長
日野原重明
日本語版へのメッセージ
最良の看護ケアは癒しです.癒しは体と心のケアだけでなく,まさにその人の存在の内核にあるもの,つまりスピリットのケアを必要とします.何世紀も前にプラトンは,次のように記しています.
「頭部のない目,あるいは体部のない頭に治療を試みるべきではないように,魂(心)を見ずして肉体を治療すべきではありません.なぜなら,全体が健康でなければ部分は決して健康ではないからです.したがって,頭も体も健康であるためには,まず魂(心)の癒しから始めなければなりません」(プラトンの対話編「カルミデス-克己節制について」より).
人間が人の魂を癒すというような考えは毛頭受け入れられるものではありませんが,私はナースとして,病いにある人の魂やスピリットを心からケアしたいと思っています.このスピリチュアルな次元のケアを追い求める自らの遍歴のなかで学んできたことを,読者の方々と共有できることは大きな喜びです.他者の心の支えになろうとするとき,自分も同じものをいただいていることを私は知りました.たとえ疲れきっているときでも,身も心もエネルギーと生気をいただき,平安のうちに何かが変わったことを自覚するのです.これは私だけでなく,きっと読者の皆様の経験ともなることでしょう.
この本が,ご自分や他者のスピリチュアルヘルス(心の健康)を願うあなたのお助けになることを願っております.
Elizabeth Johnston Taylor, PhD, RN
監訳者まえがき
本書は,エリザベス・ジョンストン・テイラー博士によるSpiritual Care : Nursing Theory, Research, and Practiceの訳書です.著者自身が本書の序文で述べているように,西洋とユダヤ=キリスト教の文化背景をもちながら,人々の多様なスピリチュアルの体験をことのほか大切にしつつ,スピリチュアルの問題を丁寧に提示しています.世界の5大宗教の信条,儀式,慣習との関係を扱った原書の第10章は詳細すぎるため割愛することになりました.
1998年,WHOの執行理事会において「スピリチュアルな健康-Spiritual well-being」を加える憲章改定案が用意されて以来,わが国でもこのテーマへの関心が一挙に高まってきました.文部科学省委託事業の1つに,「医療現場のなかでの宗教および霊性(スピリチュアリティ)をいかに実用的に概念化できるか」について,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」)における現状分析の研究報告もみられます.また,キリスト教系や仏教系などの聖職者,学者,実践家の間でスピリチュアルケアに関する学会,研修会,講演会などが行われ多面的に議論が深められてきました.
もとより,アメリカにおけるヘルスケア環境は日本のそれとは異なり,本書の内容はそうした文化背景の視点から理解されなければならないでしょう.とはいえ,著者は,スピリチュアリティは1人ひとりに付与された天賦の特質であり,スピリチュアルケアは宗教や文化を越えた普遍的なもの,そして人間の根源的な次元にかかわるものであるという立場をとっています.
『スピリチュアルケア-看護のための理論・研究・実践』と題した本書は,著名な看護理論家のみならず関連学際の顕著な学説の要点を幅広く取り込みながら,この種の概念や問題を深く掘り下げており,スピリチュアルヘルスに関心をもつ人,これからヘルスケアに携わろうとする人々にとっても,貴重な文献となるに違いありません.
本書の特色は,スピリチュアルケアにかかわる理論だけでなく,倫理的配慮を含め実践に役立つ方法論について事例やストーリーを交えてわかりやすく提示していることです.章ごとに要点がまとめられ,章末は「看護実践への示唆」,「要点整理」,「考察課題」で締めくくられています.
翻訳に着手してから思いのほか月日を要したにもかかわらず,関心を寄せていただいた医学書院の常務取締役七尾清氏,特に,忍耐をもって支え1つ1つに適切なアドバイスをいただいた看護出版部3課の石井伸和氏,本書の内容にふさわしい仕上げをしてくださった制作部3課の森本成氏に心から感謝申し上げます.
2007年11月
江本 愛子
江本 新
推薦のことば
看護の理論と実践と研究法についての多年の経歴をもつロマリンダ大学の教職にあるエリザベス・ジョンストン・テイラー博士は,同大学がアドベンチスト派のキリスト教主義の背景をもつ大学であるだけに,スピリチュアルケアを重視する環境のなかで教職活動をされてきたものと思う.こうした環境のなかで,スピリチュアリティの本質を探究しながら,この面を重視した看護ケアがいかに実践され,研究されるべきかを著者は理論的に探求し本書をまとめられた.
スピリチュアリティという概念をWHOの健康憲章のなかに取り入れるべきだと提言したのは,オックスフォードの独立型ホスピスのSobell Houseの所長をされWHOのコンサルタントでもあるロバート・トワイクロス博士である.彼はシシリー・ソンダース医師と共にホスピス運動の世界的先駆者であり,1958年に設定されたWHOの健康の憲章のなかに,「身体的,精神的,社会的なwell-being〈安寧〉に加えてspiritualという霊的側面を付加すべき」ことを1998年の理事会に提言した.しかし,日本を含め,2, 3の国の賛同が得られなかったため,これはそのまま凍結されて,今日に至っている.
彼はホスピスケアのなかでは死の近い患者を霊的な環境のなかに置くことの重要性を説かれたのである.彼は,何かの宗教的信仰のある人のほかに,一定の宗教をもたない患者でも人間の本性のなかには隠れて存在する深い魂が秘められていると考えたからである.
著者は,欧米の宗教に限らず,仏教を含む世界の五大宗教の信条,儀式,慣習をもよく研究されている.その結果として,いろいろな宗教をもつ患者,またこれという特殊な宗教をもたない人でも,その心の根底に存在するあるものを引き出し,看護の実践のなかにスピリチュアルケアを行うアートについての研究の成果を書かれたのである.
日本人にとっての宗教は,仏教が圧倒的に多数であり,キリスト教信者は国民のわずか1%に過ぎない.本当の宗教的信仰をもつものの数は日本では非常に少ないといわれているが,しかし,根源的な魂の存在を体感している人々の数は決して少なくないであろう.
聖職者が入院中の病者に霊的な指導をする訓練が,英米の病院では行われている.これはpastoral careといわれるが,その方法論には看護者によるスピリチュアルケアに合一されるものがあるように思う.
日本人が何らかの病気にかかったり,または死が近づいたりしたとき,ナースは看護の専門職としてきめ細かいケアが要請される.人間の心の底に存在するスピリチュアリティを大切にして,スピリチュアルな面からどうすれば個別的,または即応的なケアがなされるかの実践のアートとこれを研究するための理論が本書には丁寧に説明されている.その意味で看護の教官や研究者にはもちろんのこと,一般の臨床ナースにも本書が広く読まれることを期待したい.
その翻訳には難解な箇所があったと思うが,これをわかりやすく翻訳する上で監修された江本愛子氏と江本新氏のご努力に感謝し,また,このような書を出版に導かれた医学書院の七尾清・石井伸和の両氏にも敬意を表したい.
聖路加国際病院名誉院長
聖路加看護大学名誉学長
日野原重明
日本語版へのメッセージ
最良の看護ケアは癒しです.癒しは体と心のケアだけでなく,まさにその人の存在の内核にあるもの,つまりスピリットのケアを必要とします.何世紀も前にプラトンは,次のように記しています.
「頭部のない目,あるいは体部のない頭に治療を試みるべきではないように,魂(心)を見ずして肉体を治療すべきではありません.なぜなら,全体が健康でなければ部分は決して健康ではないからです.したがって,頭も体も健康であるためには,まず魂(心)の癒しから始めなければなりません」(プラトンの対話編「カルミデス-克己節制について」より).
人間が人の魂を癒すというような考えは毛頭受け入れられるものではありませんが,私はナースとして,病いにある人の魂やスピリットを心からケアしたいと思っています.このスピリチュアルな次元のケアを追い求める自らの遍歴のなかで学んできたことを,読者の方々と共有できることは大きな喜びです.他者の心の支えになろうとするとき,自分も同じものをいただいていることを私は知りました.たとえ疲れきっているときでも,身も心もエネルギーと生気をいただき,平安のうちに何かが変わったことを自覚するのです.これは私だけでなく,きっと読者の皆様の経験ともなることでしょう.
この本が,ご自分や他者のスピリチュアルヘルス(心の健康)を願うあなたのお助けになることを願っております.
Elizabeth Johnston Taylor, PhD, RN
監訳者まえがき
本書は,エリザベス・ジョンストン・テイラー博士によるSpiritual Care : Nursing Theory, Research, and Practiceの訳書です.著者自身が本書の序文で述べているように,西洋とユダヤ=キリスト教の文化背景をもちながら,人々の多様なスピリチュアルの体験をことのほか大切にしつつ,スピリチュアルの問題を丁寧に提示しています.世界の5大宗教の信条,儀式,慣習との関係を扱った原書の第10章は詳細すぎるため割愛することになりました.
1998年,WHOの執行理事会において「スピリチュアルな健康-Spiritual well-being」を加える憲章改定案が用意されて以来,わが国でもこのテーマへの関心が一挙に高まってきました.文部科学省委託事業の1つに,「医療現場のなかでの宗教および霊性(スピリチュアリティ)をいかに実用的に概念化できるか」について,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」)における現状分析の研究報告もみられます.また,キリスト教系や仏教系などの聖職者,学者,実践家の間でスピリチュアルケアに関する学会,研修会,講演会などが行われ多面的に議論が深められてきました.
もとより,アメリカにおけるヘルスケア環境は日本のそれとは異なり,本書の内容はそうした文化背景の視点から理解されなければならないでしょう.とはいえ,著者は,スピリチュアリティは1人ひとりに付与された天賦の特質であり,スピリチュアルケアは宗教や文化を越えた普遍的なもの,そして人間の根源的な次元にかかわるものであるという立場をとっています.
『スピリチュアルケア-看護のための理論・研究・実践』と題した本書は,著名な看護理論家のみならず関連学際の顕著な学説の要点を幅広く取り込みながら,この種の概念や問題を深く掘り下げており,スピリチュアルヘルスに関心をもつ人,これからヘルスケアに携わろうとする人々にとっても,貴重な文献となるに違いありません.
本書の特色は,スピリチュアルケアにかかわる理論だけでなく,倫理的配慮を含め実践に役立つ方法論について事例やストーリーを交えてわかりやすく提示していることです.章ごとに要点がまとめられ,章末は「看護実践への示唆」,「要点整理」,「考察課題」で締めくくられています.
翻訳に着手してから思いのほか月日を要したにもかかわらず,関心を寄せていただいた医学書院の常務取締役七尾清氏,特に,忍耐をもって支え1つ1つに適切なアドバイスをいただいた看護出版部3課の石井伸和氏,本書の内容にふさわしい仕上げをしてくださった制作部3課の森本成氏に心から感謝申し上げます.
2007年11月
江本 愛子
江本 新
目次
開く
第I部 看護におけるスピリチュアリティを探し求めて
第1章 スピリチュアリティとは
第2章 スピリチュアルケア提供の基礎
第3章 スピリチュアルな側面の自己認識とクライエントケア
第II部 心のケア-実践への適用
第4章 心の癒しを支えるコミュニケーション
第5章 スピリチュアルアセスメント
第6章 スピリチュアルニーズの看護ケア
第7章 人生の意味探しへのスピリチュアルサポート
第8章 看護の役割-スピリチュアルケア・スペシャリストとの協働
第III部 スピリチュアルヘルスを助長する
第9章 スピリチュアルヘルスをサポートする儀式
第10章 スピリチュアリティを育む
索引
第1章 スピリチュアリティとは
第2章 スピリチュアルケア提供の基礎
第3章 スピリチュアルな側面の自己認識とクライエントケア
第II部 心のケア-実践への適用
第4章 心の癒しを支えるコミュニケーション
第5章 スピリチュアルアセスメント
第6章 スピリチュアルニーズの看護ケア
第7章 人生の意味探しへのスピリチュアルサポート
第8章 看護の役割-スピリチュアルケア・スペシャリストとの協働
第III部 スピリチュアルヘルスを助長する
第9章 スピリチュアルヘルスをサポートする儀式
第10章 スピリチュアリティを育む
索引
書評
開く
実践に役立つ具体的な方策,ヒントが得られる
書評者: 古橋 洋子 (前・埼玉医科大学短期大教授)
「スピリチュアルケア」は大切で必要なものと思いながらも,いざ実践となると,どんな方法が考えられるのだろうと思い悩む看護師が多いことと思う。しかし本書は,その疑問を解決する多くの示唆を与えてくれる。
本書は,スピリチュアルケアを行う際に必要な,実際に役立つ手引書となることを意図している。3部構成の第I部は看護におけるスピリチュアリティの問題を探求しながら,第II部の土台となる基本的知識を示している。第II部では,スピリチュアルケアの提供を支援するための看護の実践とその方略が,具体的な事例を含めて述べられている。第III部では,クライエントのスピリチュアルヘルスを高めるための介入方法が示されている。
スピリチュアルケアはクライエントの私的側面にかかわらざるを得ず,看護師には豊かな感受性が求められる。そのため,本当のところは避けて通りたいという思いが看護師の中にあるように思う。そのような看護師に対しても,心のケアや癒しを支えるコミュニケーション,これまで言われている「共にいること」の意味の深さ,思いやりのある態度の示し方など,実践への具体的な対応が示されている。現在ホスピスケアで悩んでいる方には,大いに参考になると思う。
スピリチュアルアセスメントについては,ガイドラインやその方略が示されており,看護師が苦手としているアセスメントを看護モデルを使いながら解説を深めている。患者には大変デリケートな問題であることを理解して,ナースとクライエント間のラポールと信頼関係が確立してからアプローチをするなど,細かな面の配慮が具体的に提案されている。アセスメントの結果による診断では,NANDAインターナショナルが開発した診断名や診断指標,そして看護介入まで含めてあるので,実践する際に心強い助けとなる。
患者と直接かかわりを持つなかで,患者から「人生に対しての意味付け」について質問を受けることがよくあるが,これは,看護師がいちばん頭を悩ませることの1つでもある。そのような人生の意味などを問われると,看護師は患者に接することを最小限に抑えようとして,患者の部屋から遠のいてしまうということをよく耳にするが,そのような現象を避けることができる的確なアドバイスが示されている。
また,スピリチュアルヘルスをサポートする儀式についても説明が加えられており,祈りの仕方や祈りの効果,瞑想についての解説などは,宗教に詳しくない者にとって大いに参考になる。さらに,聖職者やチャプレンなどスピリチュアルケア・スペシャリストとの協働,友人や家族のサポートを患者ケアにどのように生かしていくかも解説されている。スピリチュアリティを育む方法として「日記事始めのアイデア」も提案されており,臨床のナースには大きなヒントになると思う。
訳文は,翻訳書とは思えないくらい理解しやすくスーッと読み進むことができる。監訳者の1人である江本新氏は神学出身であり,全人的医療を目的とした,チャプレンが常勤している病院の設立に携わられた経験があり,ホスピスケアとのかかわりも深く,日本人の心理をよく理解したうえでの翻訳が,読者にとって大変読みやすいものになっている。
書評者: 古橋 洋子 (前・埼玉医科大学短期大教授)
「スピリチュアルケア」は大切で必要なものと思いながらも,いざ実践となると,どんな方法が考えられるのだろうと思い悩む看護師が多いことと思う。しかし本書は,その疑問を解決する多くの示唆を与えてくれる。
本書は,スピリチュアルケアを行う際に必要な,実際に役立つ手引書となることを意図している。3部構成の第I部は看護におけるスピリチュアリティの問題を探求しながら,第II部の土台となる基本的知識を示している。第II部では,スピリチュアルケアの提供を支援するための看護の実践とその方略が,具体的な事例を含めて述べられている。第III部では,クライエントのスピリチュアルヘルスを高めるための介入方法が示されている。
スピリチュアルケアはクライエントの私的側面にかかわらざるを得ず,看護師には豊かな感受性が求められる。そのため,本当のところは避けて通りたいという思いが看護師の中にあるように思う。そのような看護師に対しても,心のケアや癒しを支えるコミュニケーション,これまで言われている「共にいること」の意味の深さ,思いやりのある態度の示し方など,実践への具体的な対応が示されている。現在ホスピスケアで悩んでいる方には,大いに参考になると思う。
スピリチュアルアセスメントについては,ガイドラインやその方略が示されており,看護師が苦手としているアセスメントを看護モデルを使いながら解説を深めている。患者には大変デリケートな問題であることを理解して,ナースとクライエント間のラポールと信頼関係が確立してからアプローチをするなど,細かな面の配慮が具体的に提案されている。アセスメントの結果による診断では,NANDAインターナショナルが開発した診断名や診断指標,そして看護介入まで含めてあるので,実践する際に心強い助けとなる。
患者と直接かかわりを持つなかで,患者から「人生に対しての意味付け」について質問を受けることがよくあるが,これは,看護師がいちばん頭を悩ませることの1つでもある。そのような人生の意味などを問われると,看護師は患者に接することを最小限に抑えようとして,患者の部屋から遠のいてしまうということをよく耳にするが,そのような現象を避けることができる的確なアドバイスが示されている。
また,スピリチュアルヘルスをサポートする儀式についても説明が加えられており,祈りの仕方や祈りの効果,瞑想についての解説などは,宗教に詳しくない者にとって大いに参考になる。さらに,聖職者やチャプレンなどスピリチュアルケア・スペシャリストとの協働,友人や家族のサポートを患者ケアにどのように生かしていくかも解説されている。スピリチュアリティを育む方法として「日記事始めのアイデア」も提案されており,臨床のナースには大きなヒントになると思う。
訳文は,翻訳書とは思えないくらい理解しやすくスーッと読み進むことができる。監訳者の1人である江本新氏は神学出身であり,全人的医療を目的とした,チャプレンが常勤している病院の設立に携わられた経験があり,ホスピスケアとのかかわりも深く,日本人の心理をよく理解したうえでの翻訳が,読者にとって大変読みやすいものになっている。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。